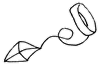
アリア・ムーシカはその建物を下から上まで眺めると、ほおと疲れたように嘆息した。
見るからに異様な存在感を持つ建物だった。
とりわけ大きいというわけでもない。幅にしてアリアの歩幅で十数歩、高さも精々彼の兄が五人分かそこら。家というのには少し小さいと感じてしまうくらいの建物だった。
それが、夕暮れのオレンジ色を浴びて、影のような漆黒の威容をさらしていた。
あたりに他の建物の姿はない。村の外れ、他の建物から幾分離れた林の中にその建物はひっそりと佇んでいた。
使われている材木は黒檀だろうか。見るからに緻密で重そうな木材の表面は、職人によって丹念に磨き上げられただろう滑らかなつやを見せており、思わず手を伸ばして触ってみたくなる。
「こら、何やってんだ、騎士様」
「ひゃっ!?」
不意打ちのような呆れ声に出していた手を慌てて引っ込める。肩越しにちらりと振り返ってみると、彼女をここまで案内してきてくれた森林警備隊の隊員、シラム・リストゥーバが奇妙に眉をひそめてこちらを見つめていた。
「あ、えーと……、り、立派な建物ですよね」
「ふぅん、やっぱり人間にはそう見えるのか?」
「え、それはどういう……」
問い返そうとして、アリアは思わず息を呑んでいた。
彼女のすぐ後ろで同じようにしてその建物を見上げているシラムの表情は、まるで相手に呪いでもかけようとしているかのように険しいものだった。
両眉の間に深いしわを刻み、憎しみのこもった視線を投げかける。それは凡そ人が建物に対して抱く感情の度を超えているように思われた。
「あの、どうしたんですか?」
「……なんでもない。それより騎士様、この建物はやっぱり良い建物なのか?」
吐き捨てるように言うその態度は決して”なんでもない”ものでは無かったが、そう言いきられてしまった以上アリアにはそれより追及する理由もない。
自分には関係のないこととあっさり結論づけて、シラムの質問に答えることにする。
「まあ、少なくとも悪い建物ではないですよ。重い木材を上手くいかした丈夫そうな建物ですし、これならちょっとやそっとの嵐が来たくらいじゃ何ともないでしょうね」
「……確かにな」
「それに、この建物は立地と方角が極めて良い」
そう言って、アリアは横方向へと視線をやる。春先の夕日はほぼ真西に沈もうとしている。その燃えるような鮮やかなオレンジが、建物の側面をまっすぐに照らしていた。直方体の建物はその四辺がほぼ東西南北を向いていると見える。
「この意味、分かりますか?」
「……いや」
「あれ、エルフならてっきり分かっていると思っていたんですけれども……。そんなものですか」
そう言って肩をすくめると、アリアは懐に一度右手を入れて、再び出すと自らの目の前に掌を水平にして構えた。
中指の付け根あたりから、先ほどシラムとの戦闘で使っていた振り子が垂れ下がっているのが見える。
目の前に取り出された武器を見て、シラムの表情が緊張を帯びる。
「あ、いえ、別に戦おうってわけじゃありません。これ、私の武器と言えば確かに武器なんですが、それよりも魔術の補助具としての役割の方が大きいんですよね」
言って、右手を自分の周りに円を描くように動かす。
一体何を、とシラムが訊ねる暇も与えないうちにそれは起きた。
「ほら、見てください」
そう言ってアリアが示す視線の先で、彼女の持つ振り子が大きくゆっくりと揺れていた。
まるでそこに何か目に見えない流れでもあるかのように、一漕ぎ一漕ぎブランコを漕いでいるかのように加速していく。勿論、彼女の手は一切特別な動きをしていない。
この振り子は今、種も仕掛けもなくその動きを激しくしていっているのだ。
「……それが、どうしたって言うんだ? 今更そんな小手先の魔術を見せられたって面白くも何ともないんだが」
種も仕掛けもない、と言われたところで、シラムは既にアリアが優秀な魔導士であると言うことを身を以て知っている。その程度の手品じみた魔術なら誰にも出来るのだし、今更そんなものを見せられても驚きはしない。
明らかにバカにした表情でつまらなげに振り子の往復を眺めるシラムを、アリアは呆れた様な表情で見つめた。
「貴方にはこれが魔術に見えるんですね。……というか私が魔術を使っているように見えるんですね。エルフは魔術に対して鈍感って言うのは聞いていましたけど、まさかこれほどとは思っても見ませんでした。はあ……、これじゃあ協会の判断も分からないでもないですね」
明らかにこちらをけなしているアリアの言葉に、シラムのこめかみが目に見えてひくつく。
「悪かったな、鈍感で。じゃあ鈍感な僕にも分かるようにその現象の意味を説明してくれよ、騎士様」
「構いませんよ。市民の知性を向上させるのも騎士たる者の務めですから。では、呪具としての振り子の特性からですね。私たちにとっては常識なんですけれども、呪具としての振り子は魔力の流れを感じ取って示してくれるという特性を持ちます。それは別にわざわざ魔術を行使しなくても起きる、ごくごく当たり前のことなんです」
ちらりとシラムの方を一瞥し、彼が何の反応も見せないのを見て取るとそのまま話を続ける。
「そこで、私の振り子、ナントスエルタを見てください。今振り子はどの方向に振れていますか?」
「……道と同じ方向じゃないのか?」
「そうですね。村からここまでの道の方向に沿うようにして触れています。この意味、分かりませんか?」
「分からないから聞いてるんだろうが」
いらだちを隠そうともしないシラムの声を満足げに聞くと、アリアは小さく頷いた。
「自分の蒙昧さを素直に認められるのは良いことですね」
「喧嘩売るのは良いからさっさと説明してくれ」
「あ、ええ、すいません。それでは続きですね。つまり、この振り子の振れる向きに魔力の流れがあるということなんですよ。分かりますか? 村から出てくる魔力の流れ、その行き着く先にこの建物があると言うことなんですよ」
「それの何が良いのか、今ひとつわからないんだが」
本当に分かっていないという表情で言葉を口にするシラムを、アリアはますます呆れた表情で凝視する。
シラムの本気を疑わんという勢いである。
「ここ、宝物庫なんですよね?」
肩をすくめてアリアが問う。
「そう言ったろう」
「宝物庫って言うことは、呪具とか置いてあるんですよね?」
「そりゃ、まあそうだろうな」
至極当たり前のことを訊ねるアリアの問いの意味を量りかねて、シラムは顔をしかめる。
一体この人間の魔導騎士は何を言おうとしているのか。全くもってさっぱり見当が付かない。
「……まあ、エルフなんて所詮そんなものですか」と再びエルフを小馬鹿にするような言葉を口にしてから、アリアはもったいつけるようにして言った。
「あのですね、呪具って言うのは魔力が豊潤な環境に置かれていたら、大抵その力を増すんです。なので、呪具保管庫というのはどこの魔導協会でも魔力の吹きだまりみたいになっている所に作るのが常識なんです。この宝物庫はその条件を満たしていて、エルフの村でこんなものを作っているなんて本当に驚いて感心していたんですけれども、肝心の住人がこれじゃあこの建物の方が可哀想というものですね」
「よく分からんが、まあ人間の流儀で建てられてるってことか」
一気に熱弁をまくし立てたアリアとは対照的に、先ほどの怒りすら消え去ってしまったかのような冷めた様子で、シラムは宝物庫を見上げた。
詰まらなそうに宝物庫の方を睨み付ける視線は、先ほどアリアが褒め言葉を口にした時に見せたものと同じものだった。
その態度の豹変振りに、アリアは首を傾げる。
「……あの、さっきもそんな目をしてましたけど、何か理由でもあるんですか?」
「理由なんて無いさ。別に理由なんて、な。考えてみれば当たり前だったんだよ。あんたら人間がこの建物を褒めるのなんて、至極当然の話さ。価値基準は結局一緒なんだから」
「……あの、言ってる意味がよく分からないんですけれども」
「そうか。じゃあ騎士様の為にわざわざかみ砕いて言ってやると、つまりこの建物を建てたのは人間だって言うことさ」
「え?」
予想もしていなかった言葉に、思わずアリアは口をぽかんと開けてシラムのことを見つめてしまった。
まるでそのことを口にしてしまったことそれ自体を嫌悪するかのように、苦虫をかみつぶしたような顔になるシラム。嫌なものをつばと一緒に地面に吐き出す。
「なんだ、今ので通じなかったか? もう同じようなことを口にするのは嫌だからな」
「え、あの……、そうじゃなくて、この建物を人間が建てたって本当ですか?」
「だからそう言っただろうが」
その話題に触れること自体が嫌、とでも言わんばかりの表情でそう吐き捨てるシラムを見ながら、アリアの頭には全く別の事柄が浮かんでいた。
確かにこの建物の配置は人間の魔法工学に照らしたら酷く合理的なもので、エルフが建てたと言われるよりは人間が建てたと言われる方が遙かに納得できる。
しかし、それはおかしいのだ。
この村に人間が建てた建物があると言うことは、
「アリア、何難しい顔してるんだ?」
不意に掛かった声に、顔を上げる。
見れば、宝物庫の前、階段を挟んだ露台から、彼女の兄であるジグ・ムーシカがこちらを不思議そうな表情で見つめていた。
「あ、兄様、いえ、大したことではありません」
そうだ。それほど気にかけることでもない。単に時が流れて、村の慣習が変わっただけかも知れない。或いは他にも理由があるのかも知れない。
とにかく、今自分たちが考えることでもない。
そう結論づけ、アリアは一人で納得した。
「それで、兄様、何か異常はありましたか?」
「いや、残念ながら何も無しだ。オーウェル氏にも協力して貰って色々調べてみたけど、特に奴らの痕跡のかけらも見あたらねえ。お前のことを疑うつもりはないんだが……、その、本当にここだったんだよな?」
「ええ、間違いありません」
地図を取り出す。
魔力によって瞬時に地形が描き出され、さらに自分たちの現在位置を示す光点が或る場所で明滅する。
そこは間違いなく先ほど彼女が《あちら側》の存在の魔力を確認した場所だ。
故に、ここに間違いなく《あちら側》の存在がいたはずなのだ。
しかし、その反応はいつの間にか消え去り、現場にも何の痕跡も残されてはいない。
こんな状況に陥ってしまったら、如何に己の技に自信を持つ百戦錬磨の魔術師であっても不安を覚えてしまうかも知れない。
しかしアリアは違った。
もとより自らの魔術を頼みにする姿勢は持っているが、それに絶対の信頼を寄せるなど言語道断。
「ひょっとしたら最初に検知した反応自体が間違いだったのかも知れません」
そう、あっさりと自らの過ちを認めて、アリアは溜息をついた。
その様子を見てシラムがここぞとばかりに口を開く。
「お、騎士様でもそんな風に失敗することがあるんだね」
しかし、アリアはと言うと、
「ええ、魔術に絶対なんてありませんから」
そんなことを爽やかな笑顔で言い、シラムの言葉に迷い無く頷いたのだった。
そんな態度を取られてしまうとどう反応して良いのか分からなくなってしまうシラム。
彼の内心の動揺を知ってか知らずか、アリアは言葉を続ける。
「私たちが魔術師である以上、重要なのは魔術を失敗しないようにすることではなく、失敗を如何にケアするかです。原因を究明し、解決を模索し、結果を改善する。ですよね、兄様?」
「ん、ああ、そうそう」
ジグの返答はいい加減なものだった。それに内心で怒りのあぶくが弾けそうになるのを感じて、アリアはじろりと兄を睨み付けた。
兄がこの手のことが苦手なのは充分分かった上で、アリアは敢えて問うていた。
いい加減この兄も騎士として一度性根をたたき直した方が良いと思うのだが、残念ながら彼女の兄は魔導騎士としては人並み以上には優秀であり大抵の難題は斜に構えたままで飄々とこなしてしまうのだった。
露台に無遠慮に座り込む兄を軽く睨み付け、アリアは訊ねた。
「それで、兄様、どうしましょうか?」
「えっとな、お前に任せるわ。どうするのが良いか決めてくれ」
「は?」
ジグの答えはアリアの予想を遥かに上回るものだった。
よもや自分に丸投げしてくるなど、一体どうして予想できただろうか。
「あのですね、兄様、騎士としてそのように仕事を投げ出すのはあってはならないことです!」
「じゃあ、お前が俺に判断を仰ぐのはどうなんだ?」
「私は、目上の兄様の方針を尊重するということで訊ねただけです。別に判断を投げ出す意図なんてありません」
アリアが顔を真っ赤にして叫ぶと、ジグはその様子を面白そうに見つめてポンと手を叩いた。
「じゃあ、俺は目上の者の判断として、今はアリアの考えに従った方が良いということで、お前に任す。何せこっちは二人が雑談している間色々調べて回ってたんだからな。ねえ、オーウェルさん」
「……ええ、まあ」
座り込んだジグの背後で、オーウェル・フィンチが苦笑しながら頷いた。
あの様子を見るからには恐らく探索というのも基本的にはオーウェルが行っていたのだろう。ジグのことだ。きっと本人はろくに何もしていないに違いない。
だが、シラムに色々な話をしていてその間のアリアが全くと言っていいほど仕事をしていなかったのは事実だ。
故に、先ほどのジグの言葉に対して反論をすることが出来ない。
こうなったら、言われた通り状況判断と行動決定を自分がやるしかあるまい。
そう諦めをつけて、改めて今の状況を確認しようとした時だ。
不意に、手元の地図が光った。

人間がこの村にいるなんて。
シャルシュ・ワイゼンには胸の鼓動が高鳴るのを抑えきる自信はなかった。
だって、この閉塞しきったエルフの村に、人間がいるのだ。こんなこと、何年ぶりだろうか。
ああ、考えるまでもない。十年ぶりだ。
その数字はごくごく自然にはじき出された。
何もかもが崩壊したあの時から丁度十年。忘れたくても忘れられない思い出の中を走馬灯のように駆け抜けながら、シャルシュは宝物庫の方へと戻っていく。
行って何をするというわけでもない。
何が出来るというわけでもない。
彼らは森林警備隊のメンバーと一緒にいたわけで、その前に出て行くようなことはきっとシャルシュには出来ない。
「行ってどうするって言うんだ?」
自分でもよく分からない衝動に突き動かされて、シャルシュは足を進める。少し進んでは止まり、引き返すべきか悩み。
けれどもそれらのことは結局は無駄に終わり、また足を動かす。
そうして、結局やってきてしまった。
先ほどエリアネル・テルミチェットと分かれた場所――宝物庫。
こそこそと、茂み伝いに近くまで行き、様子を窺う。
彼らはなにやら話し込んでいるらしかった。
二人いる人間の片方、少女が顔を真っ赤にして声を荒げる。シャルシュの位置からでは何を話しているのかは良く聞こえない。
一体何を話しているのだろうか。
その一言一句が気になって、もう少し近くへと歩み寄る。
不意に、少女が手に持つ紙が光った。
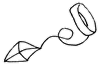
警告を示す真っ赤な光。
自分たちの間近に警戒に値する魔力反応があるというメッセージ。
眩しさを感じたのは一瞬、地図に目を落とすと現在地のすぐ近くにこちらへ向かってくる真っ黒な点が映っていた。
その数、二つ。
「兄様!」
「おう、分かってる」
かけ声一つ、ジグは露台に腰掛けた姿勢から一転飛び降りると、張り詰めた表情で辺りを見回す。
この切り替えの速さを見ると、ジグが騎士をやっているのも決して伊達や酔狂でないことが思い知らされる。
全くもって、スイッチのオンとオフの切り替えがうまい。
「数はいくつだ?」
「二です。こちらへ向かってきてます」
必要且つ十分な情報を並べながら、アリアもまたナントスエルタを取り出し、周囲を油断無く見回す。
「おい、なんだって言うんだよ?」
事態を理解できていないシラムの声。いらだちと困惑の入り交じったそれに、簡潔で明瞭な答えを告げる。
「《あちら側》のモノが二体、《こちら》へ近づいてきています。私たちが迎撃しますから、お二人は下がっていてください」
それはつまり、自分たちでさっさと片付けてしまうから足手まといのエルフは下がっていろと、そう言う意味に他ならなかった。
曲解にも思えるかも知れない。だが、彼女の口から直接聞いた者なら誰でも分かる。
その小馬鹿にするような口調。
その不適に微笑む表情。
その見下すような視線。
それらの全てが語っていた。シラムたちは足手まといだと。だから自分たちに任せておくべきだと。
「へ、冗談だろ」
アリアの言葉に、シラムは笑みを浮かべて首を振った。
シラムたちに下がっていろだと。一体何様のつもりだ。確かに彼ら魔導騎士の強さは認める。しかし自分たちだって《あちら側》の存在を相手に戦うことに関しては並ならぬ経験を積んだプロフェッショナルだ。
先ほどは慣れない戦い方にうまく手玉に取られたが、今度はそうはならない。
その自信を持って叫ぶ。
「二つ来るって言うんなら、僕とオーウェルさんで一体、お前らで一体だ」
「おい、シラム、」
突然名前を出されたオーウェルの驚きの声も、しかしシラムとアリアの二人は完全に黙殺した。
目の前の、先ほど自分にいとも簡単にあしらわれた森林警備隊員の実力を改めて量るかのようにアリアはじっとシラムの瞳を覗き込む。
その奥の、純白の輝きを。
「……いいんですか?」
それは任せても良いか、と言う問いではなく、弱者が意地を張ると後悔することになるが良いか、と言う問いに他ならない。
どこまでも自分たちのことをバカにしているようなアリアの問いに脳漿が沸騰し掛かるのをすんでのところで抑えて、譲れない理由を口にする。
「当たり前だ。そうそうお前らばかりに任せてられるか。何せここは僕たちの守る村なんだからな」
「そうですか。なら、見せていただきましょうか。ええ、言葉は不要です。どうぞ行動で示してください。あなたたちの持つ意地というものを」
シラムの表情、強い意志を秘めたその瞳をじっと見つめて、アリアは小さく頷いた。
地面に二カ所、地図を見ながら×印をつける。もう時間はほとんど無いだろう。光点が激しく点滅するのを見やりながら、アリアは手早くその作業を済ませた。
互いに十メートルほど離れた二つの×印。その一方の近くにアリアとジグが、もう一方にはシラムとオーウェルが立つ。
手慣れた様子でそれらのことを終えてふうと一息ついたアリアを、シラムが胡乱げに見つめていた。
「なあ、《あっち》の存在が近づいてきてるんじゃなかったのか?」
「近づいてきています。それも、今回のは結構分かり易く出てくるみたいですからこうして印をつけたんですけど?」
「はあ?」
アリアの言っている意味が分からないと言わんばかりに思いきり顔をしかめるシラム。
自分は何か変なことでも言っただろうかと考え、ふとそこへと思い至る。
自分たちにとっては常識であることが、エルフにとってもそうとは限らないというごく当たり前の真理。
しかし、常識というのは口にするまでもない当たり前のことだから常識なのである。
配慮が足りなかったと言えばそれまでだが、人間とエルフの文化の違い、そしてそこから来る知識レベルの違いに、改めて溜息が出る。
「わざわざ説明……、する必要はないみたいですね」
肩をすくめてシラムの方へと向き直ったところでそれが目に入った。
×印を書いたところ、そのどんぴしゃり真上。まるで空中に見えないレンズが出現したかのように景色が歪んでいる。
オーウェルは気付いたようで表情を硬くしている。何が起きようとしているのか察したのか、或いはそこまでは行かなくても長年積み重ねた経験が警告を発しているのだろう。
しかし、シラムは気付かない。こちらを不満げに睨み付けて口先を尖らせているだけで、自分のすぐ隣で起きつつある異変に目も向けない。
「必要ないとか言わずに説明しろ! 僕たちには何が何だかさっぱり分からない。《あっち》のものが近づいて来てるって言うなら、さっさと探しに行かなきゃ駄目だろ。万に一つ村の方へと迷い込んだら」
「迷い込むことはないですよ。あなたたちがここできちんと仕留められるなら」
そう言いながら、自分たちの近くにつけた×印の方へも視線をやる。向こうは空中なのに対し、こちらは地面が少しずつ脈打つように歪んできている。
もう少しだけなら話をしている時間はありそうだ。そう判断して、アリアはシラムの言葉に付き合う。
「あのな、こっちに近づいてきてるって言っても、ここへ来るまでに村の方へ行っちまう可能性は高いだろ。ここは村の近くなんだし」
「それはないですよ。彼らは必ずここへ来ます。はい、もう数える間もないほどの時間の内に」
「ああそうかい。じゃあ、確信があるって言うならそれでいいよ。分かったよ。それで、奴らはどの方向から来るって言うんだ? それくらい、もう分かってるんだろ?」
疑うような口調でじろりとこちらを睨み付けてくるシラム。その隣でますます大きさを増している大気の歪み。
丁度良い頃合いだ。恐らく、タイミングとしては台本があったと言われても不思議でないくらいのピタリのタイミング。
できすぎたシナリオに乗っかっていると考えるとあまり気持ちよくはないが、しかしシラムに泡をふかせるのはやっておきたいところだ。
オーウェルの緊張した視線の先。今まさに生まれ出でようとしている、二つの世界を繋ぐ道。そこを指さして口にする。
「《あちら》から」
シラムがその指先を追って振り向くのと、
アリアが瞬時にその場から飛び退くのと、
オーウェルが驚愕に表情をゆがめるのと、
ジグが腰に佩いていた剣を振り抜くのと、
空中の――地面の、歪みが弾けてそれらが飛びだしてくるのとは、
同時だった。
飛び退きながら、アリアはその敵の姿を視認する。
地に空いた穴から現れたそれは、出現とほぼ同時にジグが振り抜いた剣に肩口をばっさりと抉られる。地面の上をのたうちながら這うその姿は強いて言うのならモグラに似ていた。ただし、大きさだけなら人間の大人を軽く凌ぐ大きさである。
空の穴からは鳥によく似た形の、しかし鳥とは決定的に何かが違う軟体生物のようなものが舞い出てきて、宙を駆けるようにしてシラムたちの方へと迫る。
両者に共通するものは一つ。
てらてらと嫌らしく光る漆黒の肌は《あちら側》から現れてきた彼らに特徴的な、死体を思わせる淀んだ空気を纏っていた。
魔獣。そう呼ばれる彼らに極めて典型的な外見である。
彼らは《ここ》とは異なるもう一つの世界、俗に《あちら側》と呼ばれる世界から、何かの拍子に《こちら側》へと迷い込んできたものたちである。
二つの世界が相容れることは無い。そう言われる根拠をそのまま示すように、彼ら魔獣は《こちら側》へとやってくると殺戮と破壊の限りを尽くす。まるでどこか狂ってしまったかのように。
「なんだ、こいつ、今どこから現れやがった!?」
驚きの表情で飛び退くシラム。その慌てぶりをちらりと流し見ながら、アリアは自らのそばへと現れたモグラもどきへと油断無く視線をやる。
「《あちら側》から直接現れただけです。そこまで驚くほどのことでもありませんよ。ただ、そうですね。この程度でそんなに慌ててしまうようではこれから先は全く使い物にならないんですけれど」
「これから先だ? 一体何の話を……、と」
「シラム、よそ見をしている余裕は無さそうだぞ」
そんなオーウェルの声とともに、剣が空を切る音がする。一瞬だけ、背後を振り返り、とりあえずは任せておいても大丈夫だと判断して、アリアは自分たちの敵の方へと向き直った。
モグラもどきはジグが剣でうまくあしらっている。
今やるべきことは一つ。兄に加勢し、さっさと片付けてしまうこと。
「オーウェルさんの言う通りです。とりあえずは目の前に集中してください」
「言われなくても、やってやるよ!」
背後から掛かるシラムの声に小さく微笑んで、アリアはナントスエルタを構えた。
その漆黒の体が、剣撃とともに地面に倒れる。やや細長い筒のような体型の、その上部と下部にオマケみたいな手足がちょんちょんとついている。その手足が、倒れ伏すと同時に猛烈な勢いで動き出す。肩口の傷はすぐにヘドロのような黒い何かに覆われると、何事もなかったかのように消え去ってしまっていた。
「兄様!?」
まるで川面を往く舟のように地面の上を常識外れのスピードで這い動くそのモグラもどきを、剣であしらう。太く重い両手剣を器用にあやつり、モグラもどきが地面に張り付いたまま何も出来ないようにうまく動きを操っている。
「援護、頼むぞ」
じわじわと後ろに下がりながら、しつこく飛びかかってくるモグラもどきの攻撃を全てはたき落とす。
魔獣の攻撃は確かに高い威力を持っているし、その速さも、ともすれば視認できるレベルを軽く超えてくる。しかし、奴らの攻撃は極めて単調なのだ。動物であってももう少し考えて行動する、と言いたくなるほどに単調で、直線的。或る程度慣れてしまえば、これほどいなしやすい攻撃もない。
兄が確実にモグラもどきの攻撃を躱し、あしらい、その注意を自分一人に引きつけているのを見ながら、アリアはナントスエルタをゆっくりと振れさせていた。
彼女の右手からすっと下に伸びた糸と、その先に吊られる八面体の宝石。それらが夕日のオレンジ色の中で淡い黄緑色の燐光を纏う。
「標的、捕捉。距離、増加中……、予想捕縛位置、決定」
ジグが徐々に下がっていくその経路は紛れもない直線を描いている。数瞬の後の彼らの位置を正確に脳裏に描き出し、そこで決着をつけるべく脳裏にシナリオと魔術式を思い描く。
自らの体内を流れる魔力を御し、指先から目標地点へと放出する経路を仮想し、実行する。
「
呟くように紡ぎ出された呪文は、自己と、そしてこの世界に対するささやかな宣戦布告だ。これから世の理を無視した現象を引き起こす、という断り。この世界に生きるモノとして、この世の理に従うモノとして、ひと言だけ謝罪と宣言を高らかに歌い上げ、何の悪びれもなくそれを起こす。
それが、彼女たち魔術師という
緻密で正確な魔術式によって御されたアリアの魔力が一本の矢となってそこへと至る。ジグへと跳びかかっていたモグラもどきが丁度着地したタイミングで、その背から腹を地面に縫い止めるように貫く。
或いは、並の生き物であるならこれで意識を奪い活動を止めることも出来るほどの衝撃とともに、放たれたアリアの魔力は魔術式とともにあたりに飛び散る。
魔力の流れを観ることの出来る者ならば、着矢点を中心に花火のように薄桃色の魔力が広がっていくのが見えただろう。
薄桃色の魔力と魔術式、それらが渾然となることで発生する魔力フィールドが、周囲に元から存在していた自然の魔力を染め上げ、一個の巨大な魔法儀式を完成させる。
それらはわずかに瞬きをする最中にも満たない一瞬の出来事。
衝撃。破砕音。そして土煙。
その後には、地面から頑強そうな光の鎖が生え、モグラもどきの体は土の上にくくりつけられていた。
手応えと予定通りの眼前の光景に、小さく拳を握りしめるアリア。
「とどめをお願いします、兄様!」
「任せとけ!」
そう勢い込んで気合い一閃。ジグが大剣を振り上げ、身動きのとれないモグラもどきの真上から、風を切り裂く勢いで振り下ろされる。
あっけなく終焉。そう、思われた。
が、剣を振り下ろしたジグの手元に返ってきたのは会心の手応えではなく、鈍く地面を穿った時のそれであった。
土気色をした地面とその上に幾重にも重なる光の鎖、それらを真っ二つにするかのように振り下ろされた大剣は、地面に細長く掘られた溝の
きちんと目では捉えていた。しかし、手の動きはそれを追いかけることは出来なかった。
剣を振り下ろした瞬間、あろう事かモグラもどきは信じられない勢いで地面を掘り、そのまま地中へと離脱していたのだ。あとほんの一瞬早く刃を下ろせていたならこうはならなかったものを。悔しさに思わず舌打ちし、アリアの方へ視線をやる。
アリアは悔しげな兄の表情を見ると小さく肩をすくめる。その表情には落胆などの負の感情は見受けられない。
まるでこうなることを予想していたような、そんな自信に満ちた笑みを浮かべている。
「……はあ……、なんかそこで笑顔になられるのは腹立つな」
「なら今度は一撃で決めてしまって下さいな、兄様」
クスリと、どう見てもわざとジグに見せるように笑いを漏らし、アリアが指をパチンと鳴らす。
同時に重力のくびきに逆らうように、ナントスエルタがアリアの掌を越えて宙へと浮かび上がる。
燐光がその輝きを強くし、薄桃色の魔導士の掌の上で小さな太陽のような輝きがその威を放つ。
そして、それとともにジグの足下から何か鈍い音と振動が伝わってきた。
足下の地面を突き崩そうと言わんばかりの振動。
鼻で息を吐き、ジグがその場から飛び退く。
「今度こそ、外さないで下さいね!」
そう叫び、アリアが腕を振り上げる。それと同時に、地中から潜っていたはずのモグラもどきが勢いよく姿を現した。
いや、それは姿を現したと言うよりは、むしろ引きずり出されたと言った方が正確だろう。
見えない釣り糸に絡め取られているかのように宙へと引っ張り出されたモグラもどきは、四肢を乱暴に振り回して束縛を解こうとしているようだが全く意味を成していない。じたばたと空中に磔にされた漆黒の影は夕日の中に今まさに燃え尽きようとしているかのように見えた。
その姿をにらみ据えるジグ。
手にした剣を改めて上段に構える。
「《あちら》の者は、《あちら》へ還れ」
一瞬、その剣が白銀の輝きを帯びたかに見えたのは幻か。
次の瞬間、烈風のごとく振り下ろされたジグの剣は、見えない呪縛とともにモグラもどきを真っ二つに切り分けていた。
じたばたともがいていた四肢が痙攣したかと思うと、程なくその動きを力なく止める。漆黒の、この世界にあらざる存在の肉体が塵へと還ってしまうのに、時間は掛からなかった。
あとに残ったのは、モグラもどきを地中から引きずり出した名残である大穴だけ。めくれた地面を一瞥し、アリアは兄に冷たい視線を投げかけた。
「兄様、腕が鈍りましたか?」
「そんなわけあるか。お前の見せ場を取っておいてやっただけだよ」
「そんなもの不要でしたのに。余計な気を回す暇があったら一撃で決めてくれる方が余程私のためになりますよ」
「分かった分かった。次から気をつけるから」
そう言って肩をすくめるジグ。彼を見つめるアリアの視線は相変わらず冷たいままで、まるで彼の言葉が言い訳であると言いたげであった。
その実、そうに違いないのだが。
「ところで、アイツらは?」
「さあ、森林警備隊というくらいですし、あの程度の小物に手間取るとも思えませんが」
そう言ってアリアが振り返ろうとした時。
ヒュンと風を切る音。それに気付くのがもう少し遅れていたら、耳たぶぐらいは持って行かれていたかも知れない。
慌ててしゃがみ込んだ彼女の上を、漆黒の影が飛んでいく。
確認するまでもない。それは先ほどシラムたちが相手にしていた敵だった。
「全く、あの人たちは一体何を!?」
振り返るアリアの視界の隅に、慌てた様子でこちらに駆けてくるシラムとオーウェルの姿が映る。
大方、あの鳥の魔獣に何発か攻撃を喰らわせて追い詰めたところで油断して、逃げられてしまったのだろう。魔獣にだって生存本能はある。勝てない状況と分かれば逃げ出すのも当然といえば当然のことだ。
「エルフはそんなことも分かってないって言うんですか?」
いらだちに、思わず棘のある言葉が出てくる。彼らエルフと自分たち人間の考え方の違いは分かっているつもりだったが、その認識もどうやらまだまだ甘かったようだ。
「そんなことよりも、アリア、俺たちが行った方が早い。行くぞ」
若干焦りを含んだジグの言葉に頷いて、アリアも反転すると駆け出す。このままの方向へ進めば村の中に入ってしまう。そうなるとどんな惨事が起きるか、考えたくもない。
彼らの追う先で鳥の魔獣は、しかし森の中へと進路を変えた。
理由は分からない。しかし、村へと向かわないらしいということでアリアたち四人が揃って胸をなで下ろしたその時。
「う、うわああああ!?」
魔獣が飛び込んだまさにその先の茂み、夕闇に沈みつつある暗い木立の中から、その悲鳴は聞こえた。
一同、驚きに目を見開く。
「なんだって、こんな所に人がいるんだ!?」
ジグの叫びが四人の気持ちを揃って代弁した。

一体何が起こっているというのか。
目の前で起きている出来事に、シャルシュの理解は全くと言っていいほど追いついていなかった。
空中から突如現れた魔獣。何の前触れも無く、何の依代も無く。そんな現象はエルフの常識にはない。
魔獣というのは《あちら側》の世界から漏れ出してきた異質な魔力に動物たちが犯されて変貌してしまったなれの果てであるはずだ。
故に魔獣たちは《こちら側》の世界の動物に似た姿を持っている場合が多い。
では、あの魔獣たちは一体何だというのか。
シャルシュは茂みの向こう側で繰り広げられている戦いを凝視する。
二人の人間が相手をしているモグラに似た魔獣は、その姿からは想像も付かないような機敏な動きで地を這いずり回って人間の男へと襲いかかっている。
見覚えのある森林警備隊員たちが相手をしている方は猛禽類のような外見で、凡そ普通の鳥には不可能な軌道で空中を飛び回り二人のエルフを苦戦させているようだった。
二体の魔獣の動きは、彼らの知るモノたちの平均的なそれよりも幾分か鋭く見える。人間の二人にとっては恐らくこれが普通なのだろう。彼らは顔色一つ変えずに余裕たっぷりの様子でモグラに似た魔獣をあしらっている。が、エルフの二人はそうもいかないのだろう。彼らの予想を少しだけ上回る動きで攻撃を躱され、逆に反撃が少しずつ蓄積していく。その様子に徐々に、だが確実に焦りが募っていく様子がありありと見て取れた。
「この分だと、人間の人たちの方が早く決着がつきそうだな……。けど、あの二人も負けるって言うことはないだろうし」
そんな分析を冷静に口にする。
そして、思う。
「……? 僕は一体何がしたいんだ?」
わざわざこんな村はずれまで来て、影からこっそりと様子をのぞき見るだけ。
人間が村にいるということが珍しくてつい後をつけてしまった。しかしそこから何かを出来たわけではない。こうして影から彼らの様子を盗み見ているだけで、全くの第三者で終わってしまう。
絶対的な無関係。
ここは蚊帳の外でしかない。
恐らくこのまま彼らは問題なく魔獣二体を倒し、村へと戻るのだろう。そして、二人の人間はシャルシュとの接点がないまま村を出て行くだろう。それが当然あるべき運命であり、確定された未来。
結局いつまで経ってもシャルシュは駕籠の中の鳥で、憧れる世界への扉はいつまで経っても固く閉ざされたままなのだ。
「しかた……ないか……」
呟きは悔しさから。どうしようもないこの身を呪うことは既に幾度となく繰り返した。自嘲の念にさらされ続けた心はすり減り、摩耗し、この身の境遇はとっくの昔に諦めきった筈だった。
自分はこの村の中で異端として過ごすしかない。
自分は出来損ないエルフとして死んでいくしかない。
自分は、このまま無意味で無価値に何も出来ず終わることしか出来ない。
だというのに。
諦めたはずの世界がすぐ目の前に広がっている。
決して叶わなかったはずの人間との邂逅、それがすぐ目と鼻の先に待っている。
このままここで傍観者に終わって良いのか。
それは問いと言うよりは確認。
終われない、という自分の意志を確かなものにする為に確認したに過ぎない。
「じゃあ、この戦いが終わったら、」
思い切って彼らに声をかけよう。
そう、呟いて自分に言い聞かせようとしたその時だった。
ガサリ、という植物が揺らされる音、それとともに目の前の茂みが唐突に割れていた。
視界に割って入ってくる漆黒の影。それは、先ほどまでエルフと死闘を繰り広げていたはずの猛禽類に似た魔獣だった。
意識が硬直したのは一瞬の出来事。
シャルシュは半ば本能に従うように悲鳴を上げていた。
「う、うわああああ!?」
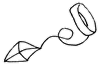
「大丈夫ですか!?」
茂みを飛び越えるのと同時に、魔力の糸を編んで最低限の守りを展開する。自分の周りに不可視の網が広がるのを感じながら宙を駆けたアリアは、開けた視界の中で起きている出来事を目にして言葉を失った。
茂みの向こうは、人が四人ほど立つことの出来る程度の場所が広がっていた。そこに、自分たちが追ってきた黒い鳥の魔獣が空中で制止している。その目が向けられた先にはエルフの少年がへたり込んでいた。
白い髪が肩まで伸びている。全体的にやせ形、筋肉というものが付いているように見えない細い体は、今は恐怖にがたがたと震えており、いつ折れてしまうのか不安に思えるほどだ。
腰を抜かしてしまったのか、地面にぺたりとお尻を付いた形で座り込んで、じっと目の前の魔獣のことを見つめている。
「……こ、こいつを……」
恐怖で歯の根が逢わないのか、震えるような声でそれだけをどうにか絞り出す。
その少年と、にらみ合う鳥の魔獣を交互に見やる。
鳥の魔獣は不可解なことに羽ばたきもせず、むしろ身じろぎ一つさせずに空中に完璧なまでに制止していた。まるで時間そのものが止まってしまったかのように動きというものが無い。
ガサリと背後の茂みが揺れて、ジグが追いついてきた。
「何だ? どういう状況だ?」
「……いえ、何でもありません。とどめは私がさします」
不思議そうな兄の問いかけを受け流し、アリアはナントスエルタに魔力を走らせる。
編み上げる魔術は限りなく細い糸を紡ぐ。限りなく細く、限りなく強い、それは一本の剣のように鋭くとぎすまされ、音もなく黒い鳥の魔獣に絡みつく。
翼の付け根と首の付け根、両足の付け根から全身の主要な関節に至るまで巻き付いた箇所は凡そ三十。その魔力の糸を吐息とともに思い切り締め上げた。
ぷちり、と何かを切り裂く手応えがある。その一瞬の後、魔獣だったものの体は三十を超える肉塊へと解体され、地面へと落ちることすら許されずに風に溶けて消えた。
「終わったのか……?」
いつの間にか背後に現れていたシラムが、宙に舞う魔獣の残骸を見て放心したように呟く。
「ええ、あなたたちが間抜けにも仕留め損ねた魔獣の始末をつけさせていただきました」
アリアが背後に視線もくれずに言う。彼女はじっと魔獣がいた場所と、そして呆然としたまま座り込んでいるエルフの少年を見つめている。
まるで何か奇妙なものでも見ているかのような視線。
その視線に気付いたのか、少年がこちらを不思議そうな目で見つめ返す。
「……えっと……怪我とかは、ありません、ようですか?」
どこかおかしな問いかけを口にしてしまい、自分が赤面してしまうのを感じた。
だが、それでも訊ねたいことは通じたのか、少年は苦笑を浮かべて答えた。
「助けていただいたお陰でどうにか無事のようです。……その、まだ腰が抜けちゃってるんですけど」
「そうですか。なら、良かったです」
それだけ口にして、背後を振り返る。
「さて……、とりあえず一段落って所だな」
ジグがからりとした笑みを浮かべて肩をすくめた。
それに小さく溜息をついて答える。
「そうですね。一番最初に感知した《あちら側》の魔力の正体は結局分からずじまいですけれども、今焦って出来ることは殆どありませんし」
「で、これからどうするよ?」
「どうって……、本来の目的に戻るだけじゃないんですか?」
兄の質問の意図が理解できなくて、思わず訊ね返す。
真面目そのものと言った表情でそう言い放つアリアに、ジグは思わず大きな溜息をついて肩を落とした。
「あのな、お前このまま日が暮れた森に入っていくって言うのか? このあたりに地理にだって全然明るくないのに」
「あ、えっと、それは……」
そんなことには全く考えが及んでおらず、アリアは思わず口ごもる。
妹が失敗を恥じる、というあまり見ることのない場面を図らずも演出したことからか、ジグは磊落に笑いをあげた。
「まあ、お前でもそう言うミスはあるわな。ていうかいつも真面目すぎるくらいだから丁度良いって。
それよりも……、オーウェルさん、この村って宿みたいなものはあるのかい?」
エルフの少年を助け起こしているシラムの方をやるかたなく眺めていたオーウェルは、突然自分の名前が呼ばれたことに驚きの表情を見せて、すぐにそれをあきれ顔に改める。
「わざわざ訊いてくる、と言うくらいならエルフの村の閉鎖性は知っているんだろう? 是非もない話だ。宿屋なんてあるはず無いだろう」
「やっぱりそうか。まったく、今のご時世呆れた種族だな」
「放っておいて貰おうか」
「で、どこか余所者の人間を泊めて貰えそうなところって無いのかい?」
「……そうだな、長老の屋敷ならば、或いは頼み込んでみる価値はあるかも知れないが……」
ほかにはどうだろうか、と考えを巡らすオーウェル。
そんな彼の言葉を遮るように、細く囁くような声がした。
「あの……それなら僕の家に泊まりませんか?」
弱々しい声は空耳かと思ってしまうほどかすかなもので、今にも木々の囁きに埋もれてしまいそうだった。
「ん……?」
不思議そうにオーウェルが首を巡らす。
声が聞こえてきたその方向。あきれ顔のシラムに肩を借りて立ち上がった少年は、皆の視線が自分の方へと向いているのを見て取るともう一度、今度はよりはっきりとした声で言った。
「人間のお二人、泊まるところがないなら僕の家に泊まりませんか?」

「突然のことなのに、悪かったな。宿に晩ご飯までごちそうになって……、えっと、シャルシュ君」
ジグがお茶に口をつけながら、彼には珍しく真摯な口調で言った。
「シャルで良いですよ」
シャルシュはテーブルの上を片付けながらそれに軽く応える。
卓上には三人分の晩ご飯が盛られていた皿が並んでおり、それを適当に積み重ねて流しへと持っていく。
シャルシュの家の居間には、現在シャルシュとジグがいた。
「野宿の覚悟はしていたからな。まさか温かい寝床とできたてのご飯、それにお風呂まで使わせて貰えるとは思ってもみなかった。上がってきたらアリアからも良く礼を言わせるよ」
「良いですって、別に。お客さんからお風呂を使って貰うのは、当然と言えば当然のもてなしなんですから」
洗い物をするべく流しに水を溜めながら、シャルシュは応える。
手慣れた仕草でエプロンを身につけると、水に浸かった食器を丁寧に洗っていく。
そんなシャルシュの後ろ姿を見ながら、ジグは感心したように溜息をついた。
「それにしても、詳しいね。それ、当然って言っても、それは人間の文化での当然だし、君たちエルフには無いだろう? そもそもエルフの村ではこうして客人を泊めることさえ少ないはずじゃないか」
「そうなんですけどね。まあ僕はちょっと特殊なエルフですから」
数枚の皿をさっさと洗ってしまって、食器カゴに並べる。手から滴る滴を簡単に切って、エプロンで手を拭った。
特殊なエルフであるということ。それが具体的にどのようなことを指すのかはジグには分からなかったが、口ぶりからして軽口の冗談とも思えない。本当に、何か彼を囲む境遇なり何なりが特殊なのだろうと推察される。そんな自分自身のアイデンティティに関わることを喋る間にも、一切淀みなく家事をし続けていたシャルシュ。それはもう自分の境遇について諦めきっているということの何よりの証であった。
すなわち、彼にとっては異常こそが日常。
自分が他者と違う異端の存在であることなど認めるまでもない当たり前のことに過ぎない。
それはとても悲しい認識である。
目の前の少年がそんな悲痛な現実を無抵抗に受け容れてしまっていることが感じられ、ジグは胸が抉られるような感じがした。
「その……、差し障りがないならさっきから言ってる特殊っていうのの意味を教えてくれないか?」
聞いてどうなるのか。
そんなことを自問しながらも、その問いはジグの口から自然に滑り出ていた。
目の前のエルフの少年の秘密を知ったところで、自分に出来ることなど何もない。
それは分かりきっていたことだが、しかし聞かずにはいられなかったのだ。
「えっと……、その、出来れば話さないで行く方針……じゃ駄目ですか? 同情されるのとか苦手なんで」
「そうか。それなら全然構わない。いや、むしろこっちこそぶしつけな質問をして悪かったな。忘れてくれ」
「はい。そうします」
そう言って、シャルシュはいつの間にか淹れていたお茶をずずっと啜る。
はあ、と息を吐くその様子は身近な幸せを噛みしめているかのように見えて、とても先ほど語ったような悲痛な認識を持っているようには見えない。
だからこそ、余計にシャルシュの仕草がジグには悲しく映るのだった。
無理をして生きていると言う、そのことが丸わかりの姿勢。やせ我慢以外の何者でもない気をつけは、それを見る第三者の目には痛々しく映って仕方がない。
彼の周りにはそれを止める大人はいなかったのか、と……言うところへ考えが言ったところで、ふと今更ながらにそのことが気になった。
「なあ、シャル、お前……親御さんはどこにいるんだ?」
エルフは人間で言うところの十八歳程度、すなわち人の五倍の長さの年月を生きる彼らにしたら九十歳程度の年で自立し、自らの家庭を持って暮らし始めると聞く。だが、目の前のエルフの少年の見た目はそれよりもまだ随分と幼いように見えた。そう、人間で言うところの十五歳程度だろうか。この程度の年ならば、まだ親元を離れずに暮らしているのが普通の筈である。だと言うのにこの家には自分たち以外の気配がない。
何らかの理由で既に一人暮らしを始めているのかも知れない。或いは暫く間家を空ける用事でもあるのか。そう思っていたのだが。
「ああ、言うのを忘れてましたね。僕の両親は十年前に亡くなってます」
「なっ!?」
思いもかけない答えに一瞬息を呑む。
何気ない問いかけだったのに、意図せずにその問いはシャルシュのプライベートにずかずかと土足で踏み込んでしまい、申し訳なさに目を伏せる。
「あ、やめてくださいって。もう、随分経つことですし、今更そんな風な態度をされてもどう反応して良いのか分からないんですよ」
「いや……でも、俺が無神経だった。すまない」
「良いんですって。どうせ、僕その頃小さかったからあんまり覚えてないんです。だから、気にしないで下さい」
「そうか……」
小さく呟いて、ジグは首を振った。
疲れているのか、今ひとつうまく会話が出来ない。こういう日はさっさと体を休めてしまうのに限る。
妹が風呂から出てきたら自分もさっさとお風呂に入らせて貰って、寝よう。
そんなことを考えつつ居間の出入り口の方へと視線をやると、いつの間にかそこには彼の妹であるアリアがいた。
シャルシュがどこからか出してきたうす桃色の寝間着を羽織って、髪の毛を丁寧にタオルで拭きながら、厳しい視線をシャルシュに向けて注いでいる。
そう言えば、先ほどの食事中にも、その前にこの家に向かって移動してくる時にも、彼女はどこか険しい表情でずっとシャルシュのことを見つめていたような気がする。
何かあったのかと、そう問いただそうとジグが口を開こうとするその一瞬前。
「シャルシュさん、訊ねたいことがあるんですけれど、いいでしょうか?」
「……どうぞ」
どことなくアリアの威勢に気圧されたようになりながらも、不思議そうな表情を浮かべてシャルシュがそう返した。
硬い表情を浮かべて、睨むと言っても良いくらいの視線でシャルシュのことを見つめるアリアの様子に、ジグは呆気にとられる。そんな様子の妹を見たのは久方ぶりだった。
「では、単刀直入におたずねします。シャルシュさん、貴方何者ですか?」
「何者、というのは?」
小さく首を傾げるシャルシュ。
唐突に前後の文脈もなく、貴方は何者ですかと訊ねられた場合、果たしてなんと答えるのが最も適当なのか。
見当もつかなかったシャルシュは仕方なく立ったままのアリアに椅子をすすめると、問い返した。
「そのままの意味、のつもりです。貴方は本当にエルフなんですか? 森で私たちが駆けつけた時、貴方が使っていたのはエルフの魔法というよりは私たち人間の使う魔術に近いものでした。計算された術式、丁寧に張り巡らされた魔力の地図、人間が扱う魔術としても平均以上の練度と言って良いでしょう。そんな風に私たちの魔術を使いこなせるエルフなんて、聞いたことがない。貴方は一体何者ですか?」
何かにせっつかれるかのような勢いでまくし立てられるアリアの言葉を聞いて、シャルシュは小さく頷くと一旦椅子から立った。
お茶をもう一杯淹れ、アリアの元へと出す。
自分の問いに対して答えが返されないことにいらだちの表情を見せるアリアの視線をやんわりと受け止めて微笑むと、小さく首を傾けた。
まるで老人が世間話をするかのようなのんきな口調で言う。
「そう言われても、僕がエルフって言うのは間違いのないことですよ」
それは覆しようのない事実で、むしろシャルシュ自身が何度否定したいと思ったことか、既に数えるのもバカらしく思えるほどである。
そんな、と納得のいかない声を上げようとするアリアを手で押し止め、更にシャルシュは続ける。
「さっきジグさんには少しだけお話ししたんですけど、僕が普通のエルフじゃない、それもまた確かなことです。けれども僕はエルフなんですよ、見ての通り、ね」
そう言いながらさっと髪を払う。さらさらの純白の髪と、その下から現れる細長く伸びた耳。白い髪の毛は魔力に祝福された民と呼ばれるエルフの、その中でも更に能力の高い者のみが持つと言われている、
「ただ、ある事情で人間の魔術を習って、そっちの方が合っていたから今では人間流の魔術しか使わなくなってる。ただそれだけの話なんですよ」
「でも、そんなの聞いたことがありません。エルフと人間の技術交換はこれまでも何度か魔術協会主体で試みられてきたのに、それは一度たりとも成功しなかったはずです。エルフには人間の、人間にはエルフの技術を扱う適性が無いから、と言うことじゃなかったんですか?」
狼狽したような声でまくし立てられるアリアの言葉は、半分真実で半分嘘が混じっていた。だが、閉鎖的なエルフの村で育ったシャルシュはもとより、協会の一構成員に過ぎないアリアやジグはその真相など知るはずもない。
彼らにとってはこれが真実であり、それ故に人間の魔術を使えるエルフなどいない。そうでなければおかしいのだった。
「僕だって詳しいことを知っているわけじゃないんですけど、でも現に使えるんだから仕方ないじゃないですか。僕に魔術を教えてくれた先生も別にそんなこと言ってませんでしたし」
「どう……なんでしょうか、兄様?」
目の前で起きたことこそが真実であり、シャルシュ・ワイゼンというエルフが人間流の魔術を使えるのは紛れもない事実である。
その疑いようのない物証を突きつけられ、アリアは困惑したような表情で兄に目を向ける。
「俺に聞くなよ」
そもそもジグにすれば、森での一件でシャルシュが魔術を行使していたことすら初耳である。あの時彼はアリアに遅れること数秒で現場に到着したが、その時間は彼の優秀な妹であるなら魔術を張り巡らせるのには十分すぎる時間である。故に空中に鳥の魔獣が磔にされていたのもてっきり彼女がやったことと思っていたのだが。
言われてみれば、悲鳴が上がってから彼らが駆けつけるまで、若干のタイムラグがあった。その時間何もなかったというのは考えがたい。となれば、シャルシュが魔術を行使して自衛したというのが自然な推測ではあった。
そんなこと、言われなければ気づけるはずもない。なんせ万事無事だったのだ。いちいち済んだことについてごちゃごちゃと考えるような几帳面な精神構造は、ジグは持ち合わせてはいない。
考えることを放棄したように天井を見上げるジグと、彼の方へ縋るような視線を向けるアリア。
二人の様子を眺めていたシャルシュは、不意に手をポンと叩くと、こんなことを言った。
「それにしても、凄いですね。人間ってみんなそうなんですか?」
「……そう、ってどういう意味だ?」
笑顔のシャルシュを見て不審そうに顔をしかめたジグが訊ね返す。
「あ、だから、現象を見ただけで人間の魔術かエルフの魔法かを判別できるっていうことです。エルフにはそんなこと出来る人いないから、さっきアリアさんに言われた時には本当にびっくりしたんですよ」
「ん、ああ、そう言うことか」
ジグは納得したという表情で肩をすくめた。
小さく鼻息を吐くと、簡単なことだ、と前置きをして説明する。
「俺たち人間の魔術ってのはちょっとでも間違えたら恐ろしい暴発をしかねない絶妙なバランスの上に成り立っているものだ。それ故に、術者は魔術の式には人一倍敏感である必要がある。そうでなきゃ、いつ死ぬとも分からないからな。だから、その程度のことは魔術師としてやっていく為には最低限必要なこと、……なんだけど」
淀みなく得意げに説明していた言葉が次第に失速し、シャルシュを見つめるジグの視線が奇異なものでも見るようなそれに変わっていく。
自分で喋っている途中に言っていることのおかしさに気付いたのだろう。
シャルシュは人間の魔術を行使する。つまり言わば魔術師である。
であるにもかかわらず魔術師として最低限必要なスキルのことを知らない。
「それって……、」
疑問をジグが口にしようとした瞬間、がちゃんと大きな音をたててアリアは机を思い切り叩いていた。
「ちょっと待ってください! 貴方、今までそんなので魔術を行使してきたんですか!?」
コップの中身がちゃぷちゃぷと揺れて、お茶の滴が数滴飛び散る。
今度こそ、アリアは間違いなくシャルシュのことを睨み付けていた。怒りの為か頬が紅潮している。
「えっと……まあ、はい」
何か気分を害するようなことを言ったのだろうか。アリアが叫ぶ理由に全く心当たりが無くて、シャルシュは首を傾げてしまう。
全くかみ合わない二人の様子に小さく溜息をついて、ジグが仕方ないといった様子で手を挙げた。
「アリア、いきなり言ったって無駄だって。俺たちとエルフじゃ常識が違うんだから、怒ったところでシャルにはさっぱり伝わらんって。ただ、まあアリアが怒るのも当然っちゃ当然なんだよ、シャル。そこの所だけは誤解の無いように先に断っておくな」
「……はあ」
全く意味は分からないが取り合えず納得の頷きだけは返しておく。
どうやら自分は彼らの常識に照らすと相当な無茶になる、ということをやってしまったらしいと言うことだけはおぼろげに理解できた。
「それで……、僕の魔術の何が駄目だったんですか?」
「ほら、分かってないんです、この人は! 自分がどれほど危険なことをしてきたか、きちんと教えてあげないといけません」
呆気にとられたような表情でのんきに訊ねるシャルシュを見てますます眉間にしわを寄せたアリアが、フンとそっぽを向きながら怒ったように口にする。
ここまで怒られるようなこととは一体何なのだろうと不思議に思う。
「うん、まあ確かにそうだな。このまま彼を放っておくのは危険だと、俺も思う。そこでシャル、一宿一飯の恩もあるし暫くの間君に魔術の基礎を教えようと思うんだが、どうだろうか?」
にやっと口元を笑みの形につり上げてジグが口にした提案があまりにも嬉しい提案だったものだから、シャルシュは思わず立ち上がって机を思い切り叩いていた
まさか、そんなこと。
彼らを家に泊めたのは、何か人間の話が聞ければいいと思ってのことで、まさか人間の魔術を魔導騎士から直々に習えるとは思ってもみなかった。
そんな提案、勿論願ったり叶ったりで、断る理由なんて微塵も存在しない。
「是非お願いします!」
勢い込んでジグの手を握りしめ、そのままぶんぶんと振り回す。まるで子供のような喜びようだった。
そんな彼らの様子を見ながらアリアは「勝手にすれば良いんです」とそっぽを向いて唇を尖らせている。
彼女にすれば、騎士としてここへやってきた任務とは違う事柄に兄が妙に乗り気であることが面白くないのだろう。根っから騎士として定規で引いた線のような性格をしているアリアには、なるほどこれは寄り道にしか見えないのかもしれない。
ジグはそんな風にそっぽを向いている妹の方をちらりと見やると、シャルシュの手を自分からも握り返して彼の肩をポンポンと叩いた。
「まあ、こっちもよろしく頼むわ。明日からアリアがみっちり授業をつけるから。アイツの授業は厳しいぞ」
「は? 私がやるんですか!?」
急に自分の名前が出て驚きの表情で振り返るアリア。
そんな彼女の様子を意地の悪い笑顔で眺めながら、ジグは言った。
「教えてあげないといけません! と言ったのはお前だろ。それに他人にものを教えるのは俺よりお前の方が絶対に上手いし、熱意もある。世の中適材適所だと思うぞ」
「でも、彼には今要点だけ説明すれば済むじゃないですか! それを何でわざわざ魔術の基礎から教えるなんて」
「亜流の魔術師ほど怖いものもないって、一番分かってるのはお前だろ。なら、二度とあんなことにならないようにこいつをきちんと導いてやれよ。市民を導くのも、騎士の務めじゃなかったのか?」
「それは……そうですけれど」
兄はずるい。
こう言う時だけ真面目な騎士ぶって、正論を並べ立てて自分には反論すら許さない。
普段はだらけている場面も多く、一見騎士に見えないような時もしょっちゅうある。だって言うのにここぞという時にこの人は徹底的に騎士なのだ。だから、尊敬できる騎士にして上官である兄に、自分は逆らえない。
アリアは諦めたように小さく溜息をつくと、シャルシュの方へ困ったような笑顔を向けた。
「そう言うことなら仕方ありません。兄の言ったように、やるとなれば厳しくやるつもりですから、覚悟しておいてください、シャルシュさん」
すっと右手を差し出す。
その右手にシャルシュも自らの右手を合わせる。
「あの、よろしくお願いします。それから、僕のことはシャルと呼んでください。みんなそう呼んでますから」
「はい、ではそうさせていただきますね、シャル」
握ったアリアの手はびっくりするほど華奢でこんな細い手の人が騎士をやっているなんてとてもじゃないけれど信じられなくて、だからシャルシュは油断していたのだ。
アリアの授業の厳しさを少しも理解していないシャルシュは、まだ未来が開けていくような予感に無限にも思える希望を感じて笑顔を浮かべているのだった。
to be continued
WEB版あとがき
今が夜でもこんにちは。因みに僕がこれを書いている今現在は朝です。yoshikemことよしけむです。
Monochronikaの第2回でした。幻想組曲28号へ掲載させて貰った作品なのですが、まあまだまだ序章といった感じですかね。
とりあえず「アリアがむかつく」というそこの貴方。ありがとうございます。今の彼女に対してはそう言う負の感情を抱いて貰うのは作者の意図通りなので。ここから彼女を愛して貰えるよう、
さて、ところでMonochronika 1をご覧になった方の中にはお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、第1回にはちょっとした仕掛け(?)をしているところが二カ所ほどあります。
僕の好きな作品から、少しセリフを引用させて貰ってるんですよね、実は。どのセリフかというと、エリアさんの「限りなく微妙な嘘は誤りに近い」、それからアリアがシラムと戦ってる時に漏らした「微妙な誤りは嘘に近いんです。……あれ、逆だったかな? 微妙な嘘は誤りに近い……?」という言葉。これらはいずれも伊坂幸太郎さんの死神の精度の中の「恋愛で死神」にある「微妙な嘘はほとんど誤りに近い」というセリフを転用させていただいた物です。
英語にはWhite Lieという言葉があるらしいですね。悪意のない嘘は時と場合によっては認められても良い、というようなことを言いたい言葉だったかと思います。上のセリフはそれとは異なるアプローチで嘘付きを解釈してみる、鋭い言葉だと思います。
恋愛で死神の劇中での用法ともまた違った形で使ってみたので、興味のある方は或いは死神の精度を読んでみて比べてみても面白いかも知れません。
実は、Monochronikaでは二回に一回くらいこういうことをやってみようかと画策しています。奇数回で喋らせて、偶数回のWEBあとがきでこうやってちょっと種明かし、なんてことを続けられたら面白いんですけれどね。
それでは、今回はこのあたりで。ではまたいずれ、次の物語の中でお会いしましょう。
yoshikemでした!
作品展示室トップへ
総合トップへ