
シラム・リストゥーバは正義感の強い青年だった。
幼い頃に魔族と鮮烈な出会いをした。その時に彼を助けてくれたのはエリアネル・テルミチェットただ一人だったのだ。他の森林警備隊のメンバーは子供の言う事と歯牙にもかけてくれず、シラムの事を笑って相手にしてくれなかった。そんな時に、彼と、彼の親友である狼を助けてくれたのが、非番で暇をもてあましていたエリアだったのだ。
その時助けてくれなかった大人たちを恨んでいるわけではない。子供の言う事をいちいち相手にしていたら手が足りない、と言う彼らの言い分も、分からないではない。
だが、少なくともシラムはそう言う大人ではなく、あの時彼を信じて動いてくれた師――エリアのようにありたいと思う。
同郷のエルフたちをなんとしても守る。そこに疑いは存在せず、行動理念の全ては村の仲間の為に捧げられる。
それが、彼が自分自身に課した誓いでもあった。
そして、今は亡き友との約束でも、あった。
右手でそれを強く握りしめる。鋭く研がれた一本の牙が掌にほどよい痛みを返してくる。
それは友の形見であり、シラムがここに居る理由の一つであった。
大丈夫だ。こうやって痛みを感じている間は冷静でいられる。
そう自分に言い聞かせて、シラムは目の前に座る少女を改めて見やった。
森林警備隊【森の翼】の本部の一室、来客用ソファに腰を下ろした彼女は、シラムの存在を意に介していないかのように取り澄ました表情でただそこに座っている。自分の所為で人が一人倒れたというのに、そのことを全く気にかけていないような冷徹ぶりである。
「それで、あいつは結局なんで倒れたんだ?」
彼女を睨み付けて、問う。
隣室では現在もシャルシュ・ワイゼンが意識のない状態で寝かされている。
医療部の者の見立てでは単に気を失っているだけ、放っておけば目を覚ますとの事だ。しかし、普通の人は何もなく気を失ったりはしない。シャルシュはエルフとしては確かに異常を抱えているが、それでも健康状態は正常だったはずだ。
その彼が何故倒れるような事になったのか。
全てを知っているだろう女魔導士は小さく息を吐くと、こちらをじっと見つめた。
推し量ろうとするような視線に、心の奥底まで覗き込まれているような気がして薄気味悪くなる。
エルフの寿命は人間の約五倍。アリアとシラムは外見的な年齢はほぼ一緒である。だが、これまでに生きてきた時間はシラムの方が圧倒的に長いはずなのだ。だと言うのにどうだろうか、この両者の立場は。落ち着いた瞳でこちらを覗き込むアリアと、まるで叱られるのを待つ子供のように落ち着きを失っていくシラムの様子は。
端から見ているとどちらが年上なのだか分かったものではない。
瞼を一度瞬いて、アリアは静かに口にする。
「正直言って、私にも正確なところは分かりかねます」
「はあ?」
アリアの表情はとてもではないが冗談を言っているようには見えない。
思わず呆れた様な声を上げて、更にシラムはまくし立てる。
「いやいや、騎士サマ、ふざけるのも大概にしようぜ。アンタ言ってたじゃないか。『全部私の責任です』って。ってことは、」
「誰も、何もわからないとまでは言っていないでしょう」
まくし立てるシラムの声が、苛立ちの混ざったアリアの声に遮られる。
その頬は若干色味を帯びており、これまでの取り澄ました冷静な表情とは随分と異なる。
もしかしたら、外面こそ冷静さを取り繕っていたものの彼女も内心では動揺していたのか。
こちらを睨み付けて、アリアが続きを口にする。
「とにかく、細かい事は分からないにしてもシャルが倒れた原因のおおよそは予想がつきます。恐らく原因は」
そこで一旦言葉を切り、小さく溜息をつく。
「十中八九は魔力炉の疲弊。単純に言えば魔力の欠乏です」
「は? 魔力の欠乏?」
それを聞いて、シラムは一気に安堵の気持ちが広がるのを感じていた。
魔力の欠乏、などという症状をそもそもエルフが起こす事自体聞いた事も見た事もなかったが、それでもその症状が重いものとはとてもではないが思えなかった。
なにせ、
「魔力なんてそこら中にあるじゃないか。なら、シャルシュもすぐ治るんだな」
肩をすくめて、心配して損したとでも言うようにそう言うシラムをじっと見つめ、アリアは呆れた様に肩を落とす。
そのアリアの様子にシラムが疑問を挟む暇さえ与えずに。
「だから、エルフに話しても無駄だと言ったんです。今回は確かにすぐ治ります。でも、シャルのしでかしたことは一歩間違えれば酷いことになっていた」
「……どういうことだ?」
「言葉通りの意味ですよ。それとも、言葉が通じませんでしたか?」
「んなっ!?」
挑発的にこちらを睨め付けるアリアに、思わず気色ばむシラム。
の前に、彼の気勢を削ぐような絶妙なタイミングでカチャリとティーカップが置かれた。
カップから昇ってくる紅茶の香りが甘く鼻腔をくすぐる。
流れるような滑らかさでテーブルの上にティーカップと下皿のセットが三つ並び、シラムの視線が一瞬そちらに下がった瞬間。
ぱあん!
なにやらやたらいい音とともに、頭に軽い衝撃が走る。
「っ、何すんだ、リーネ!?」
シラムが頭をさすりながら、平然とした表情で彼の隣に腰掛けた少女に抗議する。
「まったく、貴方はすぐにそうやって癇癪を起こすんだから。相手の方に失礼でしょ」
リーネと呼ばれた少女はシラムに向かって人差し指を立てて「めっ」とまるで親が子供を諭すように言う。
その行為によってシラムの表情が更にしかめられているのだが、一向に気にしている様子はない。
その彼女が、アリアの方を振り返ってやわらかな微笑みを浮かべた。
「ところで……、アリアさん、でしたか。シャル君は色々問題がある子なんですけど、それでも掛け替えのない私たちの村の一員なんです。だからシラム君もこんな態度ですけど、彼なりに心配してるんですよ」
シラムの方をちらりと一瞥する。
本人は気恥ずかしいのかついとそっぽを向いてしまったのだが、リーネの言葉を肯定しているようにしか見えない。
「私も心配ですし。ですから……、よろしければ分かっている事は全部話して頂けませんか?」
シラムの態度とは対照的に真摯な、かつ有無を言わせぬその口調。
アリアはリーネのその瞳をじっと覗き込んでから言った。
「わかりました。話すだけ話します。どう判断するかは、あなた方で決めて下さい。……ところで、貴方は一体?」
勝手知ったる様子で話を進めていくリーネの態度に流されていたのか、今更という質問をアリアが口にする。
リーネは少々間の抜けたアリアの顔を見て愉快そうにコロコロと笑う。
「あら、自己紹介が遅れましたね。リーネ・テレイシアと申します。シラム君の妻です」
「え?」
「は?」
驚きの声は、アリアとシラムの二人のもの。
窓から入ってきたそよ風に、腰まで伸びたリーネの水色の髪がふわりと揺れる。
困惑と驚愕の視線を一心に浴びて、リーネ・テレイシアは変わらぬ様子でコロコロと笑んでいる。
「冗談です」
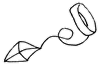
アリアは目の前に座っているエルフ二人を見つめ、一切の期待を捨て去った上で口を開いた。
「エルフに話しても無駄、と言ったのは、そもそもエルフには内在魔力と外界魔力を区別する感覚が無いからなんです」
「ないざいまりょくとがいかいまりょく?」
アリアの言葉に、シラムがわけが分からないといった様子で首を捻る。
黙ってはいるが、リーネもまたキョトンとしている。
やはり、エルフにはそう言う考え方はないのか。アリアは内心の小さな落胆を押し隠して説明する。
「世界には魔力が満ちている。これは知っての通りです。ですが、その一方で私たちは自分の体内に自分たちで生成した魔力を持っているんです」
魔導学の教科書の、お決まりとなっている始まり文句である。
世界には外界魔力と内在魔力が存在する。人間の魔導はそこから始まる。
「でも、自分の体の中の魔力なんか使うことあるのか? 少なくとも俺は使ったこと無いんだが」
「それは使った事がないわけではありません。単に意識していないだけ」
内在魔力は日常的な活動にも使われるのだ。臓器を正常な状態に保つ事から体内エネルギーの最適化まで、生命活動は魔力無しではあり得ないと言っても良い。
つまり、魔力を失った生命は消える。
「おい、それって……」
「シャルについては大丈夫です。そこまで使い果たしたわけではありませんから。では、何故シャルがそこまで魔力を使う羽目になったのか。問題はそこなんです」
「そうね、アリアさんの話だと普通に生活している分には内在魔力を激しく使う事なんて無いのでしょう? なら、彼は一体何をしたの?」
リーネの問いに、アリアは声を落として答える。
この答えは、恐らく二人には理解できまい。
「彼は、魔術を使ったんです」
アリアが口にしたその言葉に、予想通りシラムとリーネはキョトンと間の抜けた表情を返すばかりだった。
やはり、ここにエルフと人間の重大な隔絶があるのだ。しかも、人間はエルフの魔導体系の事を少しは知っているが、逆はない。彼らは人間の魔導体系の事を知ろうともしない。
自分たちが魔力に愛された民である、と言う事から来るどうしようもない驕り。
アリアがエルフたちに対して好感を抱けない理由が、これだった。
「あなたたちの考えている事を当てましょうか。恐らく、魔術なんてそこら辺に流れている魔力を練って作るものだから内在魔力を使うはず無い、とでも考えているのでしょう?」
少し苛立ちの混じった声で、アリアは言った。
「……えっと、ごめんなさい、よく分からないんですけれど、そう言うって事は、シャル君の場合はそうじゃなかったっていうこと?」
「勿論、そうです」
答えを聞いたリーネは未だ困惑を隠せない様子だし、その隣に座るシラムなどさっぱり理解できていないのは間違いない。
やはり、当初の予想通りシラムには言うだけ無駄だったようだ。
無理もない。彼らエルフにとっては魔法や魔術というものは外界に漂う魔力を自らの手の内で練り上げて作るもの。彼らにとってはそれが唯一にして無二の魔法の手段であり、そんな常識の外にある手段など理解の範疇を軽く超えているのだろう。
だが、自分やシャルを初めとする人間の魔導体系はそうではない。魔法とは、まず自らの内在魔力で魔術を組み立てるところから始まる。
「つまり、私たちとあなたたちの魔法は似たような事をやっていても全然別物、ということなんです」
「……なんだか全然説明になってないと思うんだが」
不満顔で口先を尖らせるシラムの方を向き、アリアは小さく笑みを浮かべる。
「きちんと説明しようと思ったら丸三日分くらいの講義になりますけれど」
お話ししましょうか、と小馬鹿にしたような表情を浮かべるアリアに、シラムは苦い表情を浮かべる。
現状、そんな話をちんたらと聞いている時間は勿論無い。
「……納得すれば良いんだろ、納得すれば。それにしても、人間はなんでそんな面倒くさい事をするんだか?」
呆れた様に肩をすくめるシラムのその態度は、まさにアリアが嫌うエルフのテンプレートそのものであった。
彼らエルフが魔力に愛された民と呼ばれている、その驕り。少しばかり魔力の扱いに長けているからと言って自分たちの方が人間よりも優れているという自負がそこかしこから嗅ぎ取れる。
確かに、魔法を扱う上での効率はエルフの方が遙かに良い。これは生まれ持ったモノが違うから仕方のない事なのだ。エルフには自然界の魔力を直接扱う為の感覚器官が備わっており、人間にはない。そのことは純然たる事実として認められており、今更覆りようはない。
アリアたち人間は魔力の流れを自分たちの感覚として捉えられない以上、いきなり外界魔力を練るということは出来ないのだ。
だから、今回シャルシュが倒れたその最大の原因を挙げるとするなら――
「強いて言うなら、人間がエルフじゃないから、でしょうか」
それだけの単純な話だ。
そして、単純故に覆しようのない厳然とした事実だった。
「ごめんなさい、アリアさん。どうにも話が掴めないのだけれども……」
リーネが申し訳なさそうに、そして若干の苛立ちも交えてそう切り出した。
その言葉に、アリアは小さく頷く。
リーネの反応も仕方がない事だ。説明としては今の話は少々端折りすぎ、いや、説明不足と言われても何の文句も言えない。
「シャルの扱う魔法は……、私たち人間に極めて近い方式なんです。つまり、自分の体内の魔力で術の鋳型を作り、そこに外界の魔力を詰め込む。そうして術を発動させている。言ってみれば鉄器を作るような作業に似ているんです」
俯いて、所々自分の仮説に誤りはないかと言う事を確認しながら述べていく。
正直なところ、アリア自身でさえにわかには信じられなかったのだ。まさかエルフに人間と同じようにして魔法を扱う者がいるなど、少なくともこれまでの歴史上では確認されていない。
「対して、あなた方エルフの魔法は外界に無限にある自然の魔力を直接掴み、それをまるで粘土か何かのように自在に操る。全くもって便利な能力です」
ねたみのようなその言葉は、その実アリアの隠しようない本心でもあった。
実際に、人間の魔術師からすればエルフの魔力を扱う能力は幾ら願っても決して手の届かない天の星のようなものだった。どこまでも輝かしいくせに、決して自らの手に入る事はない。
古来幾人もの魔術師がエルフの能力を手に入れる術を探したが、その全てが不可能という壁の前に残酷に屠られてきた。
自分たちの力に無自覚のまま、魔力を自在に扱える事をさも当然のように語るエルフに対して、妬みの感情を全く持たないとなればそれは相当の人格者であるに違いない。
「まあ、そんなことはどうでも良いんです。問題はシャルが
「それが……、なにかまずいのか?」
不思議そうな表情で首を傾げるシラムとリーネ。
二人にとっては、いや、エルフにとってはやはりこの事自体は大した問題ではないらしい。
だが、人間の魔術師からしてみれば、そんな事は自殺行為以外の何者でもない。
小さな溜息をついて、アリアは自分の服の胸元に手を差し入れた。
シラムとリーネが怪訝そうな表情を浮かべる前で、首に提げていた紐を引っ張りだし、何かを取り出す。
「……それは?」
不思議そうな表情で訊ねるシラムの前に差し出されたのは、彼女の掌よりも少し小さな、薄桃色の宝石だった。
丸みを帯びたカットをされており、曇り一つ無く透明で、向こう側が透けてしまいそうだった。温かな色で煌めくそれに、思わず溜息が漏れそうになる。
但し、その中央には斜めに、真っ二つに割れるようないびつな割れ目が入っていた。何らかの補修措置をしてあるのだろう。割れ目によって二つに分かたれただろう宝石はアリアの掌の上でピタリとくっついて、一つの宝石の体を為している。
不規則に、まるで迷子のようにいびつな線を描く割れ目を携えて尚宝石は輝かしく美しかったが、その傷痕が目につかないと言えば当然嘘になる。
だが、そんな風に傷ついてしまったものを、不完全とは言え直してまで持ち続けているということから、その宝石が如何にアリアにとって大切な物なのかは容易に想像が出来る。
「この割れ目と一緒なんです」
アリアは掌の上の桃色を愛おしげに撫でると、そのまま両端を摘んでほんの少し手に力を込める。
ぴしり
乾いた音をたてて、桃色の宝石は二つに分かれた。
流石にシラムの表情が驚きに染まる。
「おい!?」
「構わないんです」
右手と左手、それぞれに別れた桃色の宝石を差し出しながら、アリアはやわらかに微笑んだ。
「一度割れてしまうと、もう元には戻らないんです。ああやって直してみたところで完全に元通りにはならないんです。だからこうやって、傷痕からあっさりと壊れる。この宝石も、魔術式も」
最後についでのように付け加えられた言葉に、シラムとリーネの表情がハッとした物になる。
「分かって貰えたようですね。そういうことなんです。一度壊れた魔術式を修復するのはとても危険な行為なんです。必ずどこかに綻びが出来て、そこから魔法が暴走して崩壊する。つまり、
こくり、とシラムがつばを飲み込む音が聞こえた気がした。
「そいつが起きると、どうなるんだ?」
「植物人間か、場合によっては、死にます。私たちの体内に流れる魔力の流れをズタズタにされますから、良くても暫くは魔術がまともに使えない状態に陥ったり、身体に何らかの障害がでたりするでしょうね」
「『でしょうね』って、他人事みたいに、それなら、お前シャルはっ!?」
「落ち着いてください。シャルの場合は呪壊までは至っていません。言いましたよね、彼は無事だって」
声を荒げるシラムに対してアリアは飽くまでも冷静な口調でたしなめる。
「シャルは、騎士の名にかけて無事です。呪壊を起こす前に彼の構築していた魔術式は完全に解いてしまいましたから、騎士の名にかけて彼には何も異常は起こっていないはずです」
そこまで言い切って唇を噛み、アリアは少し苦い表情を浮かべる。
「もう、私の目の前で呪壊なんて二度と起こさせません」
その小さな呟きはほっと胸をなで下ろしているシラムの耳には入らなかったようだった。
「お礼を言わなくちゃ行けないのは私たちの方みたいね」
呆れた様なリーネの言葉に、シラムがぎくりとなった。
苦虫を噛み潰したような表情でリーネと、目の前に座るアリアの顔を見比べる。
「いや、もともとシャルが下らないことをした原因だってこの騎士サマにあるんだから……」
「でもアリアさんはシャル君を助けてくれたんだから、やっぱり私たちはお礼を言うべきよ。あとあなたはさっきまでの失礼な態度を謝らなきゃね、シラム君」
「……んー……」
自分の非を認めるのが嫌だ、という感情を全面に押し出してシラムがリーネを見つめる。
リーネはというと、腰に手を当てて困ったような表情を浮かべる。
「駄目よ、悪かった事は悪かったって認めないと。それとも、シラム君ってそんなに潔くない卑怯者だったの? あーあ、私、失望しちゃうなぁ」
「ちょ、ちょっと待てよ! 誰も謝らないなんて言ってないだろ!」
「じゃあ、ちゃんと、今、この場で、アリアさんに謝って」
「んなっ、今すぐ?」
「そうよ。謝って、それからシャル君を助けてくれた事のお礼を言ってよ。私たちの村を代表して」
「俺は村を代表するほどの立場じゃ……」
なおも渋るシラムに、リーネはとっておきのひと言を出す。
「良いから早くしてよ。それでも【森の翼】の隊員なの?」
「あー、もう、分かったよ! 言えば良いんだろ、言えば!」
ダンッと足を踏みならして、シラムがその場に立ち上がる。
背筋に棒が一本通ったかのようにまっすぐの姿勢で、やや斜め上に視線をやり胸を張る。そして、その胸の前に右手の平を添えた。
エルフ流の敬礼の姿勢である。
「アリア・ムーシカ魔導騎士殿、先ほどは貴女に対して多大に無礼な態度をとってしまい、申し訳ありませんでした。そのことを深く謝罪し、そして我らが同胞シャルシュ・ワイゼンを窮状から救っていただいた事に心から感謝の意を表し、村民を代表としてここにお礼申し上げます」
そのシャルシュの態度に合わせてか、アリアも座っていた椅子からすっと立ち上がる。
やわらかで自然な動作でありながら、すくっと立った姿勢はまっすぐで凛々しい。彼女は右手を額にかざすように人間の敬礼姿勢をとる。
「感謝の言葉痛み入ります」
そう、応えて、ニコリとやわらかな笑みを浮かべる。
シラムはリーネの方へ目線をそらし、これで良いのか、と目で問いかける。リーネが笑顔のまま小さく頷くや、ふぅと盛大に溜息をついて肩の力を抜いた。
「まあ、私は騎士として当然のことをしたまでなのですけれどね」
アリアもそう言って敬礼をやめ、再び椅子に背を預けた。
「でも、シャル君を助けて貰った事に代わりはありませんから」
リーネはそう言ってコロコロと笑みを浮かべた。
「それにしても、うちのシラム君が失礼な態度でごめんなさいね。根は悪い人じゃないんだけれど、どうも昔から荒っぽいところが抜けなくて」
「いえ、別にそんなことは……。エルフと人間の間に溝があるのは分かってるつもりですし」
アリアはそう言って、出されていた紅茶を一口飲んだ。もう、とっくに冷めてしまっていた。まるでそれがエルフと人間との関係のように思えて、少し残念に思う。
「あ、紅茶もう冷めちゃってるんじゃない? なんなら淹れ直してくるけれど」
「いえ、構わないでください。冷たい紅茶も嫌いではありませんから」
そう言ってもう一口。冷めているとは言え、甘やかな香りが口腔一杯に広がって、全身に染み渡るような気がする。
美味しい。
冷めて尚これだけ楽しめるというのは相当巧く淹れたという証拠だろう。
紅茶の温度とは裏腹に、心が温かくなるような感じだ。
「そう? なら良いんだけれども。アリアさんも、あんまり肩肘張らない方が楽だと思うわよ。エルフと人間が仲悪いって言っても、ここで私たち個人がわざわざいがみ合う必要なんてないんだし」
そう言って、リーネも一口紅茶を口に含む。
「……はあ、それはそうですけれども」
彼女は一体何が言いたいのか。図りかねたアリアは首を傾げる。
その様子に、リーネは思わず苦笑を漏らした。
「つまりね、私は、アリアさんと仲良くなりたいと思ってるの」
「はあ、そうですか……、って、え?」
今、彼女はなんと言った?
アリアは混乱する頭でどうにか状況を整理する。
彼女は、今自分と仲良くなりたいと言った。それはつまり友誼を結びたいということだろう。
「しかし、リーネさん、私は人間で貴女はエルフなんですよ」
「だから、そんなの気にする事無いって言ったところでしょう? シラムに話を聞いた時から気になってたのよ。だって、人間の若い女の子でしょ」
ふっとリーネの表情にえもいわれぬ笑みが浮かぶ。まるで獲物を見つけた肉食獣のように怪しげに口元がつり上げられ、舌が唇を撫でる。
人間の若い女の子だったら、一体なんだというのだ。
ゾクリとするような笑みに一瞬アリアが射竦められ――
「気になるじゃない! ねえ、人間の街ではどんなおしゃれが流行なの? 多分こんな村では想像も及ばない可愛い小物があったりするんでしょ。ねえ、アリアさんの住んでいる街ってどんなところなの?」
ただのミーハーだった。
「え、えぇっと……」
そう言う話題にはどちらかというと疎い方であると自認しているアリアは、突如堰を切ったような勢いで喋りはじめて目を輝かせているリーネに抑えるようジェスチャーをする。が、閉鎖された狭い村の中で思春期を過ごしているエルフの少女の好奇心はちょっとやそっとで収まるような気配はなかった。
シラムの方に助けを求める視線を送ってみるも、彼は諦めたように首を振るばかり。
アリアは困ったように溜息をつくと、苦笑いを浮かべながらリーネに向かって言った。
「分かりましたから……、とりあえず質問は一つずつにしてもらえますか?」

女という生き物は何故こうなのだろうか。
シラムは目の前で繰り広げられている光景を見やって、幾度目ともつかない溜息をついた。
先ほどから尽きる気配もない黄色い声。延々と喋り続けても話題は全く尽きる様子もないようで、アリアとリーネの会話は一層の盛り上がりを見せている節すらある。
いや、会話というのも少しおかしいか。なにせリーネが一方的に質問を続け、アリアがそれにひたすら答えている、と言う構図は最初から一切変わることがない。ワクワクした気持ちを隠そうともしないリーネの質問に、アリアもまんざらではない様子で楽しげに答えている。彼女も彼女でリーネとのお喋りに興じるのは楽しいらしい。それまでのお堅い態度からはとても想像のつかない、年頃の女の子相応の無防備な笑顔を見せている。
滅多に聞くことの出来ない人間社会の話を、見た目同い年の女の子の口から直接聞けるとあって、リーネのテンションはここ数年シラムが見たこともないくらいに上がっていた。
「へー、流石にこんな村とは大違いね」
リーネがその言葉を口にするのも既に何度目か分からない。彼女にとっては聞くこと全てが物珍しくて仕方のないことなのだろう。確かにシラムが聞いていても人間の街の話は驚くようなことばかりだ。だが、所詮はこの先も恐らく死ぬまで関わりのない世界の話だ。今ひとつ興味が持てない。
「凄いのね。一杯教えて貰って、勉強になっちゃった。ごめんなさいね、私が質問してばっかりで。アリアさんも何かこの村のことで知りたいことがあったら訊いて頂戴ね」
そう言って無邪気にはにかむリーネ。長い髪が柔らかく揺れる。
そんな彼女の方を見て、それから少しシラムの方へも視線をやり、アリアは考え事をするかのように宙に視線をさまよわせる。
質問を考えているのか。
「あ、でもこんな田舎の村のことなんかで訊きたいことなんて、無いわよね、多分。別に無理して訊くこと考えてくれなくてもいいのよ」
「いえ、一つ、気になっていることがあります」
そう、ぽつりとアリアが漏らす。
唇に指先を当て、真剣な表情でティーカップの紅茶の水面を見つめる。
まるで、その質問を口にして良いものか吟味するかのように。
何か、まずい質問が来る。シラムの中にそんな予感めいた物が走る。慌てて何かを口にしようとするが、言葉が出てこない。なんと言えばいいのだ。その質問を口にするなと。しかし単なるシラムの思い過ごしかも知れない。はっ、と小さな息だけ吸う。
アリアの逡巡は一瞬、彼女は意を決したように口を開いた。
「シャルシュが特別、というのはどういうことなのですか?」
そうきたか、とシラムは苦い表情を浮かべる。質問を促したリーネも隣でどう答えたものか顔をこわばらせている。
リーネが先ほどの高いテンションから巧く頭を切り換えられるとも限らないし、ここは自分が話すべきだろうか。
そう思って、シラムは重い口を開く。
「まず、どこまで知っている?」
「何も。ただ、彼の口から自分は他のエルフとは違う、というのを聞いただけです。ただ、あなたたちの様子を見ていても彼が他のエルフたちから孤立しているのは事実のようで、気になったものですから」
「そうか……」
成る程。確かに違和感を感じても仕方のない状況ではある。エルフの集団は人里離れたところに、外部との交流があまり無い状況であることが多い。そして閉鎖された環境故に集団内での絆は強い、というのが通例だ。実際、この村もシャルシュ・ワイゼンという特異点を除けば他の村民は極めて強固な絆で結ばれているのを村民であるシラム自身は知っている。
そういうことは、空気である程度分かるのだろう。アリアが違和感を覚えるのも納得のいく話だった。
だが。
「シャルシュ本人が何も言っていないのなら、俺たちの口からは何も言えないな」
「そう、ですか。そうですよね。詰まらないことを訊ねて申し訳ありませんでした」
本当にすまなそうに頭を下げるアリアに、リーネが慌てたように声を掛ける。
「詰まらない質問、だなんて、そんな……。ただ、本当にあの子の事は少しデリケートな問題だから……」
「リーネ」
あたふたと余計なことまで喋りそうになるリーネを言葉で制する。
「もし、それが必要ことなら本人が話す筈だ。それがないんなら、あんまり首を突っ込まないでやってくれ」
「それくらいは、分かっているつもりです」
「助かるよ。それから、もう一つだけ。さっきアンタはシャルシュが孤立してると言ったが、そんなことは俺たちだって本意じゃないんだ。勿論、親を亡くしてすぐの頃のアイツに対して俺たちにも戸惑いがあったりして、巧く接せ無かったのは事実で、それは俺たちにも非がある」
顔を伏せ、小さく、しかし深く、心に積もった澱を吐き出すかのように溜息をつく。
「けどな、閉じこもって、頑なになってるのはむしろ奴の方なんだ。俺たちはアイツのことを仲間だと思ってるのに、アイツはそれを受け入れてくれない。アイツは自分から独りになろうとしている。今じゃ唯一まともに喋るのはエリアさんくらいだ」
決して自分たち、周囲のエルフの責任を無かったことにするつもりはない。
だが、シャルシュの考え方は間違っている。
そして、出来ればこの歪な関係を修復して、もう一度彼を、本当に村の仲間として迎え入れたいと思っている。これはシラムだけでなく、村のエルフたちの総意でもある。
なのに肝心の本人にはこれっぽっちもとりつく島がない。シャルシュは他の村人たちから怯えるように隠れて、独りきりで家に引きこもっている。
「けど、昨日アイツは自分の意志であんたらを家へ呼んだ。俺は、これが何か一つのきっかけになるんじゃないかって思ってるんだ。だから、身勝手な話ではあるんだが、アンタにアイツを変えて貰いたい」
じっと、アリアの桃色の瞳の奥を見つめる。
シラムの真剣さが伝わったのか、アリアも彼の視線から目をそらすようなことはせずに見つめ返してくる。
そうして見つめ返すこと十数秒。沈黙に耐えきれなかったのか、リーネが小さくけほっと咳を漏らした。
それをきっかけに、アリアが息をつく。しばし考えるように俯き、呟いた。
「そうですか」
そう言って紅茶を口に運ぶ。冷めた紅茶をちびりちびりと、既にカップには殆ど残っていないのに、香りを楽しむかのように優雅に手の中でカップをもてあそんでいる。
そうして、カチリ、と小さな音をたててカップをテーブルの上へと戻す。
「そうですか、って、それだけか?」
「はい」
「他人事みたいに……、まるで関心なしか?」
「実際、私にとっては殆ど他人事のようなものですから」
「ああ、そうかよ。アンタがそんな冷たい人だとは思わなかった。自分が宿を借りている相手に対して、そんな風に無関心で居られるなんてな!」
ダンと机を力任せに叩く。衝撃でティーセットが一瞬浮き上がり、陶器がチンと音をたてた。
怒りを露わにしているシャルシュに対し、アリアの反応は冷めたものだった。
「そう言われても……、私にはどうにも出来ないでしょう。大体私に対して具体的に何を期待しているというのですか?」
じとっと見つめられ、思わずシラムは言葉に詰まる。
具体的に……。
そう言われると咄嗟に出てくる言葉がない。
「それは、その、アイツの考え方を変えてやるというか……、自分が間違っていることを分からせてやると言うか……」
「なら先ほどのあなたの話を直接彼に聞かせたら良いのではないですか? そうすれば彼も分かると思いますが」
「そんな根の浅い話なら苦労はしねえ」
エリアにも協力して、これまでにも幾度かのアプローチは試みた。が、シャルシュの態度は一向に変わる気配がなかったのだ。
心からの怯えにも似た、シラムたちに対する拒絶。それがいつも変わらぬシャルシュの態度だった。
「それは何故なんですか? シャルシュの抱える事情とはなんなんですか?」
アリアはこちらの目を覗き込み、静かに、しかし有無を言わさない口調で訊ねてくる。
その目を見て、言葉に詰まる。ここで素直に教えてしまいたい、そんな気持ちを全力で押さえつける。
「だから、それは俺たちからは言えないって。知りたいならどうにかしてアイツから直接聞いてくれ」
先ほどと同じ答えを渋々返す。
アリアはその答えを聞いて、更に暫くシラムの瞳を見続け。
「……だから、今はどうにも出来ないと言ってるんです」
「でもな、……って、『今は』? 今、アンタ『今は』って言ったか?」
「そんなに今今言わなくても良いですよ」
「じゃあ……、」
表情を緩ませるシラムに対し、アリアは相変わらずの素っ気なさで言う。
「勘違いしないでください。もし、これから先この村に滞在して何か私に出来ることが見つかれば、努力はする。その程度の話です。何をするとも、何が出来るとも言ったわけではありません」
「それでも構わんさ。俺が勝手に期待してるだけだからな。それにしても、そうならそうと最初から言ってくれれば良かったのによ」
「出来ない約束は、しない主義なんです」
アリアの答えはやはり素っ気なかったが、シラムの気のせいでなければそこにはどこか優しさのようなものが感じられた。
ほんわかとした沈黙。
シラムとアリア、どちらも言葉を発する気配がない。もう話すべき事は話し終えたし、お互いに何も言うことがないのだ。
その沈黙に耐えきれなかったのは殆ど会話に参加出来ていないリーネだった。
「あの、アリアちゃん、私、さっき話してた魔導アクセサリっていうのが気になるんだけど、もうちょっとお話聞いても良い?」
呆れ混じりの溜息をこぼしたのはシラムだ。が、アリアはそんな彼の様子を気にする風でもなくアリアの方へと向き直る。
「あ、はい、この子みたいに大切な品物に魔導の力を込めて使うっていうのも、よくあることなんです。勿論、道具によって向き不向きがあるんですけれども」
その彼女が掌に先ほどの桃色の宝石を載せ、その表面を愛おしげに撫でる。
と、その表面が淡い光を放ち、
「えっ……?」
「そいつは!?」
次の瞬間、アリアの両手中指から糸が伸び、掌の上には桃色の割れた宝石の代わりに、同じ色をした二つの振り子の重りが載っていた。二つに割れた宝石の欠片、ではない。何より、いびつな形ではなく綺麗な紡錘形をしている。
それは先日シラムが戦った際に彼女が取り出した魔導の武器、ナントスエルタに他ならなかった。
「私の場合はこうやって、思い出の宝石をお守り代わりの魔導具に使っています。多くの宝石は魔導具として扱うのに適してますから」
「それで、その道具でこないだは俺を良いように手玉にとってくれたってわけか」
ふて腐れたように呟くシラムに、アリアは意地の悪い笑みを浮かべる。
「ああ、そう言えばシラムさんはこの子を見たことがあるんでしたっけ。あの時はシラムさんがどうしても武器を使えと言ったから仕方なく取り出したのですけれども」
「なんだよ、その言い方じゃ、まるで必要なかった、みたいな感じじゃないか」
「まあ、言ってしまえばそうですね」
「はあっ!?」
自分程度の相手なら武器無しでも充分戦える。そう言われているようで、シラムは気色ばむ。が、対するアリアは飄々としたものだった。
両掌に一つずつ、桃色の宝石を乗せて小さく息を吐く。
「私の場合は、素手でも武器を持っていても大差はないんです。なにせ、私の得意分野は制御魔術ですからね、体一つ、自分の魔力を扱う精神力があれば、事は足りるんです」
「じゃあ、得物を出せって言った俺の様子は、さぞ間抜けだったろうな」
「こら、シラム君、拗ねたって格好悪いだけだよ」
口先を尖らせて不機嫌な様子でそう言うシラムを、リーネがたしなめる。
が、アリアは優しげな笑みを浮かべ、
「理論の上では、そうですね。でも、実際の場合はそうでも無かったんですよ」
その言葉に、え、とシラムとリーネの疑問符が重なる。
二人の様子を愉快そうに眺めて、アリアは続きを口にした。
「お守りなんです。無いと不安で、逆にあれば勇気が出てくる。私にとってこのナントスエルタはそう言うお守りなんです」
そう言って両手の上で大人しく横たわっている振り子を愛おしげに眺める。
そこに詰まっている想いが具体的にどのような物かはシラムの知るところではなかったし、知る必要があるとも思えなかった。ただ、彼女にとってそれはとても重要な想いなのだという、そのことだけはよく分かった。
「分からないでもない。戦士には、そう言う拠り所が必要なんだ。でないと、自分より強い相手には立ち向かっていけない」
そう言って、気付けば先ほどからずっと右手で握りしめたままだった自分のお守りの感触を確かめる。
自分も、彼女も、同じだ。
信念の下で、持てる力を精一杯出し尽くそうとしている。
そうでなければ、自分の想いを語る時にあんな優しい目をする筈がない。
そんな共感を覚えて微笑みを浮かべたシャルシュだったが、アリアの言葉はすげないものだった。
「まあ、私が貴方を倒すのにこの子の力は必ずしも必要だったわけではありませんが」
かちん、と空気が固まる。
和やかだった雰囲気が目に見えて凍り付いて、リーネ一人がただ困ったように首を傾げている。
「お前……、人が折角良い雰囲気で話をまとめようとしてたのになあ」
「ええ、分かってます。良いお話でまとめられたくらいであなたと私を同じように捉えられるのが少し心外でしたので」
平然とそう言ってのけるリーネ。その口元が小さくつり上がり、クスリと笑みを漏らす。
「上等だ。やっぱりアンタとは仲良く出来そうにねえ。表へ出ろ、この間の決着つけてやる」
「それは結構ですけれど、また同じように負けるのが関の山ですよ」
立ち上がる気配すらなく優雅に紅茶を口にするアリアの態度に、シラムの怒りの針が一気に振り切れる。
「そう何度も同じ手を喰らってたまるかっての。いいから、表出ろや」
しかたありませんね、と呟きアリアが立とうとしたその時、
ガタン、
物音はシャルシュの寝ている部屋の方から聞こえてきた。一同が何事かと思っている間に、きぃと軋みを立てて木造の扉が開く。
「……あ、アリアさん、僕、どうしちゃったんですか……?」
弱々しげに、シャルシュが顔を出した。
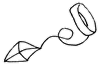
呼び声に応えて居間へ向かうと、既にシャルシュが夕食の準備を殆ど整えていた。
魔力消耗で倒れたその日の内くらいゆっくり休んでいればいい、と言ったのに、客人に台所仕事をして貰わなきゃならないほど落ちぶれてはいない、と言って退かず、彼はこうしてアリアたちの分も一緒に夕食を作っている。
先ほどから良い匂いが漂ってきていたが、今日はやはりシチューらしい。それからソーセージやハムを盛り合わせたサラダがあり、ご飯。居候には十分に過ぎるくらいのメニューだ。
「私、手抜きで良いって言いましたよね」
シャルがお椀に盛ったシチューを手に取り、机へと配膳しながらアリアは言った。
が、エプロンを着けてお玉でシチューを掬っていたシャルシュは、まなじりを下げて困ったような表情でアリアの方を見返す。
「これでもいつもよりは手抜きなんですけどね。本当は良い物を作りたいんですけれど、あんまりやるとアリアさんに怒られそうだから控えめにしてるんですよ」
「これが手抜きって……、だったら私たちのいつもの食事は一体何なんですか?」
目の前に堂々と並んであたたかな湯気を立てている料理を見て、アリアは呆れて溜息をついた。いや、確かに昨夜の晩ご飯と比べれば品数も少ないし、作るのに掛かる手間も随分と少なくて済みそうだが。
それにしても普段の自分たちの食事――二人暮らしで兄と当番交代で作るごく簡単な料理とも言えない品々――と比較してしまえば、やはり溜息の一つや二つはつきたくなる。
昨夜思ったこと、すなわち、このエルフの少年が非常に家庭的である、ということはやはり間違いないらしい。
「あの……どうかしたんですか?」
「いえ、何でもありません。自分が少し惨めに思えてきただけです」
「ええっ!? 一体どうしたんですか!?」
「だから、どうもしません」
大袈裟な驚きの声を上げるシャルシュに軽く笑んで頭を振る。恐らくこの少年には一生分かるまい。料理の手を抜くことにとことんまで腐心する人がいる、などという事実は。
と、そこでふと、シャルシュがかき混ぜているシチューの鍋が妙に大きいことに気付いた。のそりと部屋に入ってきたジグも含めて三人分……、にしては幾分どころか常識外れに多い量。軽く十人前分くらいはある。
「あの……、そのシチューの量はもしかして?」
「ええ、多分エリアさんが今晩も来ると思うんで、その分です」
つまり明らかに過多な分はエリア用、ということらしい。その量については何ら違和感がない表情で鍋に蓋をし、笑顔でテーブルに向かうシャルシュ。
呆れをより一層深いものとしながら、アリアも席に着く。
「それで、シャルの特訓はどうだったんだ?」
ソーセージを頬張りながら、ジグが思い出したようにそう訊ねてきた。
「私ですか?」
質問の相手を図りかねて、アリアは訊ね返した。
ジグが呆れた様に頷く。
「鬼教官のしごきの感想にも興味があるが、そっちは後でも良いだろ」
「そうですね、その質問は私のいないところで存分にどうぞ」
「んで、どうなんだよ、お弟子さんの実力のほどは」
ジグと、それから自分の評価を聞きたくてしょうがないシャルシュ本人にも興味津々の視線を向けられて、アリアはしばし視線を宙にさまよわせる。そして迷いながら、おずおずと口にした。
「実力……というか、魔法出力に関しては流石と言う他はありませんね。昨日思った通り、流石はエルフです。最大出力ならキャシーにも勝るかも知れませんね」
ふと、故郷で別の任に就いているだろう友人の名前が口をついて出た。
アリアの口から出た名前に、ジグも感嘆の声を上げる。
「ほお、あのキャシー嬢よりも上と来たか。そいつはなかなかだな」
「上とは限りませんけれどね。でも匹敵するのは確かでしょうね」
二人して頷くアリアとジグの兄妹。その様子に、堪らずシャルシュが訊ねた。
「あのー……、さっきから名前が出ているキャシーさんって、どなたですか?」
と、そう言えばシャルシュは知らないのだった。そもそも知っている筈がない。
が、アリアが説明しようとするのよりも早く、ジグがさらっと口を挟む。
「アリアの友達なんだが、シャルに説明しても多分この先縁はないさ。今のは、要するにシャルの
「はあ……、そうなんですか、ありがとうございます」
腑に落ちていない様子でそう頷くシャルシュ。それもそうだろう。今ので納得しろと言うのも無理がある。
とはいえ、ジグの言う通りで、彼女のことを説明するにしたところで話は長くなる上にシャルシュにこの先縁があるとも思えない人物だ。
ならばこれは悪くない妥協点なのかも知れない。
アリアはそのように独りで納得してしまう。
そしてシャルシュの評価を再開し、
「それで、話を戻しますけれど、……つまりはそういうことなんです」
「ん? ああ、そういうことか。成る程な」
と、わずかに一言で二人は合意を得てしまった。
第三者には全く意味の分からないやりとりに、シャルシュは二人の間で視線を彷徨わせる。
無理からぬ事だ。もしアリアが今のシャルシュの立場だったとしたら、やはり同じようにちんぷんかんぷんになっていることは間違いない。
「えっと……、どういうことなんですか?」
自分の評価が良く分からない内に下され、そして恐らく雰囲気だけでそれが決して良くない評価だと言うことは判ったのだろう。シャルシュが不安そうな表情を浮かべてジグとアリアを交互に見る。
口を開いたのはジグの方だった。
「つまり、だ。少年、君はこれから大変だなぁと言う話だよ」
「はい?」
全く意味が分からない、という表情で首を傾げるシャルシュ。困ったような表情でジグとアリアを交互に見て、ひたすらに首を傾げる。まるで道に迷った子羊のようで、見ていられない。
今のジグの説明は意地が悪いにもほどがある。
「兄様、説明するんでしたら、そんな風にかいつままずに、ちゃんと分かるように説明してあげてください」
「いや、最初に思いっきり略したのはお前だろ」
呆れた様に、意地の悪い笑みを浮かべてくるジグ。その反応に若干こめかみがひくつくのを感じながら、アリアは努めて冷静に言った。
「私は最初からシャルに理解させようとは思ってません。そもそも質問者は兄様なんですから、兄様だけ分かっていれば充分でしょう」
「いや、でもシャルが知りたそうだったから」
「ですから、その期待に応えるのでしたら半端にではなく、きちんと分かるように説明してあげてください。でないと、」
でないと?
続きを口にしようとして、アリアは言葉に詰まった。
でないと、何だというのだ。
あれ、今自分が何を言おうとしていたのか、わからなくなった。
「でないと、なんだ? 別にシャルが分からなくてもいいんだろ、お前は」
「そ、それはそうですけれど……」
「なら、別に俺が十分な説明をする必要は無いだろ」
「ですけど……」
ますます意地の悪い笑みを浮かべる兄を見つめ、アリアは必死に言葉を探す。
自分は何故こんなにも必死になっているのか、何か理由があるように思うのだが咄嗟に思いつかない。
シャルシュに真実を話さない兄の態度の、何が引っかかるのか。
「そうだ、騎士の道ですよ。そうやって半端に教えて生殺しみたいにするのは騎士の道に反します。だから、説明するならちゃんとしてあげてください」
それが引っかかっていたのだ。
教えるなら教える。教えないなら教えないではっきり分ける。そうして貰えば、何も問題ない。自分の中のよく分からない感情に、アリアはそう結論づけて納得した。
「そんなもんか?」
「そんなものです」
「ま、そう言うことらしいんだが、さて、シャル、お前はどう思う?」
ジグが今度はシャルに話を振る。
しかも、相変わらず具体的な中身には触れない、酷く意味の曖昧な問いだった。
「もう、兄様!」
「まあ、良いから黙ってろって、アリア先生。人から教わるばかりが勉強ってわけでもないだろ?」
その一言でハッとなる。
ただ意地の悪いだけではない、何か企みでもあるかのような兄の表情に、アリアは口をつぐんだ。
「つまり、君の魔力容量は高いと評価されたわけだ。それは強力な魔法を扱えるということを示している」
「はい……」
くすぐったそうな表情を浮かべてジグの言葉を聞くシャルシュ。
「ところで、俺たち人間の社会にはこんな武器があるんだ」
不意に、ジグが懐に手を差し入れてテーブルの上に何かを取り出す。
黒光りする、「く」の字型に折れ曲がった太い棒、とでも言えばいいだろうか。重厚な見た目が放つひやりとした気配。食卓に、これほど不釣り合いな物体もそうそう見かけられるものではない。
人体を生かす為の営みが行われる場において、空気を塗り替えるほどの圧倒的な存在感を伴って現れた殺人の為の道具。
「拳銃……って奴ですか?」
驚きを隠せない様子でシャルシュが口を開く。視線はジグの取り出した銃に吸い寄せられるようにして、離れない。
ジグの片眉がぴくりと上がり、こちらも驚きの表情を浮かべる。
「知ってたのか」
「ええ……、何度か雑誌で見たことがあります。でも、本物を見るのは初めてです」
「そうか、なら、コイツがどういうものかも知って居るんだろう?」
ジグの手がごく自然な動作で拳銃のグリップを握り、一切の殺気すら感じさせる事無くそのまま銃身をシャルシュの方へと向ける。
ジグと向かい合って座る彼の眉間に銃口が吸い付くまで、わずか一秒にも満たない間。シャルシュに出来たのはハッと息を呑むことだけだった。

「……兄、様?」
「俺がこの引き金を引いたらどうなるか、分かるか?」
アリアの言葉が耳に入っていない様子で、ジグがシャルシュに問いかける。
シャルシュにはその目が、夜の底のように暗い光を宿しているように見えた。
彼の意図が読めなくて、喉が引きつる。一瞬にしてからからに乾いた声帯をどうにか震わせて声を絞り出した。
「弾が飛び出して、僕は死にます」
「そうだな。この距離なら外すこともない。殺意なんてこれっぽっちも見せなくたって人を殺せる、そんな冗談みたいな
一体、自分は何かジグの気を損ねるようなことをしただろうか。
こんな風に死をゼロ距離で突きつけられるような、決定的な何かを。
額に当てられた銃口がひんやりとした感覚を伝えてくる。まるでそこから血液に氷が雪崩れ込んでくるかのように、全身が空寒く冷えていく。
氷河でも飲み込んだかのように――胆が凍える。
「試しに引いとくか」
ジグの指が引き金に掛かる。
理不尽で滅茶苦茶で理解不能な死が一斉にスタートラインに着く。
迅速且つ確実に、あまりにも突然にシャルシュの下へと辿りつくべく、今レース開始の合図を前に。
位置について。
用意。
かちり
予期されていた乾いた音は鳴り響かず代わりに金属のぶつかる音だけを聞いて、シャルシュは自分がまだ生きていることを知った。
「………………………………………………え?」
「『え?』じゃねえよ、ド阿呆が。俺が本気でお前を殺すと思ったのか? ったく、アリアもそんなに顔面真っ青にしやがって……、俺は恐怖の殺人鬼じゃねえっての……」
「分かってます。でも、幾ら殺すはずがないと分かっていても、今のは流石に胆が冷えました」
アリアがばつが悪そうにそう言って、ジグを睨み付けた。
ジグが呆れた様に肩をすくめて、そのまま銃を再び懐へとしまう。
「そいつは、俺の演技力もまんざらでもないって事だな。まあ、安心しろ、シャル。コイツは魔力式の銃だから、術者が火薬代わりの魔力を込めなきゃ絶対撃てないように……って、おい、シャル?」
シャルシュは体がふにゃふにゃと崩れ落ちていくのを感じながらジグの言葉を聞いていた。
本気で死ぬかと思った。
どうしようもなく怖くて、本当にこのまま死んでしまうのだと思った。
全身が安堵でだらしなく弛緩し、そのまま椅子の上をずるずると滑る。顔がテーブルと同じくらいの高さになるまで滑ったところで何だかバランスがとれて、まだ立ったままこちらを心配そうに見つめているジグのことを見上げた。
「もう、兄様の演技が過剰なんです。こんなになるまで驚かさなくても良いじゃないですか」
「ははは……、いや、流石にこれはおにーさんもびっくりだ。悪かったな、シャル」
そう言うジグに引っ張り起こされて、どうにか椅子にもとの姿勢で座る。
全身の筋肉に徐々に力が入るようになってきて、ようやく元通りに体を動かせるようになってきた。
「で、だ。今シャルには一回死んで貰ったわけなんだが……、怖かったか?」
「見れば分かるでしょう」
アリアの冷静な言葉に、これ以上無いほどに心の底から首を縦に振る。
本当に怖かった。死ぬかと思った。もうあんな思いは二度としたくないと、本気で思った。
「つまり、それが力の恐さだ。巨大な力は使い方を誤れば何が起こるか分からない。こいつだって、使い方を誤れば傷つけたくない人を傷つけるし、自分が傷つくこともある」
そう言って胸元を叩く。先ほどしまった拳銃のことを言っているのだろう。
「今、手練れの殺し屋と、ずぶの素人……お前みたいな奴がそれぞれ拳銃を持っているとする。シャル、お前はどっちが恐い?」
「えっと……殺し屋、です」
戸惑いながら答える。
それはそうだろう。ただでさえ殺し屋なんて恐い職業の人があんな強力な武器を持っていたら、恐くない方がどうかしている。
「そうか、そうだな。確かに、拳銃を持った殺し屋は恐い。そんな奴に狙われたら、手も足も出ずに殺されちまうかも知れない」
ジグはそこで一旦言葉を切り、小さく息を吐く。
そして、背筋を一度振るわせると言った。
「だが、俺は素人の方が恐い」
その言葉を発した時のジグの目は真剣そのもので、決して冗談を言っているようには見えなかった。
「な、なんでですか?」
「何が起こるか分からんからさ。プロの殺し屋なら、狙った獲物だけを確実に仕留めて終わりだ。だけど、素人が銃の扱いを間違えると何が起きるか分からん。誰が死ぬか、わからん。それは、恐い」
確かに、ジグの言うことも一理ある。
仮に自分が狙われている状況だとして、手慣れた人間がやってくるなら自分一人を殺してそれで終わりだろう。だが、銃の扱いに慣れていない人がもし暴発でもさせようものなら……。
「僕以外も、傷つくかも知れない」
「そういうことだ。力の使い方をちゃんと分かってない奴が力を持っていることほど、恐ろしいことはない」
真剣な表情でこちらの目を覗き込んでくるジグ。その意味するところ、彼の伝えたいことが、不意に頭の中で像を結んだ。
「つまり、それが今の僕っていうことですか」
「分かってるじゃねえか」
ジグがにんまりと口元をつり上げる。
正解、ということだろう。その反応に、嬉しさがこみ上げてくるのを感じた。
「お前みたいにでかい力を持ってる奴は、その制御を完璧に出来なきゃ抜き身の刃物と一緒なんだ。どうやら、お前の魔力容量の大きさは昨夜考えてたよりもずっと大きいらしいからな。アリアが納得するくらいの技術を身につけるのは、大変だぜ」
そう言って、ジグはまた意地の悪い笑みを浮かべる。
それに笑い返して、シャルシュは言った。
「大丈夫、頑張りますよ!」
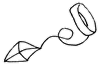
「それにしても、エリアさん来ませんね」
三人とも既に食べ終え、テーブルの上には凡そ一人の為に残されたとは思えない量のサラダとシチューが鎮座する中で、シャルシュが寂しげに呟いた。
「本当にいつも来て居るんですか?」
アリアは呆れて訊ねる。
自分より遙かに年下の少年に毎日こんな大量に、こんな美味しいご飯を作らせて生活しているなんて、なんて怠慢だ。そんな生き方は人として何かが間違っているのではないだろうか。
「最近はずっと毎日だったんですけれど……、何かあったのかなぁ」
姿を現さない隣人に対する心配の気持ちを全面に出しながら、シャルシュはエリアの家の方へと視線を向ける。
そんな仕草にどことなくムッとした感覚を覚えた。
「昨夜は徹夜されていたそうですし、晩ご飯を食べられる状況じゃないんじゃないですか?」
「でも、今までもこういう事はたまにあったのに、その時は食べに来ていたんですよ」
「けれど、来てませんよね」
シャルが視線を向けている方へ、アリアもちらりと目をやる。
窓の外、隣家の窓には明かりが灯っていない。
「じゃあ、シャルはエリアさんと、今日も晩ご飯を食べに来る、と言う約束をしたんですか?」
「いえ、そう言うわけじゃ……」
「なら、いつもはどうなんですか。きちんと約束をした上で、シャルがご飯を作って、エリアさんが食べに来て居るんですか?」
「それも……、違います。きっかけはもう忘れちゃったんですけど……、でも別に約束があるとか、そういうわけじゃ……」
「なら、良いじゃないですか」
アリアが軽い口調でそう言う。
その言葉に、シャルが目を丸くする。
「良いっていうのは……?」
「別に、約束を破られたわけでもないんですから、心配する事はないんじゃないですか? 今まで偶々居た人が、今日は偶々居ない。それだけの話じゃないんですか?」
「でも……」
食器を流しに片付け終えたシャルシュは、やはり気になって仕方がないのかエリアの家の方へ視線を向ける。
そしてテーブルの上に片付けずに残してある料理をもう一度見つめて。
「やっぱり気になるんで、見てきます。片付けは帰ってきてからやるんで置いておいてください」
そう言って、パタパタと足音を立てて出て行ってしまった。
その背中を見送って、アリアは溜息をつく。
そこまで気になるのだろうか。
「珍しいな、お前がそんな風に感情を露わにするのは」
ジグがそんなことを言ってくる。その言葉に少しかちんとなって、言い返す。
「別に、珍しいというほどのことじゃありません」
「ん、ああそうだな。例えば体型のことを言われた時、とかな」
「もう、兄様! さっきから何が言いたいんですか!」
「いや、別に。ただ、本当に、お前がそんな風に他人を気に掛けてるのが珍しいって思っただけだよ」
気に掛けている?
自分が?
シャルシュを?
そうなのだろうか。
「私は、シャルシュがエリアさんのことを気にしすぎて手の動きが止まっていたから、少し声を掛けただけです」
「そうか? なら、別に良いんだけどな」
別に他意があるわけではない。
大体、少しシャルシュのことを意識してしまっているというのなら、それはきっと昼間にシラムたちに言われたことが原因だ。
宿と食事の恩があるのだから、あんな事を言われてしまえば気に掛けないわけにも行かない。
ただ、それだけの話だ。
「そんなことより、兄様の方の調べはどうだったんですか?」
自分から話題をそらす意味も込めて、アリアは食卓では一切語られなかった今日のジグの成果を訊ねた。
ジグが不意に真面目な顔になり、辺りを一瞥する。
「兄様?」
「いや、まあ誰かに聞かれて困ると言うほどでもないんだが……、敢えて聞かす話でもないんでな」
「と言うことは、例のことについて何かわかったんですか?」
声を潜めるジグに合わせて、アリアも声のトーンを落とす。
「いや、よく分からない、と言うことが分かっただけだ」
「はい?」
「つまり、この仕事は長引きそうって事だ。今日、例の祠まで行ってきたんだが、どうにも掛けられている術が話に聞いていたのと違うみたいなんだよな」
顔をしかめながらジグの語る内容は十二分に驚くに値するものだった。
「そんな……。一体どうして?」
「分からない。誰かが故意に変えたのか、それとも偶々いつかに起きてしまった事故で術式に改変が加えられたのか。ただ、今掛けられている術そのものには悪意のようなものは感じられなかった」
「どういう意味ですか?」
兄の言っていることの意味が掴めずに、訊ねる。
「そもそも、何かを意図的に起こそう、って感じの術構成じゃなかったんだよ。ウチに伝わってた術よりもより効率の良い魔力運用をしていたから、単なる改良版って言っても良いくらいだ」
「でも、落ち度があったから、私たちはここに来ている。そうですよね、兄様」
「ああ、そうだ」
アリアの言葉にジグが神妙な顔で頷く。だが、すぐに言葉を選びながらこう続けた。
「だが、その落ち度は、俺には偶然出来ただけのものにしか見えなかったんだ。術者の見落とし、というか、とにかく術者がそうなるように構成したような気配は無かった」
「それは、これから調べてみないと分かりません。感情論で推測するなんて、らしくないのは私じゃなくて兄様の方じゃないですか」
「おっと、こいつは一本とられたな」
おどけたようにそう返す兄を見ながら、アリアは考える。
読めない。
何が起きているのか。
何が起ころうとしているのか。
そして、ここにいる自分たちが何をすべきなのか。
自分たちの演じる役割が、一体何であるのか。
何を判断するにしても、今はまだまだ情報が足りていない。
「いずれにしても、暫くは様子を見ながら情報収集だ。周りに注意を払いつつどうにか調査していくしかないだろうよ」
「……村の、エルフたちに協力を請うというのは駄目でしょうか?」
ふっと思いつきが口をついて出た。言ってすぐに、自分でも何故そんな言葉が出てきたのか分からなくなるような思いつき。
その言葉に、ジグは今までにも増して驚きを露わにした表情を見せる。
「驚いたな。本当に、どうしたんだ、アリア。確かに、正直に事情を話して協力を請えば効率よく調べられるだろうけれど……、アリアはエルフ嫌いな方じゃなかったか?」
「あ、いえ、そうなんですけれど……、でも個人の感情より優先させるべき事があるように思いまして」
それは方便に過ぎない。
確かに、昨日までのアリアならこんな事は考えもしなかっただろう。エルフなんて頼る相手ではない、と頭から決めて掛かって、一切信用することはなかっただろう。
だが、今は違う。今日、シラムたちからシャルシュの話を聞いて、彼らの人となりを知って、彼らなら協力して貰えるのではないかと、そう思い始めていた。
今までの自分にはなかった考え。その可能性に期待を膨らませていたアリアに、しかしジグの反応は素気ないものだった。
「話としては分かる。だが、暫くはやるべきじゃないだろうな」
「どうしてですか?」
「まだ、情報が足りていない。この村の中で誰を信用すべきで、誰は信用出来ないのか。判断が付くまでは、あまりこの村の者に頼ることはできない」
ジグが冷静に言葉を紡ぐ。
それは、つまりこの村の誰かを疑っている、ということか。
「可能性の問題だよ。別に誰か特定の人物を疑っているわけじゃない。そして、特定の人物を信用しているわけでもない。適当に探りを入れながらやっていくしかないだろうよ」
「そう、ですね」
自分の中で、急速に気持ちが冷めていくのを感じる。
一体、今自分は何に高揚感を感じていたのか。シラムやリーネと少し話をしただけで、もう裏切られることのない仲間になったつもりで居たとでも言うつもりか。
彼らの人柄が決して悪くないというのは確かだろう。だが、まだそこまで気を許すのは性急に過ぎるというものだ。
「そうですね。私がどうかしていたみたいです。済みません、忘れてください。それで、これからの活動方針はどうするんですか?」
「ん、お前はシャルに修行を付けつつ、村の中を調査。あとは《あちら側》に対する警戒も怠らないこと。俺は祠の術式を調べながら、この辺りの魔力の脈に何が起きてるのかを調べる」
「それで……、大丈夫なんですか?」
アリアの心配は、そんな風にのんびりしていて大丈夫なのかということだ。
もし今回の出来事の影で動いている人間が居るのなら、こちらがもたもたと調査を進めている間に先手を打たれる心配は無いのか。
「そりゃ、大丈夫だろう。俺の勘だが、黒幕は多分秋までは動かない」
「え?」
「ま、向こうが待ってくれるって言うんなら、こっちも遠慮することはない。どっしりじっくり行こうぜ。じゃ、俺は寝るわ。いやー、今日も疲れた疲れた」
「ちょ、ちょっと待ってください兄様」
アリアの言葉を聞き流し、ジグは扉を開けて寝室へと姿を消した。
あの様子では、もう今晩はまともに取り合ってくれる気配は無さそうだ。
それにしても、秋までは動かない、というのはどういう事なのか。自分の兄だからと言って過大評価をするつもりもなければ、過小評価をするつもりもない。ジグ・ムーシカは根拠のないことは言わない人間である。その兄が言ったことなのだから、きっと何かの理由があるはずだ。
そんなことを考えていたら、リビングのドアが開いた。
「……あれ、アリアさん、まだ居たんですか?」
扉の向こうから顔を覗かせたシャルシュが、意外そうな表情を見せた。
「もう寝てるかと思っていました?」
「はい。随分時間も掛かっちゃいましたしね」
シャルシュが壁際に掛かった時計に目をやる。長針は先ほどシャルシュが出て行った時から半周ほど回っている。確かに、アリアとジグの二人が話し込んでいた時間は決して短くはなかった。隣家に人を呼びに言ったにしては長すぎたくらいだ。
「隣へ行って帰ってきた、だけにしては遅すぎる気がしますが、何かあったんですか?」
「あー、その、どうにも人の気配がなかったんで、村の中を少し探して歩いていたんです」
「その表情を見ると、無駄足だったようですね」
アリアの言葉に、シャルシュは情けない表情で苦笑いを浮かべる。
「あはは、分かります?」
彼に鏡を見せてやりたいと思った。そんな力ない表情を浮かべていれば、誰にだって分かるというものだ。
「どなたか、知り合いの家にでも泊まって居るんじゃないですか? 訪ねてみました?」
「いや、それは……」
シャルシュが言葉を濁す。その反応で分かってしまった。自分の村の中に人捜しに行っておきながら、彼は誰にも尋ね人の居場所を訊かなかったのだ。ただ、一人で捜していただけ。それは、暗闇の中で光を捜して歩き続けるような、なんと孤独な人捜しなのだろうか。
昼間にシラムが言っていた言葉が脳裏を過ぎる。
――アイツは自分から独りになろうとしている。
彼の言っていたことは誇張でも冗談でも何でもない、掛け値無しの真実であるらしい。
全く、世話の掛かる生徒を持ったものだ。騎士たる者、教育をなすなら徹底的に。どうやら自分は彼の根性もたたき直してあげなければならないらしい。
アリアは洗い物を始めた生徒の姿を見て、小さく溜息をついた。
to be continued
WEB版あとがき
どうも、yoshikemことよしけむです。
名称未定公式サイトに作品をアップするのはこれで10本目です。ついに2桁の大台に!
というわけで、Monochronikaの第4回でした。前回から、ぼちぼちお話は転がり始めていますね。
これで舞台設定も整ったというところでしょうか。整っているんですかね。いや、結構怪しいです。すみません。
2でようやく人物が出そろい、3は舞台をならし、4では色々なところに突っ込んでいこうかという感じですね。
シャルシュの抱える闇、シラムの背負った責任、そしてジグとアリアのミッション。
いくつもの線が絡み合い、一枚の布を織りなす……、ことになればいいのですが、果たしてどうなる事やら。
シャルシュの抱える孤独に触れつつ、暫くはシラムとアリアのお子ちゃま二人で物語を紡いで行けたらなぁ、って思っています。二人とも思った通りに踊ってくれるんですもん。
さて、次回は本筋の流れとは少し離れた短編になります。
その次辺りからはMonochronikaの前身となったエリアさんの冒険の話をUPしていきたいと思っています。
正直一回生の時の原稿を洗い出すのは怖いんですが、改稿改題でこの場に引きずり出せれば幸い。
それでは、今回はこの辺りで。
yoshikemでした!
作品展示室トップへ
総合トップへ