夢を視た。
誰かが泣いている夢だった。
頭から布団を被って、がたがたと震えている。
真っ暗な夜の中、真っ昏な闇の中。
たった一人で布団を被って、全てのものから逃げ隠れるかのように一人でがたがたと震えている。
何を震えているのか、疑問に思って訊ねてみた。
朝が来るのが恐いと、幼い声が答えた。
痛切な声。その年に不相応な、どうしようもないほどに痛切な声だった。
何故だろうか、不思議に思う。
だって、朝はこんなにも明るくて、希望に満ちているというのに。
ほら、ごらん、夜が明ける。
白く染まっていく視界に――
――意識が覚醒していく。
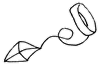
朝の空気に目がさめた。
真っ白に染まった視界が徐々に像を結び、今日の一枚目の風景が飛び込んでくる。
アリア・ムーシカの一日はいつもこうやって始まる。
ふかふかのベッドから体を起こし、部屋の中を見回す。
一瞬、いつもの自分の部屋と異なる風景に驚いたが、すぐに思い出した。
そうだ、自分は今エルフの村にいるのだ、と。そこで出会ったエルフの青年の家に泊めて貰っているのだと言うことを。
昨日は森の中を延々と歩き続けて漸く目的地の一つであるハルヨビの村へたどり着いたかと思ったら、何故かエルフの森林警備隊員に喧嘩をふっかけられ戦闘、さらには魔獣までもが現れてめまぐるしい一日だった。
だからといって疲れたなどとは言っていられない。一晩ぐっすりと眠って疲れもとれ、十分な睡眠を取った頭はこの上なくスッキリとしている。
今日やるべきことは、まずこの村を取り巻く現状の確認。協会から受けている任務を完了させる為に一歩一歩着実に情報を集めていかなければならない。
それから、アリアにはどうにも寄り道に思えて仕方がないのだけれども、ここの家主でもあるあの少年に対して成り行き上、魔術の指導をしなければならなくなった。確かに啓蒙は騎士たる自分たちの務めだ。それについてはアリアとて異存はない。だが、状況によってもっと優先されるべきものごとは沢山あるはずだ。
兄の言うことは正しい。彼がこのままの状態で魔術を使い続けるのなら、それは魔導学的見地から見れば非常に危険なことで、いつ事故が起きたっておかしくない。むしろ今までなんの大事件もなく魔術を行使し続けてこられたことこそ、サイコロで六を出し続けるような奇跡的な確率の上に成り立っていると言っていい。
だが、それでも任務中であると言うことを無視するかのようにああも平然と彼の指導を買って出る兄の真意を、アリアは測りかねていた。
「……引き受けた以上は、これ以上考えても詮無いことですけども……」
そう。昨夜兄の言葉に頷いてしまった以上、騎士に二言はないのだ。
無いのだが、心のどこかに納得しきれていない自分がいることを、アリアは否定することが出来なかった。
自分らしくもない。
「多分、私らしくないことをさせられるからなんでしょうね。ええ、兄様が全部悪い」
そんなことを呟きながら、昨晩寝る前に出しておいた着替えをベッドの上に広げる。
いつもと代わり映えのしない、華美に走らず機能性を徹底的に高めた協会魔導騎士の制服。
完全形で身に纏えばプレートメイルから鉄靴、ヘルム迄完全装備となるものだが、戦時ならともかくそんな重武装を普段から用いる者など協会本部にもまずもっていない。普段は多くの者が今アリアが広げているアンダースーツの上から革製の胸当てや手甲などの軽装備をつけるに留まるだけで、アリアもその例に漏れない。
日常生活においてなら更にその軽装備が外れ、アンダースーツのみとなる。アンダースーツには多くの魔術師にとって使いやすい機能が備わっている為、それに満足している者も多い。自然と協会の魔導騎士たちの普段着は、このアンダースーツになっている場合が多い。
というわけで今日もいつも通り、代わり映えしないアンダースーツに着替えようとしているのだが。
利便性の面において協会魔導士たちの希望を満足して止まないこのアンダースーツ、強いてあげるなら一点だけ問題点がある。
それも女の子であるアリアにとっては、割と切実な悩みだ。
デザインが一つだけ、それもあまり可愛いとは言えない。これはおしゃれしたい年頃の女の子にとっては、拷問のようなものだ。
ならばアンダースーツを着なければいい、と簡単に言う者もいるかも知れないが、この服に備えられた様々な仕掛けはデメリットを補ってあまりあるのだ。
だから、合理的選択をした場合に、アリアには服の選択肢は一つしかない。
まあ。
別に。
誰に見せるわけでもないから構わないのだが。
「……はあ……」
半年に一度くらい頭を過ぎる、このジレンマ。
何度考えたって、自分がこういう性格に育ってしまった以上はこの服を着るしかないのだ。
アリアは溜息をついて頭を振ると、着ている寝間着のボタンに手を掛けた。
シャルシュが昨晩用意してくれたこの寝間着、腹が立つことにアリアにとっては随分とぶかぶかであり袖と足下を何度か折り返してどうにかまともに行動できるようになった。そんなに大きいサイズであるくせに不思議と腰のサイズは同じくらいなものだからズボンがずり落ちることもないし、極めつけに胸元はゆとりたっぷりでここまで来るといっそ心地よい。
彼がどこから出してきたのかは知らないが、知っていてやったのだとしたらそうとう嫌味の才能があると言っても良い。
と、そんなことを考えてしまうのもどうにも自分らしくなくて、アリアはもう一度頭を振る。
ぶかぶかの寝間着を脱ぎ捨てて、いつもの服に袖を通そう。
そうすれば、きっといつも通りの自分が始まるから。
そう思って上着のボタンを外し終えた時。
「アリアー、起きてるかー?」
ノックとともに扉の向こうから聞こえる兄の声。
「あ、兄様、ちょっとま」
がちゃり
返事の声を聴く意志が一切感じられないタイミングでノブが回され、扉が開く。
開いた隙間から現れる兄の顔が、驚きの表情で固まる。
勿論その視線の先にあるのはこれでもかと言わんばかりに前をはだけられたアリアの姿であり。
「……に……、」
「えーとだな、その、おはよう、アリア。飯が出来てるらしいからシャルが呼んでるぞ。うん、それだけ。起きてるならいいんだ。それがちょっと心配だったもんだからな」
自分の怒りの沸点がこんなに低いとは思わなかった。
アリアはへらへらと言い訳を並べ立てる兄を睨み付ける。
「……兄様の、馬鹿ー!」

「えっと……、どうしたんですか、二人とも?」
無言のまま頬を膨らませて怒りを全身から発しているアリア・ムーシカと、右頬を腫らして困ったような表情で苦笑いを浮かべる兄のジグ・ムーシカを交互に見比べて、シャルシュ・ワイゼンは首を傾げて訊ねた。
アリアの方は昨夜シャルシュに対して見せていたのの比でないくらいに怒りを露わにしている為、眺めるだけでもなんだか恐い。やむなく視線はジグの方へと泳いでいく。
そんなシャルシュの不安そうな視線に気付いたのだろう。ジグは困ったように腫れていない左側の頬をぽりぽりと掻きながら、肩をすくめる。
「あー、まあ気にせんでくれ。アリアがかんしゃくを起こしてぶたれてな……。よくあることだから」
その一言に、明らかに頬をひくつかせてこめかみに青筋を浮かべるアリア。
「兄様、右の頬をぶたれたら左の頬も差し出せ、って言う言葉をご存じですか?」
「確か辺境のマイナーな神様の言葉だったっけ? わざわざ反対側のほっぺたまで叩かせてやるなんて、よっぽど人が良いんだろうな。俺には無理だ」
「因みに私の故郷の神様は、右の頬をぶったらついでに左の頬もぶっとけ、というありがたい言葉を下さったのですけれども」
そんなことを言いながら、爽やかな笑顔で右手を握ったり開いたり、指の関節の柔軟運動まで始めるアリア。
「待て待て待て待て。お前の故郷ってことは俺の故郷でもあるはずだが、俺は断じて決して間違いなくそんな暴力的な神様は知らないぞ。お前、どこの怪しげな宗教に引っかかってそんな暴力的になったんだ? まったく、お兄ちゃんは悲しい」
「大丈夫ですよ。その神様の言葉は相手が兄様の時だけ有効ですから。と言うわけで、両頬とも腫れ上がるまでぶたれて喋れなくなるのがお嫌でしたら、今すぐさっきの言葉を訂正してください」
「訂正って……、ぶたれたがりの神様がマイナーだってことか? そうは言っても……、」
「そちらではなく、私がかんしゃくを起こしただの、それが良くあることだの、兄様が先ほど発したシャルに誤解を与えるような言葉の方です」
「誤解……。どこが?」
本当に、心底見当がつかないという表情で首を傾げるジグ。
その仕草にアリアのこめかみに浮かび上がっていた青筋が何本か増える。
「……兄様、冗談はほどほどにしないと面白くないですよ。さっきのことは全面的に兄様が悪いんです。いきなり私の着替えている最中に入ってくるんですから」
「はい、ごめんなさい。すいませんでした。もうしません」
どう考えても申し開きようのない決定的な証言に、流石のジグも諦めたように両手を挙げる。
はあ、と小さく溜息をつきながら素直に頭を下げた。
「分かれば良いんです。ノックは人類最大の発明品って言う言葉もあるくらいですが、すぐにドアを開けてたら意味が無いことくらい、わかるでしょう?」
そう、困ったように頬を膨らませるアリア。
ジグとしてはそんな妹の仕草がなんとなく可愛く思えるのだが、そんなのを顔に出せば何を言われるか分かったものでもないしじっと殊勝な顔で頭を下げる。
そんな二人の様子を見ながら、呆然と息を吐くシャルシュ。
「……まあ、大体分かりました」
やや自信なさげなその呟きに、アリアはほっと胸をなで下ろす。
「よかったです、分かって貰えて」
「ええ、その頬はどうやら一方的にジグさんが悪いことをした結果らしいと言うことと、あとアリアさんを怒らせちゃ駄目だって言うことは」
「後半は余計ですけどね」
苦笑いしながらシャルシュの言葉に頷くアリア。
そんな彼女のお腹が不意に。
ぐー。
小さな、耳を澄ましていなければ聞き逃してしまうようなとても小さな音をたてた。
自分のことだ。当然アリアがその音が自分のお腹の音だと言うことに気付かないはずがない。
咄嗟にお腹に手をやり、神速で紅潮する顔を隠す為に俯く。
今の音、気付かれてしまっただろうか。
兄に。
そして、目の前のまだ知り合ってから日の浅いエルフの青年に。
騎士として、何かとんでもない失態を犯してしまったような気分でちらりと隣に座る兄のことを伺う。
まだ先ほど謝った態度のままで、こちらの方を申し訳なさそうに見てはいるが、どうやら気付いている様子はない。
ほっとしつつも、今度は正面で先ほどから朝食の用意をしているシャルシュを見る。
ふと、彼と目が合ってしまった。
白金の髪を揺らして、エルフの青年はニコリと微笑む。
「朝から楽しいのは良いですけど、お腹もすいたことですからご飯にしましょうか」
そう言って、ハムと目玉焼き、それからサラダの載った皿をこちらへ差しだしてくる。
気付いているのか、いないのか。それが気になりながら、アリアはおずおずとシャルシュの差しだした皿を受け取る。
手渡す一瞬、シャルシュがアリアにだけ分かるようにウインクをした、ような気がした。
目玉焼きにハムとサラダを添えたおかずに、メインディッシュはきつね色にいい焼き色を見せているフレンチトースト。
一人暮らしで鍛えられたシャルシュの料理の腕は、朝食から比較的手間暇を掛けた献立になっていた。
「男の一人暮らしでこれだけ作るってのも、珍しいな」
目玉焼きの黄身をつつき、中からとろりと流れ出てくる半熟の黄身を白身に絡めて口へ運びながら、ジグは感心したように呟いた。
「お客さんがいるっていうのは珍しいんで、ちょっと気合いが入ったんですよ。いつもはこんなの作りませんよ」
そう言いながら、シャルシュはフレンチトーストを一切れくわえる。
思っていた以上に出来が良かったのか、一瞬満足げな笑みを浮かべると柔らかな口当たりのパンを咀嚼する。
「ま、何にせよこうやって朝から旨いものをごちそうになってるんだ。恩返ししないわけにはいかないよな、アリア」
「そのことは分かっていますから、混ぜっ返さなくても結構です、兄様」
「へいへい。じゃあ、そっちはよろしく頼むぜ、頼りになる妹さん」
そう茶化す兄をじろりと睨むように一瞥し、アリアはむすっと口を尖らせる。
「兄様こそ、私がいない分も綿密に調査を進めてくださいね」
「言われなくても判ってるっての。俺を誰だと思ってるんだ?」
「魔獣を一撃で仕留められない程度に頼れる、私の兄様です」
ツンとそっぽを向いてそう言い放つアリアの様子を見て、ジグは苦笑を浮かべる。
「こいつは手痛いな」
「事実ですから」
「違いない」
全くもって、仲の良い兄妹だ。
二人のやりとりを見て、シャルシュは自然と口元がほころぶのを感じていた。
互いに攻撃的な言葉は口にしているものの、相手がきちんと冗談として受け止めてくれるという確信を持っている。要するにこれは二人でじゃれ合っているだけなのだ。
両親もなくし、兄妹もいない。シャルシュにはそう言うじゃれあいをすることが出来る相手がいない。
だから、本当のことを言えばアリアたちのように気兼ねなく軽口をたたき合える仲が羨ましかった。
そんな感情が表情に出ていたのかも知れない。
「ほら、兄様、シャルが呆れてますよ」
「おっと、悪い悪い。まあ見ての通りの妹なんでな」
「そのセリフ、そっくりそのままお返しします」
などと、やっぱり二人の軽口は止まない。
願わくば、自分も彼らとこういう風に軽口をたたける仲になりたいと、シャルはそんなことを思った。
「そう言えばシャル、お前、朝どこに行ってたんだ?」
ふと思い出したようにジグが問いかけてきた。
「朝?」
アリアは何の話をしているのか、と首を傾げて兄の方を見る。
一方で訪ねられた本人であるシャルシュは、少し驚いた表情を見せていた。
「ひょっとして、起こしちゃいましたか?」
朝方、確かにシャルシュは出かけていた。が、朝方と言ってもまだ夜明け前の真っ暗な時間帯のことだったし、眠っているジグたちを起こしてはいけないと細心の注意を払って物音を立てないようにしていたつもりだ。
「いや、そう言うわけじゃないんだ。ただ、そう言うのにはそれなりに気づけるように訓練してるからな、騎士って奴は。なあ、アリア?」
「え……、っと、私は……」
急に水を向けられたアリアは、困ったように俯いて言葉を濁す。
まさか気づいていなかったと堂々と言うわけにもいかない。のだが、わざわざ口にするまでもなく、その態度が既に全身で語っているも同然だった。
「まあ、半分冗談だけどな。俺は割とそう言うのに敏感だから、どうしても気付いちゃうんだよ。アリアが気付かなかったってことは、充分こっそり出かけてたことになると思うぞ」
「はあ……、そうですか」
「それで、どこに行ってたんだよ、あんな時間に?」
薄闇が晴れていく、明け方の時間。
何か特別な用事でもなければわざわざ外へ出かけようなんて人はいないだろう。
好奇心に充ち満ちたジグの視線を受けて、シャルシュは一瞬躊躇うような表情を見せた後小さく溜息をついて答えた。
「笑わないでくださいよ」
「笑うかよ」
興味は隠すことなく、しかし真面目な表情でこくりとジグが頷く。隣でついでにといった風にアリアも頷いた。
「じゃあ、言いますけど……。朝を確かめに行ってたんです。この村で、一番日の出が早い丘の上まで」
「朝を、確かめに?」
首を傾げるジグの表情は不思議そうなもの。
それを見て、シャルシュは変わらぬ真面目な表情で続けた。
「はい。日課みたいなものなんです。毎日、日の出を確かめに行って、今日も新しい一日が始まっちゃうんだなっていうのを確認する。これをやらないとどうも落ち着かないんですよね」
そう言って、あはは、と苦笑を漏らすシャルシュ。
照れ隠しか、頭をくしゃくしゃと掻いた。
「趣味は人それぞれだから特に何も言わないけど、なかなか変わった日課だな」
「そうですか? 朝の散歩と思えばそうでもないと思いますけど」
「いや、早すぎるだろ、普通に考えて」
呆れた様に言うジグに、シャルシュは「やっぱり、そうですよね」とあっさりと頷いた。
「んで、今日も朝はちゃんと来たのか?」
「ええ、ご覧の通りに」
春の柔らかな日差しが差し込んでくる窓を見やり、シャルシュは苦笑を浮かべながら小さく肩をすくめる。
何故だろうか、ジグにはその様子が一瞬辛そうなものに見えた。何か痛みに耐えるような、望ましくない状況に巡り会ってしまったかのような、そんな痛切な表情に見えたのだ。
「シャル……、お前……」
「はい、なんですか?」
だが、そんな錯覚じみた感覚も一瞬。思わず呟いた声に返答するシャルシュの顔には先ほどまでと何ら変わらない笑顔が浮かんでおり、痛切さなど微塵も覗かない。
恐らく見間違いだったのだろう。そう結論づけて、ジグは
「なんでもねえよ。ところで、このフレンチトースト旨いな」
「はい、僕としても今朝のは会心の出来です」
沢山あるからどんどん食べてください、とフレンチトーストが山と盛られた皿を差し出すシャルシュの浮かべている笑顔はとても幸せそうなもので、とてもではないが先ほど一瞬見えたような気がした痛切な表情や、或いは昨夜彼がちらりと語ったエルフとしての特異な状態とは無縁に見えた。つまり、どこにでもいそうな、幸せなごくごく普通のいちエルフ。
だと言うのに、既に両親は他界しておりこの広い家にずっと一人暮らし。くわえて、昨日のシラムたちの態度から推察するにどうやらこの村の中でも孤立しているらしい。
まだ出会ってから一晩しかたっていないが、ジグには断言できる。シャルシュの人柄は間違いなく良い。そんな彼が置かれている状況を考えると、どうにもやるせなかった。
そんな内心の苦痛を押し殺して笑顔を浮かべ、シャルの差しだした皿を受け取る。
両手にずしりと重みを感じるほどのパン。その量が、今更ながらとてもではないが三人分ではすまない量であることに気付き、苦笑を浮かべる。
「いくら何でも多すぎないか? 俺はともかくアリアはそんなに食べる方じゃないし」
「ああ、これはですね、その内分かりますよ」
一瞬キョトンとしたような表情になったシャルシュが笑顔でそう言った時だった。
ばたん、と。
玄関の扉が開く音がした。
こんな朝早くから客人か、とジグとアリアは不思議そうな視線をシャルシュの方へ向けるのだが、シャルシュは何の疑問も抱かない表情で居間の扉の方を見ている。
玄関へと続く廊下への扉のノブが、かちゃりと音をたてて回った。
「ふあああ、おはよー、シャル……。なんか食べるもんある?」
盛大なあくびの後に、眠気を隠そうともしない舌足らずな声。ぼさぼさの髪の毛には所々木の葉のかけらなどもついており、白銀の色がどことなくくすんで見える。
部屋へ入ってくるなり挨拶もそこそこに身につけていた防具を外すと部屋の隅に置き、至極当然そうな顔をしてテーブルの空いた席に座ったのは、エリア――エリアネル・テルミチェットであった。
「ふむふむ。今朝はフレンチトーストなのね。いっただっきまーす」
そう言って手を合わせると、阿吽の呼吸でシャルシュが差しだしたフォークを手に取り、パンの山を崩しにかかる。
幸せそうな表情でフレンチトーストを口に運ぶエリアと、そんな彼女にすっとサラダとハムエッグの皿を差し出すシャルシュ。まるでどこかのお嬢様と執事のような二人の様子をぽかんとした表情でジグとアリアが見つめる。
我慢できずに口を開いたのは、予想通りといえばその通りだが、やはりジグだった。
「……えっと、どういうこと?」
「エリアさんが正気を取り戻す前に説明しておいた方が楽そうですね」
そう呟きながら苦笑して食に興じるエリアの様子を見るシャルシュ。
小さく肩をすくめると、自らもまた席について二人の方を見てしゃべり出した。
「この人はエリアネル・テルミチェットさんという人で、率直に言うとうちのお隣さんです。それから、僕の保護者みたいな人で、あと説明するなら……、森林警備隊に所属していて、自称最強レンジャー、だったかな」
「はあ……、自称、ですか」
シャルシュの言葉を受け、アリアはエリアに胡乱げな視線を向ける。
誰がどう見ても、その目はエリアの実力を疑っている者の目だった。
無理もない。昨日のシラムやオーウェルのような人たちならともかく、こんな風に目の前で周りの状況にも気を配らずにパンをひたすらもきゅもきゅと口に入れては咀嚼し続ける物体が最強を名乗るというのなら、【森の翼】もたかが知れるというものだ。
そんなアリアの考えが読めたのだろう。シャルシュはふぅと小さな溜息をついて言った。
「いや、いまはこんなですけど、エリアさんは本当は凄い人ですよ。そこだけは保証します」
「そう、なんですか?」
わざわざそんなことに嘘をつく意味もないだろう。となればシャルシュの言っていることは本当で、エリアは本当に腕利きなのかもしれない。
第一印象とその実が食い違うことなど往々にしてあることで、まさにその卑近な例を身近に知っている身としては、ことさらにシャルシュの言葉を疑う理由もない。
アリアは納得の頷きを返すと、改めてエリアの方を見た。
なるほど、落ち着いて見てみれば、最強を名乗れるだけのキャパシティは備えているのかも知れない。腰まで伸ばされた彼女の髪の毛は、
が、そんなことよりも何よりも驚くべきことには。
「……あれ、フレンチトースト……?」
気がつけば、皿の上に山と盛られていたはずのパンが一切れたりとも残さずに消え去っていた。
ふと隣を見てみればジグは自分の皿に何切れかをキープしている。シャルシュも動揺に数切れキープをしているが、この卓上に他のパンは一切見あたらない。
ということは、どういうことだろうか。
目の前で笑顔でハムエッグを咀嚼する彼女が食べたと言うことだろうか。
まさか。
あの量を。
こんなわずかな間に?
「なるほどな。量が多かったのはこういうことか」
「はい。エリアさんがウチに朝ご飯を食べに来るのはいつものことなんで」
納得したように頷きながらエリアのことをあきれ顔で見るジグに、シャルシュが苦笑いを浮かべて答えている。
いや、この事態はそんな風にあっさりと受け容れて良いものなのだろうか。
特に女性として。
日頃から体型や体重に気を遣っているアリアとしては、今のエリアの食べっぷりは断じて流して良いものとは思えないのだが……。
「ふぅ……、ごちそうさま。今日も美味しかったわ、シャル。……それで、この人たちは誰?」
先ほどまでの朗らかな表情は冗談のように消え去り、なんだか怪しい者でも見るような視線で品定めするかのごとくアリアとジグを見つめるエリア。
確かにシャルシュの保護者のような立場にあるなら、アリアたちの素性を訊ねるのは当然のことかもしれないが、それにしてもあまりにも疑いの意志が露骨すぎる。
エリアの視線にムッとなりつつ、にらみ返す。二人の視線が空中で見えない火花を散らす。
何故か対立の空気を全開で発している二人のことを不安そうに見つめ、シャルシュが恐る恐る口を開く。
「……あの、エリアさん? この二人は……」
「まあまあまあまあ、お姉さん、そんな顔をしてると折角の美人が台無しですよ」
底抜けに明るい声で割って入ったのは、ジグだった。
シャルシュは勿論、険悪な雰囲気だったエリアたちもぽかんとした表情でジグの方を見つめる。
いつの間にか立ち上がっていたジグは、つつーっと驚くべきスムーズさで机を回り込んでエリアの元まで行き、跪くとその手を取る。
「ヘクセン魔導協会所属特務魔導騎士のジグ・ムーシカと申します。以後お見知りおきを」
そう言って気障ったらしく手の甲に口づけをする。
ジグの様子を呆れながら眺めていたエリアは顔を上げて目線があった彼に目掛けてぽつりとひと言。
「あんた、馬鹿でしょ」
「心外な。ただ、美しい女性には礼儀を弁える。それが俺の騎士道なのでね」
明らかに先ほどシャルシュと喋っていた時とは異なる態度に、見ている方が恥ずかしくなってくる。
が、エリアはそんなことは斟酌しなかったらしい。
「人間……、ねえ。見たところ、旅の人間にシャルの方から宿の提供を申し出たってと頃かしら? シャルらしいって言えば、シャルらしいけど……」
恐るべき洞察力でもってそう言って、シャルシュの方へ責めるような視線をちらりと投げかける。
「まあ良いわ。そんな馬鹿らしい態度とられたら、色々問い詰める気も無くなったし。それで、あんたたち、わざわざこんな所まで何しに来たのよ?」
「それは勿論、貴女に会うた」
「あ、お嬢ちゃん、お願いできる」
無駄にかしこまって声高らかに謳い上げようとするジグの言葉を途中で遮って、エリアはアリアの方へ水を向ける。
兄のことをあきれ顔で見ていたアリアは、一瞬弾かれたように表情を改めると、すぐに真面目な顔でエリアのことを見つめる。
図らずも先ほどの構図を再現することとなったわけだが、
「お嬢ちゃんとは私のことですか?」
「ええ、そのつもりだけど」
「申し遅れましたが、私はヘクセン魔導協会所属魔導騎士アリア・ムーシカです。名乗った以上はもうお嬢ちゃんなどという呼び方はやめて頂きたいものですが」
「出来る限り努力するようにするわ、お嬢ちゃん」
険悪な雰囲気は相変わらずのようだった。
妖艶さすら漂う視線でアリアの方を流し見る視線は、オブラートに包んだ敵意を確実に孕んでいた。
「……はあ、まあ、そうなりますか、やはり」
友好的な態度からはほど遠い彼女の態度に、アリアは溜息をつく。
そんなアリアの様子を見てニヤリと口元をつり上げるエリアだったが、その笑みは次の瞬間凍り付くこととなる。
「エルフとまともな会話をしよう、という発想が間違っていたみたいですね」
ぴしり、と音をたてて空気がひび割れるような錯覚。
シャルシュは知らないだろうが、今ここでふくれあがっていく怒気の規模は昨日のシラムのそれを遙かに上回っていた。
まるで目に見えて陽炎が燃え立つかのように、エリアが怒りを沸き立たせているのが分かる。
「ほお、それは何かな? 私たちには言葉が通じないと、そう言いたいのかな、お嬢ちゃん?」
「そう言ったつもりでしたけれど、一度で通じないと言うことはやっぱり間違いないみたいですね。そんな人とまともに会話しようとした私が悪かったんです、本当にすいません」
そう言って頭を下げるアリアの態度が、決して嫌味さを感じさせず酷く真摯なものだからまたたちが悪い。
まさに一触即発の空気が膨らんでいく様子を、ジグはあきれ顔で見つめる。
「……全く、また悪い癖が出てやがる……」
アリアがエルフに対して突っかかりがちになるのは今に始まったことではない。
ジグにとってはこうやってもめ事になりそうな場面に出くわすのは慣れたものだったが、シャルシュにとってはそうは行かない。
自分にとって親しい人と大切な客人、その二人が険悪な雰囲気でにらみ合っているなど、とても黙って見過ごせるものではなかった。
「ああ、もう! 二人とも、喧嘩はやめてください!」
エリアの肩を掴んで椅子ごと強引に後ろへ下がらせ、テーブル越しににらみ合っていた二人の間に割って入る。
そんなシャルシュを不満げに睨み付けるエリアと、詰まらなそうに見つめるアリア。二人の視線を浴びてへこたれてしまいそうになるのをどうにか抑え、大きく息を吸うとシャルシュは言った。
「ここで喧嘩をするって言うならこっちも家主としての強権を発動しますからね。今すぐ、出て行って貰いますから。ついでにエリアさんはもうご飯をごちそうしません」
思い切り胸を張って、外面だけは堂々と宣言する。
何とか声を裏返らさずにすんだ。
「うっ……、それは……」
「……えっと、そうなるとちょっと困りますね」
左と右、それぞれ怯んだような声があがる。
それに小さく溜息をついた。
「なら、喧嘩はやめてください。人間とエルフが喧嘩したって良いことなんか一つもないんですから」
ほっとしたような、どこか悲しそうな、そんな口調でシャルシュは言う。
エリアが「降参降参」と両手を挙げておどける一方で、アリアは申し訳なさそうに頭を下げた。
「いえ、分かって貰えれば良いんです。……ところで、僕もアリアさんたちがこの村にやってきた理由を知らないんですけれども……、聞いても良いものだったら教えて貰えませんか?」
ひとまず落ち着いたらしい二人の様子を見やりながら、シャルシュはそう訊ねた。
ジグとアリアは一瞬顔を見合わせ、ジグが頬を掻きながら
「んー……、まあ聞いたまんま棺桶まで持っていってくれるなら、」
「兄様、違うでしょう」
「すまん……、冗談だ。別に任務内容自体は大したことないから、協力を仰ぐ為なんかで他人に話すことに問題はない」
一瞬、アリアがジグの腕のあたりをつねったように見えたが、目の錯覚だろう。
シャルシュは興味津々に、エリアは話半分にジグの語る任務の話に耳を傾ける。
「話せばちょっと長くなるんだけどな――」
昔話をしよう。
世界には初め二人の神様がいたという。
片方は男、後に黒の神と呼ばれることとなり、もう片方は女、後に白の女神と呼ばれることとなる。
黒の神と白の女神はそれぞれに自らの力で眷属を作り、世界を賑わわせていたという。
しかし、ある時彼らが幸せに暮らしていた世界に白でも黒でもない何者かがやってきた。
その何者かは黒の神の眷属と白の神の眷属を憎んでいるかのごとくに虐殺し、世界は急速に崩壊の一途を辿っていった。
突然の事態には、当然二人の神様も頭を悩ませた。その白でも黒でもない何者かの力は強大で、二人の神様が同時にかかっても止められるかどうか怪しいほどだった。
だが、二人の神様がどうしようかと悩んでいる間にもその何者かは世界を崩壊させる勢いで眷属たちを虐殺していく。
時間ばかりが過ぎていき、そのまま世界は消えて無くなってしまう。何もない虚無が支配する世界が来ると思われた。
そんなある日、黒の神とその眷属たちがこの世界から消えた。
そして、それと同時に何者かも消えていた。
世界は平和を取り戻し、その後白の女神の眷属たちが世界中に広がり、子孫を増やし現在に至るという。
「これが、俺たち人間の間に伝わっている、世界創世の神話だ」
ジグが神妙な顔つきで一息ついた。
「
「はあ? ふざけた伝説もあったもんだな」
エリアの言葉に、ジグが呆れた表情で首を傾げた。
しかし、事実このハルヨビの村において語り継がれている世界創世の伝説はエリアの言う通り、二人の神様の痴話喧嘩によって幕を閉じる。
この世界を追い出されて《あちら側》の世界に行った黒の神とその眷属は今でも《こちら側》の世界に戻ってくる機会を狙っており、時折出てくる魔獣や、ごく希に現れる魔族はその意志の表れだといわれている。
だが、今のジグの口ぶりだと人間の認識ではどうもそうではないらしい。
「まあいいや。それで、神話は一応そこで終わってるんだが、多くの魔導士はこいつを実際にあったことだと確信している。理由は簡単だ。魔獣がいる。それが何よりもの根拠だ」
「どういうことか説明して貰えるかしら?」
「神話の結末に関して、こう解釈しているんだ。その何者か、大抵は
「ちょ、ちょっと待ってください! 魔獣って言うのは《あちら側》に追い出された黒の神の魔力が僕達の世界に染み出してきて、それにこっちの動物がやられちゃった姿じゃないんですか?」
慌てた様子でそう言うシャルシュをみてジグはほお、と感心したように溜息をつく。
「それがエルフの説か?」
「ええ、そうよ」と答えるのはエリア。
「でも、魔獣というのは虚空に突如として無から現れるモノ。シャルも昨日見たでしょう? その点を考えてみても、エルフの説より私たちの説の方が有力だと思いますけど」
アリアがそんなことを付け加える。
「ま、その辺の真相究明は専門家に任せようぜ。俺たちが額を付き合わせたってわかりっこねえよ。で、だ。一応伝承によるとだな、白の女神と黒の神が暮らしていた場所がこのあたりにある、ってことになってるんだよ」
「このあたりって……、このあたり!?」
「そう。このあたり」
エリアの驚きの表情にも、地面を指さして平然と答えるジグ。
不敵な笑みを浮かべて肩をすくめる。
「知らないってことはないだろ? 祠のこと」
そのジグの言葉にエリアの眉がびくりと動く。
それには気付かない様子で、シャルシュが何かを思い出すかのように宙に視線をさまよわせる。
祠……。なにか、ごく最近どこかで聞いたことがあるような。
「もしかして森の奥にあるっていう?」
確か、エリアが昨日そこへ行くと言っていなかったか。思い出したシャルシュが、ポンと手を叩いて会心の笑みを浮かべる。
「それだな。そいつが何かここ最近変な魔力を発してるらしくてな。その調査、それから、必要があれば何らかの魔術的処置を施す。それが俺らの任務だ」
「なら、エリアさんに訊けば多分色々わかりますよ……、って、エリアさん、何を渋い顔をしてるんですか?」
笑顔でジグにそう語るシャルシュと対象的に、エリアの顔は苦虫でも噛み潰したかのようだった。
「いや、私、そう言う面倒くさそうなの苦手だし……」
「エリアさんのそれは苦手じゃなくて嫌いって言うんだと思います」
「どっちでもいいじゃん。まあいいわ。そう言うことなら頑張ってね。とりあえず私は帰って寝るから」
「……はあ。そうですか」
面倒くささだけでそこまで元気が無くなるものなのか、先ほどまでと打って変わって精気がなくなってしまったエリアのことを不思議そうに見送り、シャルシュはお茶を一口、口にした。
冷たく冷えていたはずのお茶は、いつの間にか日差しにぬるめられていた。

高々と昇った太陽が春の柔らかな日差しを投げかけてくる。白く染まる視界の中思う存分伸びをして、シラム・リストゥーバは大きく息をついた。
自分の右手を見つめる。
手には未だに昨日の感触が残っているような気がした。
アリアに為す術もなくあしらわれた事。
現れた魔獣を取り逃してしまった事。
動揺が無かったと言えば嘘になる。たかが人間に手も足も出なかったという事実はシラムのプライドを粉々に砕くのには充分に過ぎたし、その相手がすぐ目と鼻の先で同じように魔獣を相手に戦っていたのだ。少しでも名誉を挽回しようと闘いに焦りがあった。
だが、それは飽くまで個人的な事情だ。アリアに喧嘩をふっかけたのも自分なら、勝手に負けたのも、それを引きずったのも、全てシラム自身が勝手にやった事だ。
そして、その挙げ句に魔獣を仕留め損ねて村の方へ向かわせてしまうという、村を守る者としてあってはならない失態を犯してしまった。
森林警備隊【森の翼】に身を置く者として、本当に情けない事甚だしい。
「ちくしょう」
知らず、そんな言葉が漏れていた。
昨夜自棄になって浴びるように酒を呑んだというのに、まだ鬱憤は逆巻く渦となってシラムの中で激しく波立っている。
どうにかして、あのアリアとかいう女を見返してやる。
幸いにして今日は非番である。何かいい手はないものかと、村の中をぶらぶらするのも良いかもしれない。
そんな風に思考が少し前向きになってきた時だった。
「丁度良いところにシラム発見!」
酷く聞き覚えのある声がしたかと思ったら、やたら見覚えのある彼の師匠が、その先だけが黒く染まっている特徴的な銀髪をなびかせて彼の横を駆け抜けていった。
師匠――エリアはすぐ近くにある建物の脇へと隠れてそこから顔だけをちょこんと出す。
「すぐにジグっていう人が追いかけてくるけど、私はあっちへ行ったって言うように」
それだけ言うと再び顔を引っ込める。
それと同時に、エリアが出てきた角を曲がって、シラムにとっても見覚えのある人間の魔導士がきょろきょろしながら駆けてきた。
「ん、君は確か……?」
「シラムだ。【森の翼】のシラム・リストゥーバ」
駆け寄ってきたジグに、シラムは不機嫌そうに返す。
「ああ、そうだった。シラム君だ。覚えているさ」
「そいつはどうも」
「何せ妹に派手にやられてくれちゃったからね」
笑顔でそんな余計なひと言を付け足すジグ。
途端にシラムのこめかみが引きつる。
どうにもシラムにはこれから先彼と仲良くなれる気がしなかった。
「で、アンタは朝から俺に喧嘩を売りに来たのか?」
「まさか。人を探していてね。美しい銀髪の女性なんだが……」
「エリアさんのことか?」
「よく分かったな、銀髪ってだけで」
ジグの驚きように、一瞬心臓がびくっとする。あんまり少ない情報から的確な答えを出すと、先ほどエリアに嘘をつくように頼まれた事がばれるかも知れない。いや、ひょっとしたら今のでばれたか?
内心を表に出さないように、必死で言い訳を考える。
「あ、いや、美しい銀髪って言ってたろ? あの白銀を持ってるのは村でもエリアさんくらいのもんだから」
「ふむ、なるほどな。やっぱり彼女は凄い人なんだな?」
「ああ。それで、エリアさんを探してるんだろ? ならさっきあっちへ走っていったぜ」
肩をすくめて明後日の方向を指し示す。
そんなシラムの仕草をジグは不思議そうに眺めている。
「……どうしたんだよ?」
「いや、なんでそんなに素直に教えてくれるのかと思ってな。昨日とは大違いだ。理由は訊かないのか?」
なるほど。確かに昨日宝物庫へ行くのをさんざん止めようとしたシラムの態度としては、妙にあっさりしすぎているかも知れない。エリアに頼まれたとは言えもっと焦らすべきだったのか、と一瞬思ったが。
「アンタらに関わるとろくな目に遭いそうにないからな。さっさと行って欲しいだけだよ」
溜息混じりに、言い訳でもなんでもない素直な本心を口にする。
今はまだ鼻をあかす手も思いつかない事だし。
シラムの仕草を一瞬じっと見たジグは、合点がいったというように息を吐くと、シラムが指した方へ目をやる。
「なるほどね。じゃあ、遠慮無く」
「ああ、とっとと見えないとこまで行っちゃってくれ」
「そうすることにしよう」
そう言うが早いか、再びジグは駆け出す。しかし、ジョギングというかなんというか、本機の追跡を行おうという走りではない。その後ろ姿がのろのろと視界の中を小さくなっていき、どこかで曲がったのか見えなくなるまで見送って。
「……なんでエリアさんがアイツに追いかけられてるんですか?」
背後で様子を窺っているであろう相手に問いかけた。
「いやあ、まあ細かい事は話せば長くなるから省略。とりあえず助かったわ、シラム」
建物の影からエリアがほっとしたような表情で出てくる。
「それにしても、シラムもアイツと知り合いだったの?」
「それはこっちの台詞ですよ……。省略せずに、是非説明してください」
「いや、説明っていっても、実のところ私にもよく分からないのよ。徹夜明けでシャルの家に行ったらアイツらがいて、ご飯食べてから家に帰って寝ようとしたら後ろから声をかけられてね、で逃げてきたってわけ」
頭でも痛いのか、こめかみのあたりを抑えながら疲れたように呟くエリアを、シラムは呆れた様に見つめる。
「なんか端折られすぎて全然分からないんですが……」
「その辺は行間を読みなさい。私はとにかく帰って寝る。もう、眠くて我慢ならない」
そう言うなり、エリアはシラムの返事も待たずにもと来た方向へと歩き出す。
徹夜で何をしていたのかは分からないが、確かにその足取りは重たげに見える。
「って、ちょっと待ってください、シャルの家にアイツらがいたって、じゃあアリアって言う女魔導士もいたんですか?」
「いたけど、それがどうしたの?」
緩慢な動作でこちらを振り返って、眠たげな視線で睨み付けるエリア。あんまり話を長引かせるとこちらの身が危険かもしれない。
そんな事を感じたシラムは手短に言葉をまとめる。
「彼女が今何をしているか、分かりますか?」
「知らない。シャルを鍛えるとか言ってたから、どっかで特訓でもしてるんじゃないの?」
それだけ言うと再び振り返って歩いていく。その背中が、今度は何を言っても振り向かないという意志を告げているように見えた。
よろよろ歩くエリアの背中を見送りながらシラムは考える。
シャルを鍛える?
特訓?
ジグとアリアがこの村へ何をしにやってきたのか、昨日一緒に宝物庫へ向かう過程で簡単には聞いていた筈なのだが、その目的にあのシャルシュ・ワイゼンを鍛える事が関係あるとはとてもではないが思えない。
「……一体、何を企んでるんだ?」
鼻をあかしたいのはもとよりだが、しかしそれ以前に出来れば彼らにはさっさと目的を達して帰って貰いたい。
下らないことをしているようなら嫌味の一つでも言ってやろうかと思い、シラムはアリアを探す事にした。
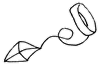
「心配です」
柔らかい草の上に腰を下ろすなり、アリアはそう呟いた。
冗談でもなんでもない、心の底からの危惧の念が感じられる言葉だった。
「えっと、何が心配なんですか?」
「兄様の事に決まっているでしょう」
不思議そうに訊ねたシャルシュの言葉は、若干怒りを滲ませたアリアの言葉にあっさりとはじき返された。
朝食の後、ジグはエリアが立ち去るのと同時に用事が出来たと言って出て行った。アリアとシャルシュが口を挟む暇さえなく、まるで彼女の事を追っていくかのように。
他にどうする事も出来ず、二人は村はずれの一角へと場所を移して約束通り魔術の特訓を開始しようかと思った、その矢先である。
「そうはいっても、ジグさんも魔導騎士なんですから……、意味もなくエリアさんを追っていったわけじゃないと思うんですけど……」
「当然です。兄様はきっと何か考えがあってさっさと出て行ったに違いありません。別にあの女のことを追っていったわけではないはずです」
憮然とした表情でそう言って溜息をつく。
余程ジグの事が気になるのか、腕組みをした、その右手の人差し指がとんとんとせわしなく左手の肘を叩いている。
いらだたしげに表情をしかめて、独り言のように呟く。
「兄様は立派な騎士なんですから、大丈夫です。ちゃんと任務の為に行動しているはずです」
「……あのー、アリアさん? 準備できましたけど?」
なにやら恐い雰囲気を纏っているアリアに向かってシャルシュが恐る恐るといった様子で声をかけた。
両者の距離はシャルシュの歩幅にして二十歩分ほど離れただろうか。その位置に立ったシャルシュは運動に向いていそうなシャツと長ズボンという簡単な服装に身を包み、表情を引き締めてアリアの方を見つめている。
そのシャルシュの様子を見て、アリアははあ、と小さく溜息をつく。
そうだ。兄がやるべきことをやっていると信じるのなら、自分は自分で今やらねばならない事に打ち込まなくては。
勝手に決められた事とは言え、約束は約束。
これからシャルシュの全然てんでなっていない魔法技能を徹底的に鍛え直すのだから。
「すいません。少しぼうっとしていました。……ええ、これくらい離れれば充分でしょう。それでは、まず貴方の魔術の欠点を端的に理解して貰う事にしますから、そこから何か攻性魔法を放ってみてください」
「攻性魔法、ですか?」
シャルシュが戸惑いを浮かべるのも無理はない。
エルフはこの世界に生きる白の女神の眷属の中でも「魔力に愛された民」と言われているほど魔力の扱いに長けている。実際、魔法の純粋な出力においてエルフの右に出られる者はいないだろう。
昨日シラムの魔法をアリアがあっさりと受け流す事が出来たのは魔法の出力とは別の点での攻防においてアリアがシラムに勝っていたからに過ぎない。事実、彼女にはあの時シラムが発動させたような大規模の魔法を自分で放つ事や、或いは真正面から受け止める事はできないか、仮に出来たとしてもその時には相応の犠牲を払う羽目になるだろう。
シャルシュの魔法の実力はよく分からないが、少なくとも昨日の束縛魔法を見る限りではエルフの平均レベルには軽く届いているように見えた。
なら、下手に攻性魔法など放とうものならどれほどの規模になるのかは想像に難くない。
だが、そのような心配は無用だ。シラムの場合と同様に、アリアには魔法の出力とは別の点でシャルシュをどうとでも出来る自信があった。
「大丈夫です。細かい事は気にせず、本気で撃ってきてください。……そうですね、では、風の魔法でどうですか?」
「風の魔法ですか。わかりました。……どうなっても知りませんからね」
しぶしぶといった様子でシャルシュがそう言って、右手をすっと持ち上げる。
その掌がまっすぐとこちらへと向けられる。まるでシャルシュのその全身が一つの拳銃になったかのような錯覚を受ける。
当然だがそこに殺気はない。しかし、殺気ではないにしてもびりびりと肌を突き刺すような何かが、確実にシャルシュの身から放たれている。
そして、それと同時に彼の周りに展開され始める魔法の式。
シャルシュ自身の中にある魔力を一本の糸のように編み上げて、それが大地に一筆書きの陣を描く。
魔法陣からはさらに幾本もの線が伸びて行き、あたりを流れる魔力の流れを一本の無駄もなく完璧に絡め取る。
「魔法の運用手続きは私たちと一緒なのに……、流石はエルフですね」
アリアは呟いて、彼の元に集まってくる魔力の規模を走査魔術で分析する。
風のパラメータに変換された魔力がシャルシュのいる場所を中心に冗談みたいな分布を描く。あたりの魔力脈から一切の無駄なく効率的にかき集められた魔力は、上手くやれば嵐の一つくらいは起こせるかも知れない。
本気で、とは言ったものの、これは少しアリアにとっても予想外の事だった。シャルシュの能力を甘く見ていたのかも知れない。これでは下手をすればシラムなど比べものにならない巨大魔法が完成してしまう。
だが、その中心で全ての魔法構造の中心を支える最も基本となるシャルシュの魔術式を見て、アリアは肩を落とす。
やはり、危険だ。彼の魔法運用は極めて危険な土台の上にあると言わざるを得ない。
シャルシュの周りに集まった魔力が徐々に一つの形を無し、魔法が完成に向けて秒読みに入るのを見て、アリアはほんのわずかに指先を動かして魔術式を組み上げた。
いつでも発動できる状態まで組み立てあげた待機状態の魔術。そこに込めた彼女自身の魔力はごくわずかなもので、この魔術の規模と言ったらシャルシュが今組んでいるものと比べたら大きな川の流れに対して石ころ一粒、みたいなみたいなものだ。とてもではないが対抗できるとは思えない。
そのちょっとしたびっくり箱の確かな手応えを感じながら、アリアは満を持してシャルシュの方を見る。
嵐一つ分にも相当する風のパラメータを持った魔力。その魔力が、今シャルシュの右手の平の中でまるで一本の矢のようにまっすぐとこちらへ狙いを定めていた。
魔力量から推測するに、その威力は恐らく大木くらいなら軽く粉みじんにし、分厚い岩盤も紙のようにあっさりと貫いてしまうだろう。
勿論アリアの小さな体など、直撃したらどうなるかは想像したくもない。
その風の矢を構えたシャルシュが、もう一度だけ確認するように問う。
「……本当に撃ってもいいんですか?」
「大丈夫です。魔導騎士を、あまり舐めない方が良いですよ」
飽くまで余裕を崩さないアリアの様子に、シャルシュは小さく肩を落とした。
「じゃあ、行きます。
シャルシュの言葉とともに解放される魔力の矢。
あたりの空気を巻き込みながら冗談のような初速で矢が疾り出すその直前。
「
小さな呟きとともに、アリアの手からそれが放たれた。
魔力の矢に繭糸のように細くか弱い糸が絡みつくのを見て、アリアは小さな笑みを浮かべた。
シャルシュはそれに気付いている様子はない。
そして、そのまま矢が放たれる。
放たれた矢は、二十歩分の距離を瞬く間に駆け抜け、アリアの直前で突如弾けたかと思ったら天空高くまっすぐに豪風となって吹き抜けていった。
誰の目にも明らかな、制御ミス。いや、違う。アリアの目の前で照準が途端に外れるなどと言う都合の良い制御ミスなどあり得ない。どう考えても、アリアが何かをしてシャルシュの魔法の矛先を変えたと見るのが自然だった。
上空を漂っていた雲にぽっかりと小さな穴が開いてすぐにふさがる。かき集めた魔力の量を考えてみれば充分あり得る話であるが、地上から観察できるほどの穴を雲に開けるなど、冗談か何かにしか思えないような威力だ。アリアは呆れた様に言った。
「……本気でとは言いましたけれど、まさかこれほどとは。シャル、実は貴方は魔法の天才ですか?」
肩をすくめながら視線をやった先で、
「……え?」
シャルシュはぽかんと、我を忘れたようにアリアの事を眺めていた。
「いえ、こちらの話ですから気にしないでください。さて……、」
そんな事を良いながら、アリアは未だ呆然とした様子のシャルシュへと歩み寄った。
先ほど濃密に収束していた魔力は既にあちこちに拡散しており、あれほど強力な魔法を放ったという痕跡は既に無い。
まったく、驚きに値する魔力制御技術だ。普通あれだけの魔法を立ち上げたら、辺りの魔力脈は暫く揺らいで魔力供給が不安定になると言うのに、アリアがさっと走査魔術をかけた限りではシャルシュの先ほどの烈風の矢が残した影響は、ほぼゼロと言っても良いレベルに抑えられている。
環境に擾乱を起こさないように魔力をかき集めて、尚あれだけの出力を発揮できるなど、アリアのような人間の魔導士の常識に照らしてみればまるで悪夢のような現象だった。一般常識とされている事実が悉く崩壊していく瞬間。つくづく、エルフと人間の
が、それはそれとして、やはり先ほどのシャルシュの魔法にはどうにも捨て置けない重大な欠点がいくつかあるのだ。
「……ええっと……」
未だ呆然としているシャルシュの前に立つ。シャルシュはぽかんとアリアの事を見ているのだが、先ほどの現象にまだ驚いているのか、その目は未だにどこか意識が飛んでいるような、そんな雰囲気である。
「それがエルフの反応なんですね。とりあえず解呪されたら呆然としちゃう。私たちなら、高位の魔導士を相手にした時にはまず解呪があるという前提に立つんですけれども、エルフの魔法体系にはそもそも……」
「す、凄いです、アリアさん!」
「へ?」
突然アリアの手を握って、大きな声で叫ぶシャルシュ。
突然の大声に耳がきーんとなっている間にも、シャルシュはアリアの手をぶんぶんと嬉しそうに振り回す。
「あんなの初めて見ましたよ! どうやるんですか? 人間はみんなあんなの当たり前に出来るんですか?」
完全に我を忘れてとにかく好奇心の赴くままに脊椎反射でマシンガンのごとく言葉を掃射するシャルシュ。
その様子に呆気にとられながらも、アリアはえいっと掴まれていた手をふりほどくと、腰に手を当てて表情をしかめた。
「ちょ、ちょっと待ってください。落ち着きなさい、シャル。順に説明しますから、とりあえず私の話を聞いてください」
「あ、はい。すいません、取り乱しちゃって」
今まで自分がどんな状況になっていたかを思い出したのだろう、赤面して縮こまるシャルシュの事を、苦笑いを浮かべながら眺める。
「かまいませんよ。どうせ貴方には今のがまるで魔法みたいに見えたんでしょう? なら、はしゃぐのも無理はありませんから」
そう言って、一歩下がって改めてシャルシュの事を上から下まで品定めでもするかのように眺める。
魔力順応性の高さを示す髪の色――日に透けるような白金の
その色を見ると、改めてシャルシュの魔力に対する親和力が理解でき、先ほどの莫大な魔力量にも十分に合点がいく。
これは、ひょっとしたら少しのレクチャーでとんでもない魔導士が誕生する事になるのかも知れない。
そう考えるとどこかワクワクしてくるのは、何故だろうか。
ああ、そうか、簡単な理由だ。
アリアは自分と、それからシャルシュに呆れて溜息をつく。
やわらかな笑顔を浮かべて。
「好奇心がない者は一流の魔導士にはなれません。そう言う意味では、貴方の先ほどの態度は優秀な魔導士になる素質があると言う事なのかもしれませんね」
そう、この気持ちも好奇心なのだ。未知のモノ――彼がその実力を余すところ無く発揮するところを見たいという、心の底からの好奇心。

手頃な倒木を見つけ、二人して腰掛ける。
隣に座ったアリアとの距離が思わず近くて、シャルシュは一瞬頬に血が昇るのを感じた。
身近にいた女性はずっとエリアだけ、彼女は世話焼きなご近所さんであり、少し迷惑な隣人であり、女性として見ると言う可能性は微塵もないに等しかった。
年の近い少女とこんなに近くにいるなど、シャルシュにとってはその人生で問答無用に初めての事だ。
昨夜は確かに一つ屋根の下に寝泊まりしたわけだが、それとこれとは全く別の話だ。
改めてこうして目と鼻の先に座っているアリア・ムーシカという人間は、年の頃ならシャルシュと一つか二つ違いの女性なのだということを実感する。やわらかなうす桃色の髪の毛が森の風になびき、なんだか甘やかな匂いにどこか胸の鼓動が速まる。
「……あの、シャル?」
アリアが不意にこちらに顔を向け、困ったような表情を浮かべる。
「え? あ、はい、なんでしょうか、先生」
「先生……? まあ、いいですけど。その……そんなに見つめられると何か恥ずかしいんですが、私の顔に何かついていますか?」
眉をひそめて首を傾げるアリア。
その指摘に、ようやく自分がやたらと彼女の事を凝視していたという事実に気付く。
ぼっ、という音でも出ているんじゃないかと思うくらいに、頬が熱を帯びるのを感じた。全身の血液が顔面に集まり、今にも火が噴き出してしまいそうな恥ずかしさ。
そんな事になってしまったシャルシュにとれる行動はそれまでと真逆――つまり、明後日の方向に顔を背けてしまう事だけだった。
「……シャル、どうしたんですか?」
「べ、別になんでもないです! それより、さっきのことの説明、してくれるんですよね?」
視線は直接アリアには向けずに、恥ずかしさを隠すようにシャルシュが言った。
「え、ええ。それは勿論これから話す事の中でちゃんと理解して貰います。いえ、理解して貰わなければ困る、と言った方が正しいでしょうか」
「理解して貰わなければ困る、んですか?」
「そうです。まあ、その意味はおいおい分かりますよ。それでは、まず、シャルは魔法の二大属性については知っていますよね?」
「えっと、白と黒、って言う意味ですか?」
訊ね返すシャルシュに、アリアは満足げに頷いた。
この世には、大きく分けて二つの魔法の系統が存在する。通称白魔法、そして黒魔法と呼ばれるものである。両者の区別は、その力の源である魔力の性質によって分けられている。白魔法の源である白の魔力はこの世界に満ちあふれる白の女神に起源を持つ魔力であり、一方の黒魔法はかつて世界に存在していたとされる黒の神の放つ黒い魔力を力の源とする。一般に、白魔法より黒魔法の方が破壊・攻撃に優れていると言われているが、その本当のところはよく分かっていない。というのも、黒魔法は理論的に存在している、と言われる程度のもので、その目撃例は極めて少ないからだ。黒魔法というのは《あちら側》の世界と呼ばれる異界に住まう黒の神の眷属たちの使う魔法であり、そもそも彼らが《こちら側》の世界に姿を見せる事など有史に残っている例に限れば片手で足りる。そのわずかな目撃例から存在だけはかろうじて実証されている、そのような幻の魔法が黒魔法なのである。
「それじゃあ、二大属性よりも下位になりますけど、白魔法の四属性についてはどうですか?」
「火、水、大地、風の四つの属性の事ですよね」
シャルシュの、今度は先ほどよりもやや自信のある答えに、再びアリアは満足げに頷く。
白魔法の下位分類である地水火風の四大属性。これは白魔法が主に自然現象に関与する事の出来る魔法であるから、ということから分けられる四つの属性である。
シラムやシャルシュが使ったような風の魔法の他にも、炎を熾す魔法、水を操る魔法、大地を割る魔法、などもある。一般にこの属性は個人の得手不得手はあまり無いとされていて、なんの属性の魔法を使用するかは個人の好みに因るところが多い。
「そう、それから、光も忘れてはいけません」
アリアが靴先で地面に四角錐を描きながら、付け加える。
底面がほぼ正方形で、それらの上に一点、☆のようなものが据えられた四角錐。
図の意味するところは、シャルシュにとっては説明など無くても十分に理解できた。
すなわち、底面の正方形の各頂点はそれぞれ地水火風の四属性。そして、それらの属性を超越して純粋な魔力を用いて行われる、極めて高位な魔法。それらは、時に光属性とも呼ばれる事がある。
「どうやら、魔法に関する基礎知識はある程度しっかりしているようですね」
アリアの満足げな笑みに、思わずシャルシュは嬉しくなる。
褒められる事には慣れていない。なにせ褒めてくれる人など自分の周りにはほとんどいなかった。
「その辺りの事は、本で勉強しましたから」
「本で? でも、貴方には魔法を教えてくれた師匠がいたと言ってましたよね?」
「あ、えっと、あの人はそんな細かい事は教えてくれなかったんです。とにかく、自分の感じる魔力の流れに、魔術式を投げこめと、それだけ」
「投げこむ、ですか?」
「釣りをするように、魔力の密度が濃いところに自分の魔術式を投げ込む。それだけで魔力なんか勝手に集まってくるんだって」
事実、自分は今までもずっとそうやって魔法を行使してきた。
今でもあの人の教えは、シャルシュ・ワイゼンを形作る重要なパーツとして生き続けているのだ。
今まで、こんな話を他の知り合いにした事なんて無かった。だからだろうか。どこか、人とは違う自分の秘密を話すのがほんの少しだけ気持ちいい。
他のエルフとは全く違う自分の魔法。その方法を喋るシャルシュは、いつの間にか笑顔が浮かんでいた。
シャルシュが満足げにしている一方で、アリアはなにやら表情をしかめているようだった。
そのアリアがやや抑えたような声で更に問う。
「先ほどの魔術式はその人が教えてくれたものですか?」
周囲の魔力脈から膨大な量の魔力を無駄なく吸い上げた、尋常ならぬ魔術式。魔導理論に関しては素人同然に見えるシャルシュが自ら構築したものとはとても思えない。
その一方で、理論を熟知していない素人にあんな規格外のものを安易に教えるなど、それはそれで正気の沙汰とも思えない。
しかし、アリアの表情が少し変わっている事にシャルシュは全く気付いていない様子で嬉しそうに答える。
「はい。最初に教えて貰った時から、ずっと同じ形で使い続けてるんです」
「はあ……、つまり、貴方は初めて魔術を使った時からあんな魔術式を使っていたという事ですか」
溜息混じりにそう言って、アリアは額を抑える。
そんなアリアの仕草に、シャルシュは今まで楽しげに話していた気分に急に水を被せられたような気がした。
「……何か、まずいんですか?」
あの人が教えてくれた事が間違いだったのか。そんな不安が急速にシャルシュの中に広がる。
「まずいですね、ええ、とてもまずいですよ、それは」
やや頬を膨らませ、アリアはシャルシュの事を見つめる。
その厳しいまなざしに、何か自分が悪い事をしてしまったかのような感覚に陥る。
まるで知らずに犯していた罪を突然糾弾されるかのような。
「あ、そんなに表情を暗くしなくてもいいんです。悪いのはシャルではなく、初心者に重要な事を教えもせずにあんな高機能な魔術式を教えた貴方の師匠なんですから」
アリアはシャルシュを励まそうと思っていった言葉だったのだろうが、結果的に彼女のひと言はより一層シャルシュの表情を暗くすることとなった。
「……師匠を、悪く言わないでください」
ぽつりと漏らす。
彼の事だけは悪く言わないでいて欲しかった。
彼は凄くて、彼は偉大で、そして彼はシャルシュにとってかけがえのない恩人。
それは、シャルシュの中で揺るぎようのない真実であり、信仰にも似た信念なのだ。
「……駄目なんです。師匠の悪口だけは、駄目なんです……」
その姿に、自分の騎士道に対する信仰に通じるものを見たのか、或いは単にこれ以上言っても無駄だと思ったのか。アリアは小さく息を吐くと、苦笑いを浮かべた。
「まあ、そのお師匠さんも詳しい事を知らずに教えたのか、或いは何か意図があったのかも知れませんし……、その辺りは私は知りようがないですから、とやかくは言いません。ただ、シャルがしていた事が危険極まりのない事だった、と言うのも紛れもない事実なんです」
師匠の事から論点を外したアリアが、顔を上げたシャルの目をまっすぐと覗き込む。
透き通った桃色の瞳は、脅す雰囲気もなければ緊迫した雰囲気もない。ただ、純粋に真実を告げている瞳だ。
師匠への敬愛も何もかもをひとまず脇に措いて、シャルシュの中にすっと染みいる。
「ですから、何はともあれまずは魔術の運用方法を学んで貰います。良いですね?」
「……はい」
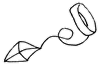
走査魔法で描き出された地図上に、高密度の魔力反応を示す光点が現れる。
みるみるうちに輝きを増していくその点――目の前で魔術式を編み上げているシャルシュの方に手をすっと伸ばし、アリアは解呪の魔術式を放つ。
ただのいち動作、ほんの一瞬で、それまでシャルシュが編み上げていた魔術式が解け、何事もなかったかのように虚空へと消え去る。
「はい、これで丁度百回目ですね」
「また、駄目だったんですか……」
アリアのあっさりとした言葉を聞き、シャルシュはどさりとその場に座り込んだ。
下は土の地面だったが気にならない。いや、気にする余裕が今はない。
魔術式を組み上げては、アリアにかき消される。作っては消され、作っては消される。その繰り返しが、シャルシュは数えていなかったがアリアの言うところによると既に百回は行われてしまったらしい。
いつの間にか息も上がっていて、ぜえぜえと肩を上下させながら視線を上げると、涼しげな表情でこちらを見下ろすアリアと目があった。
「もうお終いですか?」
一切疲れの表情を見せていないアリアは、頬をかすかに持ち上げて挑発的な笑みを浮かべる。
そんな笑みを向けられたら俄然座ってなどいられない、とは思うのだが、普段特別な運動もしていないシャルシュの心臓は基準を遙かに超える無茶な労働に先ほどからストライキ寸前の状態だ。立ち上がろうにも、脚も動かない。
「ちょ、ちょっと待ってください。ちょっとだけ休憩……」
「まあ、仕方ありませんか。慣れない高密度魔術式をあれだけの密度で組めば……、いえ、それにしてもやはり少々ギブアップが早いですか」
「し、仕方ないですよ。僕は体力無いんですから……」
「堂々と言えた事でもありませんね」
呆れた様な声でそう言うと、アリアは不意に空を見上げた。
釣られてシャルシュも上を向く。
どこまでも青い空が広がっていて、その中に時折思い出したように白のまだら。
ぷっかりと浮かんだ雲は春風に流されて緩やかに軌跡を描く。
そんな穏やかな景色を眺めていたら。
「……っとっとっと」
どさっ。
ついバランスを崩して背中から地面に倒れ込んでしまった。
土の冷たい感触が、シャツ一枚越しに伝わってきて気持ちいい。
寝そべって見上げる空は、いつもよりも少しだけ広く見えた。
「問題点は、少しずつ良くなっています」
不意にアリアがそんな事を言った。
「え?」
「だから、シャルの魔術式は着実に良くなってきている、と言ったんです」
「そうなんですか? でも相変わらずアリアさんには一瞬で砕かれてるんですが……」
「私に砕かれない魔術をすぐに編めるようなら、すぐに協会の一流魔導士になれるから大丈夫です」
それはひょっとして遠回しに当分は無理、と言われているのだろうか。
そもそもシャルシュにはこの課題の到達目標も、そしてこの課題の難易度もまだ今ひとつ分かっていないのだ。
「アリアさん……、僕は結局どうなれば良いんですか?」
「どうなれば……、ですか? それはまた、難しい質問ですね」
寝そべっているシャルシュからは見えないが、アリアが笑いを漏らすのが聞こえた。
笑う事はないだろうに。
そう思っているうちに、顔のすぐ横にとさり、と何かが落ちる音がする。
そちらへ顔を向けると、アリアがそこに腰掛けてこちらを見下ろしていた。
「そうですね……、話は少し変わりますけれども、シャルは神様を信じていますか?」
「神様……、ですか? 白の女神なら、少々」
この世界に漂う魔力を初めに生み出したとされる存在、白の女神。彼女にどんな力があったのか、詳しくは知らないにしても現在この世界に生きる者の多くはその存在の事を神格化している。
「いえ、必ずしも白の女神の事でなくても良いんです。そう……例えば、運命を司る神様がいるかどうか、とか」
「運命を司る神様……ですか?」
知らないうちに声が固くなっていく。かすれながら絞り出した声は、かろうじてアリアに届いた。が、彼女はそんなシャルシュの様子の変化に気付かない。
「そうです。私は、運命の神様はいるって思っているんです。私たちの思いも寄らない凄い存在が、私たちの善行悪行に目を光らせて相応の運命を振り分けてくれてるんだって。そう思った方が救われるような気がするんです」
それは……。その運命の神様という奴は、一体何をしてくれるというのか。
喉の奥が乾いていくのを感じながら、シャルシュは何も口に出来ずにアリアが楽しそうに喋るのをただ聞いている。
「あ、それでも、誰かが言っていたんですけれど、何か都合の悪い事があっても、神様に見なかった事にして貰えば良いそうです。私としてはそんな意見はとても賛同できないんですけれど……、シャルはどう思いますか?」
不意に向けられた質問。
渇いた喉を震えさせて、シャルシュが応える事が出来たのはただのひと言だけだった。
「神様なんて、いませんよ」
「え?」
アリアが言葉を無くしてこちらを凝視する。
その表情を正面から見ることが出来なくて、シャルシュはアリアの方から顔を背けた。
「あ、あはは、そうですよね。こんな子供っぽい事、シャルは信じてないんですよね。すみません、何だか変な事を言っちゃって。……その、神様が見ていようが見ていまいが、魔術が暴発しちゃえば一緒だよっていうのを言いたかったんですけど……、ごめんなさい、回りくどかったですよね」
明るい、乾いた感情の載らない声でアリアはかろうじてそう言った。
もう少し他に言い方はあっただろう。そう思っても、シャルシュが口にしてしまった言葉を取り消す事は出来ない。アリアに不要な不快感を与えてしまったという事実は、消えない。
それこそ、神様がいるのなら見なかった事にして、無かった事にして貰いたいくらいだ。
だが、現実には神様なんていない。
白の女神は単なる魔力の象徴で、黒の神にしたって同じだ。
世界にいるのは自分たちエルフ、それからアリアたち人間。そして雑多な生き物たち。そこに神などと言う存在が介入する余地はない。
「結論から言ってしまえば、ゴールなんて無いんですよ、シャル」
そっぽを向いていたシャルの背中に、不意にアリアの声がかかった。
「そこが分かってないって言う事は教え方が悪かったんでしょうか?」
先ほどのシャルシュの言葉を気にしてか、若干こちらの様子を窺うように、おどけた風に言うアリア。
そんな彼女の様子に、少し慌てて返事をする。
「い、いや、そういうことじゃ」
「冗談です。まあ、見えもしない目標を目指すのも難しい話ですから、シャルの気持ちも分からないではないんです」
そう言うと、再びアリアは視線を空へと向けた。
「ただ、先ほども言いましたが、貴方の魔法には重大な欠点がある。それは、自らの魔力で編み上げた魔術式によって自然界にある魔力を制御して魔法を放つ人間のやり方をやっている以上、無視してはいけない欠点なんです」
地面の草をわずかにむしって、アリアはふっと風に乗せて投げた。
上昇気流にでも乗ったのか、緑色の断片が青い空に吸い込まれていく。
「私たちはまず自分たちが持っている固有の魔力で魔術を編む。そして、その魔術を鋳型として、自然界の魔力を取り込んで魔法を形と為すんです。その鋳型に不備があれば、魔法を解呪されることもあるし、魔術式を壊される事によって自らに魔力ダメージが返ってくることもあるんです。貴方の魔術式は、その意味で決定的に脆い。いえ……、脆かったと言うべきでしょうかね」
「ということは?」
「先ほども言いましたが、段々緻密で強固な魔術式が出来てきています。勿論、魔術式の強度を上げると言う事は消費魔力も大きくなるので決してメリットだけではありません。でも……、シャルの場合はやはり最低限の強度を持った魔術式でないと、絶対危険なんです」
最後の「危険」と言う言葉だけ、少しアリアの声が固い。
その理由なら、シャルシュは先ほど既に聞いてはいた。
なんでも、シャルシュの使っている魔術式は魔法を発動させる時に自分の中にある魔力の貯蔵庫――魔力炉と外界の魔力の流れを一時的に直接繋げてしまうものであるらしい。
普通人間の魔術師は体内から魔力を放出して魔術式を編み上げたら、その段階で体内に持つ魔力炉と自分の魔術式との魔力的接続を切断する。その為に、魔術式を破壊されるという最悪の事態に陥っても自分に跳ね返ってくるダメージは最小限度で済む。
しかし、シャルシュのように魔力炉を開放した状態で魔法を発動させる場合、魔術式破壊の際に最悪の場合は外界の魔力が彼自身の中に流れ込んできて、強烈な魔力ダメージを受けてしまう可能性がある。
シャルシュには実感が沸かなかったのだが、アリアはバケツの底が抜けるのとため池の堰が切れるのほどの違いがある、と言っていた。
それほどの危険な事を、シャルシュは今まで無意識にやっていたらしい。
「まあ、魔力接続の手続きは無意識下でやっちゃってるから今更直せそうにもないんでしょう? なら、諦めてとにかく強固な堰を作るべきです。壊れなければ大丈夫なんですから」
そう言ってアリアが立ち上がる。
訓練再開、ということなのだろう。
腕と脚に力を入れてみる。大丈夫そうだ。息ももう落ち着いているし、もう百回くらいなら頑張れなくも無さそうだった。アリアだってあれだけやればそろそろ疲れが出てくる頃だろう。なら、一度くらいは上手く魔法を発動させられるかも知れない。
勢いをつけて、思い切り立ち上がる。
「よし、大丈夫です」
「なら続きをやりましょうか。また遠慮無く解いて上げますから」
そう言ってアリアが不敵な笑みを浮かべる。
その笑顔を見て、そういえば、とシャルは不意に気になっていた事を訊ねた。
「あの……、気になっていたんですけれど、魔術式を壊されるっていうのは本当にそんなに危険なんですか?」
「あら、確か一度言ったと思いますけれど……。私は今解く方の解呪しか使ってませんけれども、壊す方の壊呪も使えるんですよ。そんなに気になるなら、一度試してみますか?」
アリアが浮かべた笑みは、今までとは比べものにならないほどに邪悪なもので、一瞬背筋に震えがはしってしまう。
「え、えっと、やっぱり良いです……」
怯えたように即答したシャルシュを見て、アリアはその邪悪な笑みとは百八十度異なる、おかしさを堪えきれないと言った笑みを浮かべて口元に手を当てる。
「冗談ですよ。壊呪なんて使えても使う人はいません。包丁を持っていても、みんな人殺しにはしるわけではないでしょう? それくらい危険なものなんです。下手をすれば死にます。だから、私は貴方を放っておけなかったんですよ」
「そう、なんですか」
笑顔で死ぬ、などと言われると、真顔で言われるよりも余程恐ろしく思われるのは、きっと気のせいではない。
若干背筋に寒気は感じながらも、シャルシュは何度か頷き、「じゃあ、始めます」そう言って数歩下がる。
適度な距離を開け、アリアの方へと右手を構える。
編み上げるのは風の魔法、その根幹を支える魔術式。
硬く、より硬く。
強く、より強く。
厚く、より厚く。
自分の体内から少しずつ魔力を絞り出し、緻密で強固な魔術式を形にしていく。
掌の上で徐々に成長していく魔術の帯が、少しずつ重みを増していくのを感じる。
先ほどアリアに解かれたものよりも強い手応えを感じる。
「行きます」
「どうぞ」
笑顔でそう答えた魔導士に目掛けてその腕を突き出す。
瞬間、強烈な存在感とともに掌から放たれる魔術式。
周囲の魔力を吸い上げながら、急速に膨らみその存在感を増して、魔術から魔法への昇華の階段を駆け上がっていく。
それとほぼ同時、アリアの右手の指が、絵でも描くかのように宙を軽くなぞった。
魔術式の中心に先ほどまでと同様に楔が打ち込まれる感覚。
ぴしり
小さな亀裂が入る。
強固な縛りによって高密度に圧縮されていた魔力が、鋭く噴き出し始めるのを感じる。さらに、その亀裂から何かが進入して急速にシャルシュの編んだ魔術式を溶かしていく。
苦労して作り上げたものが砂上の楼閣だったことを思い知らされるこの感覚、それが百一回目。
これではまた解呪されてしまう。
幾ら強固に魔術式を組み上げたところで、小さなひびを入れられ、そこから鮮やかに溶かされる。アリアの技法には到底叶う気がしない。
だが、そんなのは
「……いや、だ!」
このままこれまでの百回と同じように解呪されてしまうなんて、嫌だ。そんな気持ちがシャルシュの中で弾けた。
ならばどうすればいい?
解呪されずに魔法を発動させる為にはどうすればいい。
魔術式を強固にするだけでは駄目だった。
ならばどうすればいい?
崩されないようにするのが無理ならば。
「何度崩されても、また組み直せば良い」
どうして今までその発想に至れなかったのか。自分に歯がみしながら、シャルシュは即座に魔術式の再構築を開始した。
アリアの解呪魔術による侵食、それに真っ向から対抗して、溶かされた分だけ魔術式を補充する。
風を括る魔術式を。
風を導く魔術式を。
風を研ぎ澄ます魔術式を。
溶かされる前と変わらぬ精度で、変わらぬ密度で組み上げる。
否、今この瞬間、魔力はこれまでよりも遙かに速く、遙かに強烈にシャルシュの手元に集まってきていた。
魔術式が強固になりつつあることが、魔力収集能力をも強化したのかもしれない。
――いける。
この速度なら、負けない。
溶解と構築、二つの相異なる力が、シャルシュの目の前に展開される魔術式という盤面の上でせめぎ合い、ここにおいて勝敗はただ単に速度論的に決定される。
走査魔術の画面を見つめるアリアの表情が一瞬苦いものでも食べたかのようにゆがめられる。
そして、両者の力は一瞬均衡した。
「……それでは、駄目です」
ぽつり、と。
今まで聞いた事もないような、低く怒りを押し殺したアリアの声がシャルシュの鼓膜を撃った。
弾かれたようにアリアの方を見る。
その瞬間、シャルシュの脳裏から、全ての感情が強制的に排除された。
ただ一つ、恐怖を除いて。
彼女はまだシャルシュが見た事のない表情をしていた。こちらを睨み付ける、鬼のような形相。同じ顔のパーツを使っているのにこうまで違う表情を作れるのかと思う。
殺気にも似た怒りの感情。隠す事のないむき出しの刃物が、シャルシュの全身に狙いを定めて寸止めにされているような錯覚。
圧倒的な迄の威圧感に頭の天辺からつま先まで余すところ無く射竦められて、立っている事さえ出来なくなる。しかしその場に膝をつく事さえままならない。
少しでも動いたら――される。
躯の停止は心の停止を呼び、魔術式の再構築も完膚無きまでに停止する。
怯えて動きのとれない蛙を前にした蛇のように、それまでに倍する、いや、比べものにならない速度で魔術式が侵食、溶解されていき、無へと還ってゆく。
思い知らされた。
これが、アリアの実力。
今までの特訓で見せていた百回の解呪など、彼女にとっては本気でもなんでもない、お遊びのようなものだったのだ。
彼女が見せていた動作、その指先をわずかに動かすだけのそれと何ら変わらない、肉体的にも魔術的にも同様の負荷の事しかしていなかったのだ。
それを自分はなんて浅はかな誤解をしていたのか。
完膚無きまでに解呪され、そのまま強烈な脱力感とともに倒れ込む。
あれ……、一回だけの魔術で、なんでこんなに、疲れ……、
薄れ行く意識の中で駆け寄ってくるアリアの表情だけがはっきりと認識できた。
先ほどの怒りの形相はすっかりと抜け落ち、心配そうな表情で何かを言っているように見えた。

魔力が吸い寄せられていく。
辺りの地脈という地脈から、まるで何かに引き寄せられているかのように魔力が一つの方向へと流れていく。
シラムは背筋をくすぐられるかのようなえもいわれぬ気持ち悪さを感じていた。
エルフは魔力に対して極めて敏感な種族である。彼らはほぼ同じ外見をした人間には存在し得ない五感以外の魔力感を持っているのである。
そのエルフの持つ特有の感覚がシラムに告げていた。
妙な事が起きている、と。
シラムの周囲に起きている妙な流れは、感覚としてはわずかだ。恐らく、あと十歩でも「その現場」から離れていれば、シラムも何も感じないままで居ただろう。きっと村の住人でこの奇妙さを感じている者はいないはずだ。
村はずれの茂みでシャルシュとアリアを探していたのだが、何とも奇妙なものを見つけてしまったものだと首を捻る。
「……まさかとは思うけど、アイツらの仕業なのか?」
今ここにいない女魔導士の顔が思い浮かぶ。エリアの話では、彼女たちはこの近くに居るはずである。
得体の知れない出来事と、得体の知れない人物。その二つを無根拠に関連づける事は、決して難しい事ではない。
魔力が吸い上げられている方へと走る。村はずれ、茂みをかき分けて、人気のない方向へと魔力は向かっている。
高い木立を抜けたその先の広場。そこに二人はいた。
「……だから、無知な人は嫌いなんです!」
広場の中央では、アリアがしゃがみ込んでいた。
昨日出会った時のローブ姿とは異なる。動きやすそうなうす桃色をしたズボンとシャツ、腰回りや主要な関節にはプロテクターのようなものをつけており、服装だけならそのまま戦いに赴けそうな凛々しさだ。
だが、彼女の表情は今は怒りにゆがめられており、腕の中でぐったりとしているもう一人の人物――シャルシュに向かって何事かを叫んでいる。シャルシュはぐったりと精気のない表情をしており、アリアの言葉に対して何の反応も見せていない。
「魔術式の補強なんて!」
彼女が何の事を言っているのかはシラムにはわからない。
わからないが、何か奇妙な事があってその原因があると思しきところまで来てみれば村の者が倒れている。
村を、そして村人を守る森林警備隊の隊員である彼がそこに犯人と被害者という構図を当てはめるのは、当然の事だと言えた。
「……おい、騎士サマ、何やってんだ?」
シラムの声に、ようやく気付いたという様子でアリアがこちらを振り返る。その目元は涙で濡れているように見えた。
「……シラムさん……、でしたか?」
涙でにじんでいる瞳が「何故?」と問うているのを無視し、シラムは彼女とその腕の中で眠るシャルシュを睨み付ける。
「良いところにお邪魔だった、って様子でも無いよな。アンタ、そいつに何をした?」
アリアの腕の中でぐったりとしているシャルシュを指さし、問う。
「貴方には関係のない事ではありませんか?」
「あるさ。そんな奴でもこの村の一員だ。なら、俺たち【森の翼】が守らなきゃならないものなんだ。そいつが倒れてるとあっちゃ、見過ごせない」
そう。見過ごせないのだ。
自分はこの村を守ると誓ったから。村人たちを守ると誓ったから。
「もう一度訊くぞ。アンタ、そいつに何をした?」
アリアはそんなシラムの様子を見て、諦めたように息を吐く。
俯いて、シャルシュの胸元に手を添えた。
「釈明するつもりはありません。彼がこうなったのは、私の責任です」
「えらくあっさり認めるんだな。で、そいつに何をしたってんだ? 事と次第によっちゃ容赦はしないが」
アリアがこちらを振り返り、じっと見つめる。何かを推し量ろうとするような、そんな視線。
その視線がまるで氷のように冷たくて、シラムは思わず一歩後ずさった。
彼女が小さく溜息をつく。
「エルフに話をしても無駄です。今はとにかくシャルをどこかで寝かせないと」
そう言ってシャルシュの肩の下に自分の肩を入れ、彼をどこかへと連れて行こうとする。
シラムの事など既に眼中にない。
シャルシュは男としては決して体格の良い方ではない。しかしアリアと比べると幾分か上背がある為、彼女が肩を使って運ぶとなるとどうしても地面に脚を擦る事になる。
ずっずっといびつなシュプールを描きながら茂みの小道を進んでいこうとする小さな女魔導士の背中を、叫ぶようにして呼び止める。
「ちょ、ちょっと待てよ!」
「まだ、何か?」
不機嫌そうに表情をゆがめて、アリアがこちらを振り返る。これ以上話しても時間の無駄、と言う無言の圧力は気付かないふりをして受け流し、シラムはアリアと彼女の肩に担がれたシャルシュの様子を見比べる。
「何があったのかは知らねえけど、そんな安易に動かしても大丈夫なのか? 安静にしておいた方が良いとか……」
「外傷はありませんし、心拍もとりあえずは正常です。一応、動かしても大丈夫と判断したから、動かしています」
それくらい当然でしょう、と何だかこちらを小馬鹿にするように言うアリアに、こめかみが無意識のうちにひくつくのを感じる。
が、今はそんな事を気にかけている場合ではない。
アリアの肩に担がれたシャルシュはどことなく血の気の引いた顔色で、死人のように目を瞑っている。早くどこか落ち着ける場所で寝かせてやった方が良い、というのは確かなようだ。
アリアの方へ一歩踏み出して、右手を差し出す。
意図を図りかねるのか、彼女は桃色の瞳を疑問符で曇らせて、シラムの手をじっと見つめる。
「そいつを貸せ。アンタより俺が運んだ方が確実に速い」
「……ありがとうございます」
どこか納得いかない様子なりにも、シラムの言っている事が正しいと判断したのだろう。しぶしぶアリアがシャルシュの肩を譲る。
ひょいと背負ったシャルシュの体は、本当に男かどうか疑ってしまうほど軽かった。
「まったく、鍛え方が足りねえよ」
吐き捨てるように呟いて、茂みをかき分けながらアリアが向かおうとしていた方向とは別の向きへ足を進めていく。
「え、シラムさん、どこへ?」
戸惑いを隠せない様子でそう問いかけてくるアリアの方を振り返って、努めて真摯な口調で言う。
「俺らの本部。ここからならコイツの家より近いし、それに治療設備だってそれなりに揃ってるからな」
アリアが進もうとしていた方角から彼女が行こうとしていた場所の予想はついていた。ならばどう考えても森林警備隊の事務所へ運んだ方が都合が良い。
シャルシュの家がどんなのかは知らないが、少なくとも薬やらの治療資材に関しては確実に【森の翼】の事務所の方が充実しているはずだ。それに医術に明るい隊員も少なくない。
「それから、アンタには色々と聞きたい事もあるしな」
「なるほど、治癒と取り調べを兼ねた連行、と言うわけですか。でも、話しても無駄と言ったと思いますが」
「それは聞いてから俺が判断する。言っておくが、アンタが逃げてもシャルは事務所まで連れてくからな」
そう言って、アリアの返事も確認しないままに茂みをかき分けて進む。
背中から呆れた様な声が聞こえた。
「逃げる理由なんて、ありませんけどね」
to be continued
WEB版あとがき
今が夜でもこんにちは。因みに僕がこれを書いている今現在は夕方です。yoshikemことよしけむです。
Monochronikaの第3回でした。幻想組曲29号へ掲載させて貰った作品ですね。ぼちぼちと、物語を動かしていきたいなぁ、と言う回。
前回までで、一番はじめのキャラクターが出そろったので、ようやく物語を転がして行けそうです。
鬼教官のアリア先生修行編。その一。ただし、修行が続くのかどうかはまだ決まっていないんですけれどね。
Monochronikaは大体2話を1セットとして話を進めていこうと思っているのですが、その理屈で言えばこれは「前編」に当たるお話。修行の途中で意識を失ってしまったシャルシュ。はてさて彼はどうなるのか。
そして、修行を付けていたアリアはそれを見てどう思うのか。
徐々に物語の深いところに突っ込んで行ければいいなぁと思っているのですが……、どうにも僕は行き当たりばったりで書いてしまうところがあるので、難しいかも知れません……。
自分にもっと計画性があればなぁ!
とにかく、次回「後編」を息切れせずに書けるよう、頑張ります。
yoshikemでした!
作品展示室トップへ
総合トップへ