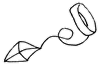
あー……、だるい。
漏れ出そうになった呟きはどうにか飲み込んで、男は視線を再び前へとやった。
行けども行けども広大な森が終わりを見せる気配はない。果てしないかに見える暗緑の闇は進んだ分だけうっそうと濃くなっていくようで、溜息をつく度に足が重くなるような気がする。
実際に軽い空気を吐き出した分この体は重くなっているのではないだろうか、そんなことを考えて、男は
くだらない。そんなことで体重が減るというのなら、美容を磨き体重を減らすことばかりを腐心する世の淑女の面々はひたすらに息を吸うことにだけ尽力していれば済むことになる。そうなればいずれは風船のようにぱんぱんに膨れた女性が宙を舞うように軽やかに闊歩する世の中も来るのかも知れない。
まさか。
そんな馬鹿げた光景があるのなら是非とも見てみたいものだが、いくら何でもあり得ない。あまりにも馬鹿げた自分の考えに流石に呆れて、溜息をつく。
「太いのに軽い……か。あったら面白そうな話だがな」
「……何を言っているのですか、兄様?」
呟きには、そよ風のようにやわらかな声が返事をした。
隣を歩いていたはずの連れが、いつの間にか男より少し前へと出てこちらを振り返っていた。薄桃色のローブに身を包んだ彼女は、少し唇を尖らせているようにも見える。
目深に被っていたフードを脱ぐと、丸みを帯びた愛らしい顔が少し怒ったようにゆがめられていた。笑っていれば愛嬌のあるだろう容貌が怒りに眉をしかめている様は、しかし兄としての身内びいきを差し引いても十分に可愛らしいものであった。
それはともかく、男には妹がそれほどに怒る理由が思い浮かばなかった。
「……何怒ってるんだ?」
「自分の胸に訊いてみてください」
「胸にって……、俺、何かしたか?」
てんで心当たりがなかった。それも当然だ。何せ男は今まで妹とはこれっぽっちも関係のないことを考えていたのだ。いきなり怒られても、どうして良いのかさっぱり見当もつかない。
そんな当惑が表情に出ていたのだろう。妹は更に唇を尖らせると、その細っこい人差し指をぴっと顔の前に立ててこちらを睨み付けた。
「もう、人が気にしていることを言うなんて、騎士道に反するんですから」
「気にしていることって……、ああ」
自分の言動を思い返して、さきほど無意識のうちに妹のNGワードを踏んでいたことに気付いた。
「……太いってのはお前のことじゃないよ」
「え? そ、そうなんですか?」
彼女は驚いたように口を手で覆った。その拍子に彼女のうす桃色の髪の毛がふわりと揺れる。その一挙一動がどうにも愛くるしい小動物を思わせた。
この愛すべき妹が太る、だとか太い、だとかの単語にやたら執心していることをうっかり失念していたのは、男のミスだった。とは言っても、話の流れも何もないところでぽっと出た単語に目くじらを立てて食らいついてくるのもどうかと思う。
ということで、男は少々悪戯心を出してみることにした。
「でもな、お前は別に太っていないと思うけど」
「兄様に言われたって説得力無いです……。そりゃ、協会のローブはゆったりしていて体の線が見えませんし、兄様と比べたら太ってはいないかも知れないですけど……、私の中では今は結構ピンチなんです」
「そうなのか? じゃあ、もし水着なんかを着たら?」
「えっ……、み、水着ですか……? 駄目ですよぉ、あんな体の線がはっきり出る服を着るのは。この間だってウエストが……その……、って、何を言わせるんですか、兄様!?」
怒りと羞恥で顔を真っ赤に染めて言い返してくる妹は可愛く、意趣返しとしては既に充分目的が達せられたように思えた。が、ここで素直に退くのもいささか大人しすぎる感があるような気がした。
「いやいや、続けてくれ。愛すべき妹の体について知っておくのは兄としての義務だろ。でなきゃ、いざ病気になった時とかに対応が遅れるかも知れないしな」
「結構です! もし兄様に知っておいて貰わなきゃならないような異常を抱えてしまった時には迷わずお話ししますから!」
「そうか? ならまあいいんだが」
妹のウエストは気にならないでもないが、別に知っておく必要がある情報というわけでもない。というかこのまま聞き続けるといずれ変態扱いされそうな気もするし、ここら辺りが潮時だろう。
そんなことよりも、真に彼女に訊ねるべきことは別にある。
「ところで、まだなのか?」
雑談をしながらも足は目的地へ向けて着実に歩を進めている。協会から与えられた情報によると、そろそろ目的のものが見えてきても良い頃合いだ。面倒な仕事はさっさと済ませて帰るに限る。そうすれば、うんざりするような森ともおさらばだ。
というのに。
「そろそろの筈……なんですよね」
妹は不思議そうな表情で辺りを見回すと顔をしかめて首を横に振った。
何かを探るように、手のひらを周囲の空間に向けて断続的に呪文を呟く。走査魔術に関してはそれなりの実力を持つ彼女が珍しく険しい表情を作っていることに、若干の驚きを覚えた。
「広域走査(エリアサーチ)には、さっきまで引っかかっていたんです。ちゃんと目的の方へ来ていた筈なんですよ……。なのに……」
信じられないといった表情で少女は足を止めると、地面に手を当てて精密走査の魔法陣を展開する。
嫌な予感を覚えた。少なくともここ数年一緒に任務をこなしている間、男は少女がこの魔法陣を組むところを見たことがない。それはつまり、そのような強力な魔術を用いる必要がなかったと言うことだ。
「なのに?」
「……反応が、消えました」
「そんな馬鹿な」
彼自身は索敵系の魔術は使えない。つまり、反応があるのかないのかすら分からない為、少女の言葉の真偽を確かめることは出来ない。
だが、それを疑う理由がない。
彼女が消えたと言ったのなら、それは真実消えたのだ。
「考えられる可能性は?」
「対象の自然、又は人為による消滅。或いは、何者かによる妨害……」
「お前の走査を邪魔できる妨害魔術なんてあるのか?」
彼女の走査・索敵魔術に関する実力は二人の属する魔導協会でも指折りのものだ。これは断じて身内びいきなどではない。
その彼女の索敵を逃れうる魔術があるなど、男にとっては信じがたいことだったのだが。
「魔術に最強は無いんです。どんな優秀な索敵魔術であっても、逃れうる可能性が無いわけではありません。もしこれが人為的な妨害によるものなら、単に相手が私より優秀な魔術師だっただけの話」
妹は表情に悔しさをありありと滲ませながら、そう呟いた。
魔術に最強などあり得ない。それは幼い頃から彼らの父であり師でもあった人がことあるごとに口にしてきた言葉である。どんなに強い魔術であってもそれを凌ぐ術を作り出すことは理論上不可能ではない。彼はそのことを常に肝に銘じていた。そして、驕らず鍛錬を続ける。それこそが魔術師のあるべき姿だと。
父の教えが妹にきちんと伝わっているのを感じて、男はやや安堵を感じつつ、しかし声には依然として緊張を保ったまま改めて訊ねた。
「で、消滅と隠蔽、お前の予想で良いから確率的にはどれくらいだ?」
「そうですね……、恐らく九割方は隠蔽でしょう」
「なっ!?」
男の驚きの声が上がる。
「驚くことではありません。兄様だってあの魔力反応の中身については聞いているのですから、冷静に考えれば私と同じ結論に達しますよ」
「そう言われても……、お前の索敵から巨大な魔力反応を隠蔽するんだろ? そんなヤツがそうホイホイいるなんて信じたくないな」
苦り切った表情で言う男に、しかし妹は不思議そうな表情を返すばかりだった。「何を言っているのです?」と首を傾げた彼女は、そのままなんでもないことのように続けてきた。
「モノがモノです。普段は動かないような大物が動いていても何らおかしなことは無いでしょう?」
「ん……、それはそうなんだが……」
何せ、別任務に派遣されていた二人を呼び戻してまでわざわざ彼らをこの地に派遣するほどのことだ。協会も今回の件には慎重になっているのがありありと見受けられる。
「勿論、そうでないに越したことはありません。けれど……、もし最悪の可能性が進行中だったとしたら、それと戦うのは私たち一族の使命です」
「俺だって分かってるよ。その為だけに今日まで無茶な訓練させられてきたようなもんだからな」
「はい。だから、きっとどんな大物魔術師が敵でも大丈夫です。何せ、私と兄様が組んでいるのですから」
そう言って笑顔をほころばせる妹の肩が少し震えているのが、男には見えてしまった。
本来なら自分が彼女を励ましてやらねばならない筈なのに、いつの間にか場の空気を奮い立たせる役を彼女に押しつけてしまっていた。
こんなことでは兄失格だ。そう自嘲気味に首を振って、ひと言妹に言い返した。
「バカ。まだ最悪の事態だって決まったわけじゃないだろ」
「あはは、そうですね」
場の空気が一瞬緩む。しかし、この世界に居る神は意地悪なのだろう。
一瞬の後、何かを感じ取ったのか彼女の表情が再び緊張にこわばった。
「兄様……、少し遠くなのですけど、移動している妙な魔力反応があります」
「妙な魔力反応?」
「はい。……ちょっと信じられないんですけれど、どうも《あちら側》の存在としか思えない魔力パターンです。それが……、例の村の方へ向かっています」
彼女の言葉に、一瞬にして思考が固まる。
彼ら二人の間で、この状況で、例の村と言った場合、それはあの村以外にはあり得ない。人外の者たちが住まう、敬遠したくもあるが、場合によっては頼らざるを得ないあの者達の、村。
《あちら側》の存在が例の村へと向かう。その事実に明快な一つの解を見いだせてしまう自分たちが恨めしい。
「まさか、出てきたのか?」
口の中が乾くのが否応にも感じられる。喉がその事実(こと)を発音するのを拒否するかのように痺れる。全身の細胞が恐怖に縮こまり、推測されるその事実を否定したがる。
「いえ、ただの魔獣かも知れませんし、とにかく行ってみましょう」
その言葉に顔を上げると、妹は既に背中を見せて走り出していた。薄桃色のローブが森の緑の中へと溶けてゆく。
「……全く、いざというときに頼りにならないアニキだな」
結局は、妹に引っ張って貰うばかり。
自嘲の笑みを浮かべると、頬を叩いて気合いを入れ直す。このまま彼女一人に行かせると、本当に兄の面目丸つぶれである。
男もまた駆け出し、緑の中へと吸い込まれていった。

空気は重さがある。何故なら空気も無数の粒子から出来ているからである。
鬼の首でも取ったかのようにまことしやかに謳いあげる新聞の記事を一通り眺めて、シャルシュ・ワイゼンは溜息をついた。
その特集記事の見出しには、ご丁寧なことに「大発見」とまで銘打たれている。一般大衆への媚びがそこかしこに見られる、いかにも世間の話題に乗っただけの上っ面の記事だった。
曰く、空気の粒子が見えないのは目に見えないほど小さいからである。
曰く、暑い日は空気の粒子が激しく体にぶつかってきているから暑いのである。
曰く、風は空気の粒子が沢山あるところから少ないところへと粒子が流れる現象である。
記事の中で取りあげられているいくつかの現象はそのどれもが身近なもので、それぞれに対して簡単な言葉で解説がつけられている。
なるほど、どれも確かに空気が目に見えないほど小さな粒子であることを認めれば矛盾なく説明することが出来る。
記事はあまり深い内容にまで立ち入ることはしていない。あくまで表面的な内容ばかりで、専門家の目から見れば取るに足らない記事に違いないだろう。
しかし、インテリぶって蘊蓄を披露するには十分すぎる。
故に、このような記事が世間で色々ともてはやされ、巷の口を賑わす事柄になるのである。
そう考えると。
「……はあ、人間って、羨ましいよな」
改めて、シャルシュは溜息をつくのであった。
そう、羨ましい。
記事の内容自体は高度でもなんでもない。むしろシャルシュの持つ知識に照らして見ればあまりにも当然のことしか言っておらず、今更何をこの記事は騒いでいるのか、と言う感すらある。
彼が羨ましがっている点は他にある。
もう一度記事を上から下まで斜めに読み流して、しばしの間考え込む。思考時間にしておよそ十秒ほどだっただろうか。シャルシュは思い切ったようにその記事を新聞から切り抜くと、手近にあった大きな紙束をテーブルの上に置いた。
大判の紙を何十枚も重ね、その一辺を紐で綴じてある。ノートと言うにはあまりにもお粗末な紙束。その束をぱらぱらとめくり、無地のページを開くと先ほど切り抜いた記事の裏に糊をつけて、ぺたりと貼り付ける。
ペンを手に記事の隣に何事かを書き込むと、再び紙束をめくってもとあった場所へと戻した。
よくよく眺めてみるとその紙束が置かれた場所には既に似たような紙の束がずでんと、人の腰ほどの高さにまで積まれている。それも、十やそこらというわけでは無さそうだった。
想像するまでもない。これらにも先ほどシャルシュがやったのと同様に新聞の記事――それも科学にまつわる記事ばかりが切り集められているのである。言わば手作りスクラップブックと言ったところだろうか。そのスクラップブックの塔を眺めてシャルシュはつまらなそうな顔をする。
何故、人間はこれほどまでに科学を好むのかと。
何故、人間はこれほどまでに大衆に科学を広めるのかと。
何故、自分は人間に生まれてこなかったのかと。
肩まで伸びた髪の毛を手で梳いて、ひと束を目の前へと持ってくる。日に透けるような薄い色の髪の毛は、女神の愛の証と言われている白金の色。世界を満たす白い魔力が浸透した
こればかりではない。顔を上げた瞬間に不意に窓に映る自分の顔が見えて、その長く伸びた耳に一層憂いが増す。
やはり、外面だけはどこまでもエルフだ。その思いがシャルシュの心から碇のように投げ落とされ、どこか深く暗いところにきっちりと彼の精神を係留する。
「人間だったら良かったのに」
小さい頃から何度願ったか分からないその思いを改めて口にしたところで、唐突に叶うはずもない。
実際に、村を出て人間の社会に混ざったらそれなりに順応できたはずだ。彼の持つ事情を説明すれば理解してくれる者も現れただろう。だが、それをすることは出来なかった。
勿論、周りのエルフ達がさせてくれなかっただろう、ということもある。シャルシュの後見人を自称する隣人など、実際に相談してしまったら最期どんな手段でこの村にくくりつけられるか分かったものではない。想像するだに恐ろしい。
しかし、最大の理由はきっとそこではないのだ。
結局、自分は何も出来ない。
やりたいことは頭に浮かんでは消えていくくせに、いざそれを実行するとなると指先一つまともに動きやしない臆病者なのだと。
脳裏を埋めていくネガティブな思考に溜息をつく。
「けれども、それが現実だよな」
溜息をついて積み上げたスクラップブックを眺めた。
定期的に人間の街に行商に行く者に頼んで買ってきて貰った新聞。それを読んで気になった記事をスクラップしていったものがうずたかく溜まってきた。が、しかしその記事に出ている場所を見に行くなどと言うことは今までしたことがなかったし、これからも無いだろう。
苛立ってスクラップブックの山を乱暴に崩したらいっそほんのひとときでも鬱憤は晴れるだろうに、そうすることさえない。自分でも呆れるばかりのチキンぶりだ。
「……なんで、僕は今生きて居るんだろうな」
そんなことを呟きながら椅子の背にもたれ、ぐーっと後ろに体を倒していき。
「生きていることに特に理由なんて無いわよ」
眼があった彼女にそう言われた。
「……エリアさん。勝手に入ってくるのはやめてくださいって言ってるのに」
「気の滅入るような呟きが中から聞こえてきたら、誰だって入ってくるわよ」
そう言ってエリア――エリアネル・テルミチェットは大袈裟に肩をすくめた。
シャルシュが体を起こして向き直るのと同時に、その肩がポンと軽く叩かれる。
「アンタはまた下らないことを考えてたわね。いつも言ってるけど、そういう生き方って肩こるわよ。もっと楽に、楽しく生きるってことがどうして出来ないかな」
「……僕が僕である限り、多分無理でしょうね」
「まあそう言うとは思ってたけど」
既に幾度となく繰り返されたやりとりである。一言一句まで違わずに予想通りの言葉のやりとりには、既に双方とも半ば意地になっている節があった。
そして、シャルシュがこの言葉を紡げばエリアが決して二の句を告げなくなることも、いつも通りである。
「……普通のエルフには、……エリアさんには、分かりませんよ、この感覚は」
エリアが悔しそうに歯がみするのを視界の端に捉えて、シャルシュは少しばかり溜飲が下がるような気がした。
いつもいつも、二人のやりとりはこの言葉で決着を迎えるのだ。これ以降二の句を告げないエリアは毎回何か言いたげな表情のまま引き下がっていく。
だが、今日はいつもと少し異なった。
「……シャル、アンタのそれは反則だって」
「でも、事実ですから」
エリアが言い返してきたことに若干の驚きを覚えつつも、シャルシュは変わらぬ拒絶の態度を返した。
この議論に平行線以外の結末は無いはずだ。それは今まで何十回、何百回と繰り返して二人の共通認識になって――それでも未だにエリアは何度となく同じような問いかけを繰り返してくるのだが――シャルシュが他のエルフ達に迎合する様なことをしないというのはもはや決まり切った事実となりつつあるはずだった。
だが、エリアの言葉はこれまでの共通理解を突き崩すようなものだった。
「そりゃ、アンタが他のエルフ達と違うってのは事実だよ。だけど、だからってそれを理由にして生きることに疑問を覚えたり、他のエルフ達との交流を断ったりするのは逃げだよ」
「逃げちゃいけないんですか?」
傷つくのが嫌なら逃げるしかないじゃないか。
シャルシュには他の術がなかった。
エルフの村に異常な自分が独りぼっち。
小さい頃にその状況に突如として放り込まれ、周りからは奇異の視線を浴びせられ、幼い心が自己防衛の為にどうにか編み出したのが今の生き方だ。
すなわち、集団の中に於いて孤独に生き、外界との接触を必要最低限に留める。
そうすれば傷つくこともないし、日々を安穏と暮らしていける。
「でも、逃げてちゃ日々が楽しくないわよ」
エリアの言葉は残酷なまでに正鵠を射ていた。
村の中にあって、外には人の声と日の光が溢れているというのに、自分はいつまでも家の中に閉じこもっているばかり。書物とばかり向き合う日々は感情を摩耗させていき、「楽しい」という概念すらをも薄れさせていく。
それはシャルシュが日々感じていることに他ならなくて。
だからこそ、どうしてもその言葉は否定しなければならなくて。
「楽しいですよ」
嘘をついた。
わずかにひと言、嘘をついた。
ただのひと言だけだった嘘を呼び水に、言葉は冗談みたいに次から次へとあふれ出してくる。
「僕は、こうやって色々な知識を学んで、日々を豊かに暮らしていける。単に僕とエリアさんの価値観が違うっていうだけで、僕の生き方を否定しないでくださいよ」
言葉の一つ一つがどうしようもなく乾いていて、ひと言口にする度に喉がからからになっていくのを感じた。
駄目だ。これ以上言ったら駄目だ。
理性で分かっていても口は止まらない。言えば言うだけ自分が傷つくって分かっているのに、一度切れた堰はそう簡単にはふさがってくれなかった。
「……ほう、そんなことを言うのね」
ゾッとするほど冷たい声に顔を上げると、エリアが笑顔でこちらを見つめていた。
爽やかな風を思わせる、無邪気で明るい笑顔。しかしシャルシュは知っている。このエリアネル・テルミチェットという人は怒っている時ほど笑顔になるのだと言うことを。
「そんな顔をされても……」
「いや、別に怒っているわけじゃないんだけどね」
誰がどう聞いても嘘にしか聞こえない言葉を、エリアは紡ぐ。
言葉の裏に塗り込められた怒気が背筋を凍らせる冷気となってシャルシュの耳を撫でていく。
「昔、余所から来た人が言ってたんだけどね……、限りなく微妙な嘘は誤りに近いんだって」
「……」
どういう意味かとシャルシュが問いただそうとするのよりも先に。
「今のが誤りであって欲しいわね」
苦笑しながら窓の方へと歩いていき、窓枠へと手をかける。
そのままばあんと窓を開け放つと、エリアはこちらを振り返った。
その顔に先ほどまでの重苦しさは一切無い。一体どうすればそこまで明るく笑えるのかと問いたいほどのすがすがしい笑顔で、シャルシュの方をすっと見つめる。
白銀の長髪が風にふわりと踊った。
「重たい話はここまで。そもそも私がここに来たのは、あんな肩のこるような話をする為じゃなくて、別の目的があったんだから」
そう言うエリアの顔はどこか悪戯めいていて、シャルシュの脳裏を嫌な予感が雷鳴のごとく駆け抜けた。

「この倉庫を造った人はバカですか?」
シャルシュは目の前でぴっちりと閉じられた木製の扉を見て溜息をついた。
屋外に吹きさらされている倉庫であるはずなのにその扉は磨き込まれているかのようにつややかで、爽やかな春先の陽光に鈍い光を反射している。黒檀作りだろうか、重々しい色合いの扉は非常に密度が高いように見える。
一応村の宝物庫という名目の倉庫であるが、その中に何が仕舞われているのかシャルシュは知らなかったし、興味もなかった。
重要なのは、今その扉が何故か開かなくなったらしく、何故か自分がそれを開ける為にわざわざかり出されているということである。
妙に威圧感のある取っ手にそっと手をかける。
ぐっと引っ張ってみてもぴくりとも動かず、開く気配などこれっぽっちも見受けられない。
「一応念のために聞いておきますけれども、この扉、鍵は開いているんですよね」
「当たり前じゃないの。いくら何でも鍵の閉まった扉を無理矢理開けるなんてことはしないわよ」
そう答えたのはエリアである。シャルシュの後ろに立って、困ったような視線を扉に向けている。
「いやー、冬払いの祠の手入れに行くのに肝心の道具を忘れてることに気付いて、いざ倉庫へ取りに来てみたら開かないのよね」
冬払いの祠というのは村の外、徒歩で数時間の位置にある祠のことで、シャルシュはよく知らないのだがどうやらこの村にとって重要な役割を担っている場所らしい。エリアはとある一件以来そこの管理人のような役割を担っているのだが、それはまた別の話である。
「男の人何人もで協力したら開くんじゃないですか?」
「そうなんだけど、なんだか恥ずかしいじゃん。扉の一つも満足に開けられないなんてさ」
そう言いながらエリアは頬をぽりぽりと掻いている。日頃から自らの所属する森林警備隊【森の翼】最強の森林レンジャーを自認するエリアにとっては、たかが扉を開けるくらいで他人の手を借りるというのは、どうやらプライドが許さないらしい。
ならばシャルシュに助けて貰うのは良いのか、という疑問を眼で問いかけたところ。
「いや、アンタなら力業じゃなくて頭の方で解決してくれるかなー、なんて。頭脳が要ることなら私が少々出来なくても仕方ないしね」
などと言うことをあっけらかんと言う辺り、エリアのプライドは腕っ節の面に限定されているらしかった。
或いはこれは自分の頭脳が認められていることと素直に喜ぶべきなのかも知れないが、しかしこのように軽い調子で言われてしまうとどうにも素直に納得できないシャルシュであった。
「はあ……。それにしても、この倉庫……、一体何考えて作られているんだか……」
倉庫の周りを歩きながら、その壁や床の作りを検分する。どこを取ってもとても木材で作られているとは思えない密な作りをしていて、ネズミの子どころか風すらも通さないような堅固な倉庫となっている。
が、今回の一件に関しては、その密閉の良さが倉庫をがっちりと封殺する原因となってしまったようである。
「今更ですが……、通気口すらないのはどうかと思いますよ」
「あー、そう言えば確かに、この倉庫の中っていつも空気悪いわね。でも年に何回かしか開かないし良いんじゃない?」
「いや、今回ここの扉が開かなくなった原因の一つですから、良くはないでしょう」
溜息をついて扉にもたれかかる。
たわむことも、軋むこともない。本当に丈夫に出来ていて、そして密閉されている。その木製の扉からひんやりとした感覚が伝わってきた。
「どういうこと? なんで通気口がないと倉庫の扉が閉まるの?」
「エリアさん、昨日のお昼にこの倉庫に来たんじゃないですか?」
質問に質問を返した。
エリアは少し嫌な顔をしたが、もしこれでエリアの答えがイエスであるならばすべての物事にそれなりに説明がつく。
少々馬鹿げすぎていて信じたくないが。
「……来たわよ。いくつか祠の手入れ用の道具を取りにね。でもって、その時取り忘れたものを今取り出そうとしてるんだけど」
いぶかしげなエリアの視線を軽く受け流して、シャルシュは納得したように頷いた。
「じゃあ、問題は解決です。放って置いたらこの扉はその内開くようになりますよ」
「なんでよ?」
「中との気圧差が元通りになるからです」
言って、シャルシュは扉の前にしゃがみ込んだ。
扉と床の間にはこれっぽっちの隙間も開いていない。指をぺろりと舐めて扉と床の境目辺りに置いても、これっぽっちも空気が流れていないのだ。
それは扉と屋根の間にしても同じだった。他の箇所を一通り見ても、この倉庫はどうやら完全と言っても過言でないくらい気密されているらしい。はっきり言ってしまえば、異常だ。
「昨日のお昼は随分と気温が高かったですからね。エリアさんがここへ立ち入った際に中の空気があたたかく軽い空気と入れ替わったかなにかしたんだと思います」
「それで、なんで今扉が開かないのよ?」
「昨夜は随分と冷え込みましたからね、中の空気は存分に冷やされたことでしょう。だけどこの倉庫は気密が良いですから、中の空気が冷やされて嵩が減っても外から空気が補充されることはなかった。だから、気圧差が生まれて扉が開かなくなったんです」
「……ごめん、全然意味が分からない」
エリアは困ったような表情で首を傾げている。
が、別にシャルシュだって分かって貰おうと思って説明したわけではない。ただ説明さえしておけば、あとで色々としつこく訊かれるのを避けられるだろうと思っただけの話である。
「要するに、中の空気が扉を押す力が弱いから、外から扉を押す力が強力になりすぎて居るんですよ。中の空気が暖まればそのバランスが崩れて、また扉が開くようになるっていうことです」
「ふーん、で、いつ頃になりそう、それ?」
「さあ……、そこまでは僕には分かりません」
今はまだ昼前。気温が上がり切るには随分時間がある。
「私は今この扉に開いて欲しいんだけど……、なんか手はない?」
面倒くさそうに頭を掻くエリアに、シャルシュは小さく溜息をついた。
「待つってのじゃだめですか?」
どうせ駄目だという答えが返ってくるのだろうと半ばあきらめにも似た感情を覚えながらシャルシュは訊ねた。
「そう訊くってことは何か手はあるんでしょ? さっさとやりなさいよ」
「はあ……、わかりましたよ。ただ、成功するかどうかは分かりませんからね」
そう言いながら扉の前にしゃがみ込み、床板に手を当てる。
「失敗したら爆発する、とかじゃないわよね」
「まさか。その辺は多分大丈夫です。……というわけで、少々我慢していてくださいね」
エリアが疑問を挟む暇がないように高速で魔術式を展開。
空間に充満する魔力を括る魔術という名の取り縄を脳裏に描く。その縄を辺りに放り投げて、適当な量の魔力を周囲に縛り付けた。
魔力から顕現させる属性は風。
自分とエリアを含めた扉の周囲の空気を圧縮し、擬似的な壁を作る。空気は空間を自由に漂う粒子の集まりであり、本来はこのように特定の形に縛ることなど不可能だ。だが、それを可能とするのが魔術。この世界に生きる一部の生命にのみ許された禁断の術。
魔力の強制力にものを言わせて空気の粒子を空中に完膚無きまでに固定する。
これで倉庫の扉を包む一部の空間が擬似的な密室になったことになる。それも、気密は考え得る限りで最高レベル。空気の抜ける余地はない。
あとは、この密室内の気圧を下げてやれば扉を閉じている力は消滅する。
「減圧開始」
空間に満ちる空気のうち約三分の一を無理矢理地面に押しつける。要は先ほど壁を作った時と同じことをするだけだ。空気を構成するあまたの粒子を地面に這わせて、実質的な体積をほぼゼロに近づける。すると元々それらの空気があった空間まで残りの三分の二の粒子で満たさなければならなくなる為、この密室内の気圧は約三分の二に減少する。
つーん。
強烈な耳鳴りを感じて、つばを飲み込んだ。
ぐりっ、と脳みそを直接叩くような鈍い音がする。
それと同時に。
きぃ
小さな軋みを立てて、扉がこちらへ少しずつ動き出していた。
シャルシュは心の中で小さなガッツポーズを取りつつ、魔術を調整してそのまま低気圧状態を維持する。
その中で扉が少しずつこちらへと引っ張られてきて。
「……やめろって言ってるでしょうが、この馬鹿シャル!」
ゴンという鈍い音とともに、エリアの鉄拳によってシャルシュの頭上に星が舞った。
強烈な痛みに視界がぐらつき、とてもではないが魔術の維持など出来るはずもなくその場に倒れ込む。風によって作られていた壁が一瞬にして瓦解し、辺りの気圧が元へ戻る。
ズキズキと痛む頭をさすりながら、エリアの方を見上げた。
「……ぃつ、何するんですか!?」
「それはこっちのセリフよ。アンタこそ、何やってるのよ? 耳がキンキンして仕方ないじゃないの」
そう言いながら長く伸びた耳を押さえて、エリアは顔をしかめる。その様子は冗談でもなんでもなく本当に苦しそうで、シャルシュは若干の違和感を覚えた。
「エリアさん、大丈夫ですか?」
「大丈夫じゃないっての。急に酷い耳鳴りがしだすんだもん。一体何の拷問かと思ったわよ」
「酷いって、そんな大したものでも無かったと思うんですけど……」
シャルシュの言葉にはエリアの厳しい視線が返された。よく見ると目尻にはうっすらと涙がにじんでいるようにも見える。それほど酷かったのだろうか。
あれだけ気圧が変化すれば確かに耳鳴りはするだろう。しかし、いくら何でもエリアの反応は大袈裟すぎると思うのだ。自分もいくらかの耳鳴りはあったが、つばを飲み込む程度で我慢できたのだし。
と、そこまで考えたところで、あることに気付く。
「……そうか、エリアさんは普通のエルフだから」
途端に胸の中に影を落とす異様な疎外感。
エルフは自然に愛され自然と一体となることで命を謳歌する種族だ。その感覚は常に自然と同調し、それ故に敏感である。だから、先ほどの気圧差もエリアにとってはシャルシュの何倍もに感じられたのだろう。
こんな些細なところにまで、自分がエルフとして異端であるという事実が出てくる。そのことがなんだか哀しくなる。
日々を暮らしていくだけで募っていくどうしようもない疎外感。悪意があればまだ恨むことも出来ように、今のエリアには悪意など欠片も存在せず責めることさえできない。
そうして俯いているシャルシュを見とがめて、エリアが肩をすくめた。
「何を辛気くさい顔してるのよ。別にそんなにアンタを責めてるわけじゃないわよ。ここまでやって扉が開いてなかったら……話は別だったかも知れないけどね」
そう言われてポンと肩を叩かれて。
顔を上げたシャルシュの視界にぽっかりと口を開けている倉庫の扉が入ってきた。
魔術自体は途中で途切れさせられたが、扉を開けるという一番大本の目的自体はどうにか達成できていたらしい。
「アンタのお陰ね。まあ、さっきのはこれでチャラってことにしてあげましょう」
「……あ、ありがとうございます」
何故自分が礼を言っているのだろうか。助けたのは自分で、礼を言うのはエリアの筈なのに。
そんな疑問が脳裏をよぎるが、今は些細なことに思えた。
エリアが自分を必要としてくれて、自分がそれに応えることが出来た。そのことが温かいものとして胸の内を満たしていくようで、嬉しかったのだ。
「……また、何かあったら呼んでください」
そう口にしてしまったのは、だから一時の気の迷いで何かの間違いで、そうは言っても後悔は常に先には立たないからどこまでも果てしなく後悔なのであるが。
こんなことを言ってしまったら最後、これから一体どんなことに狩り出される羽目になるのか。
想像してシャルシュが顔を青くした時には既に遅く、エリアはこちらへ極上の笑顔を向けていた。
「ありがと。しっかり覚えとくわ」
血の気の引く音が聞こえた気がした。
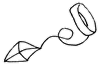
「……なにも、ない?」
焦っている時ほど気が動転して、現実とは違う景色を見てしまうものなのかも知れない。そう思って、ジグ・ムーシカは一度深呼吸をした。
だが、目の前の景色はそれで変わったりすることもなく、彼の目の前には相変わらず平和な村の一角が広がっているのだった。
「変ですね。さっき見つけた反応はどう見てもこの村にやってきているんですが」
ジグの隣では彼の妹のアリア・ムーシカが手元の地図に視線を落として不思議そうな顔をしている。アリアの手にある白い紙の上では魔力が黒い線となって地形を描き、その中心に闇のように深く沈んだ光点が明滅している。
そこが、今彼らのいる場所。
村。
名前などはじめから無く、その住人達が自分たちの住む場所を指して呼ぶ時はただ「村」と呼ぶ。
世界で最も古くから存在するエルフの集落は自分たち以外の人、すなわち人間であるとか、或いは余所へ出て行ったエルフ達の集落との交流を持ち始めても自らを以て名付けることはしなかった。
それは強情なのかなんなのか。ともかく、彼らは自らの集団を以てエルフ唯一の集団と任じ、わざわざ名乗ることはしないのだった。
いや、事実名乗る必要など微塵も存在しないのだが。
最近になり、ようやく人間達が不便と言うことでこの村に名前をつけた。ハルヨビと。
が、その名前は当の村の住人達には全く認知されていないので、この場で使うことはほとんど無いだろう。
そのハルヨビの村の入り口に立って、ジグとアリアの兄妹は半ば呆然としていた。
およそこの世のものとも思えない《あちら側》の世界由来の魔力反応をアリアが感知したのが十数分前。そこから全力で駆けてきて、村がどのような惨状になっているかと思ってみれば全く何も起きていないに等しい。
村の中ではエルフ達が普通に出歩いており、時折呆然と入り口に立ちつくすジグ達の方へと奇怪なものを見るような視線を向けてくる。
その長い耳。その日に透ける
彼らがこの村の住人のエルフであることは、疑いようのない事実のようだった。
わけが分からない。まさかエルフの村に何食わぬ顔をして《あちら側》の世界の住人が紛れ込んでいるとでも言うのか。
「アリア、反応はどこから出ている?」
「えっと……、あっちです」
アリアの指さす方向、村の奥へと続く道へと躍り込むと、道行くエルフ達が奇異の視線を向けるのにもかまわずにひたすら走る。
もしかしたら今はまだ潜伏して何らかの準備をしているところなのかも知れない。
エルフ達は魔力を操ることには秀でていても、小さな魔力反応を検知したりすることは不得手だと聞く。ならば自分の村に《あちら側》の存在が紛れ込んでいたとしても気付かないことは充分考え得る。
急げ。こうなったら一刻でも早いほうが事態を速やかに収めることが出来ることになる。
「兄様、少し待ってください!」
後ろからアリアの声が聞こえてくる。なんだかこちらを止めようとしているらしく、焦り混じりに聞こえた。
一体どうしたというのか、一度振り返って確認すべきかとジグが足を緩めた瞬間だった。
「人間よ、ここより先へ何用か?」
鋭い声と、のど元に向けられたひんやりとした殺気。
背筋を寒気が駆け上るのよりも先に、本能的にジグは後ろに飛び下がっていた。
それらを向けてきた相手と一瞬のうちに距離をとった。のど元に手を当てる。直接触れられたわけでもないのに、急速冷凍をされたかのように血の気が通っておらず、ごくりとつばを飲み込むと生気が戻ってくるような気がした。
「もう一度訊こう。人間よ、ここより先へ何用か?」
そう訪ねる男の手には何も握られていなかった。ただ左手のみが水平に掲げられており、それが先ほどジグののど元に迫ったものだろう。
痩身の身から放たれる殺気の凄まじさはそうそう目にかかれるようなものでもないが、それでも恐らくまだ本気の半分も出してはいないことが伺える。
こちらをうろんげに見つめる目元には、未だ涼しさが消えていない。
「なに、
相手の涼しい目元に少し腹が立った。
お茶を濁すべく、ジグは敢えて軽口を叩いた。
「大したことの無い用ならば帰れ。そもそも人間がこの村に一体何故居る?」
「居ても良いだろ、お隣さん?」
「……人間風情が舐めた口を。そのように呼ばれる所以はない」
男は相変わらずクールな表情を崩さないまま、こちらを睨み付けている。その視線に先ほどよりも幾分か殺気が上乗せされているのは気のせいではないだろう。
「兄様、何をわざわざもめ事を起こそうとしているのですか?」
ジグの後ろから追いついてきたアリアが呆れた様に頭を押さえて言った。
今回ばかりは本当に喧嘩を売っていた為、なんの弁解の余地もない。
「いや、噂に名高き【森の翼】のレンジャーの腕がどれほどのものか、いち騎士として気になってな」
そう言いながらにやにやと笑んで男の方へ顔を向けると、彼は小さく肩をすくめて溜息をついた。
「貴様の様な軽い男にわざわざ乗せられるほど安くは無いつもりだ。残念だったな、人間」
「なんだと!?」
一瞬で沸点に到達し、一足飛びに殴りかかろうとするジグの肩が、わしっと強烈に掴まれる。
振り返った先ではアリアが怒りに肩を振るわせて右の拳を握りしめていた。
が、その怒りは兄のそれとは随分性質の違うものの様だった。
「……そもそも挑発ももってのほかですが……、なんで喧嘩を売りに行って買わされてるんですか、兄様は!?」
「あ、いや、その……、すまん、つい……」
自分に向けられる妹の怒りにジグがたじたじとなっていると、その頭上にからからと乾いた笑い声が降ってきた。
見ればいつの間にか男の後ろに、まだ少年と言える程度のエルフがやってきていた。
「オーウェルさん、こんな奴らさっさと追い出しちゃえば良いんですよ。でなきゃ、僕らはいつまでたっても巡回に行けないじゃないですか」
少年はそう言いながらジグ達の方を指さしてくる。
オーウェルと呼ばれた男は、面倒くさそうに頭を掻いて顔をしかめた。
「万に一つでもこいつらの用事が本当に急務だったとして、シラムに責任がとれるのならそうしても良いんだがな」
「え、責任問題に落としちゃうのは反則ですよ!」
シラムと呼ばれた少年は、おどけた様に大袈裟に肩をすくめる。さらに、ジグ達の方へとちらちら視線をやりながら。
「大体、この村へ来た人間があっちに用事なんてあり得ないでしょ。ってことは騎士なんて名乗ってても大方宝物庫狙いの泥棒なんじゃないですか?」
「いや、そう決めるのは性急に過ぎる。村の治安を預かるものとしては、やはり……」
いつの間にか二人で話を盛り上げて言ってしまうオーウェルとシラム。
そのやりとりの中に、どうにも見過ごせない言葉が混ざっていたのが聞こえてアリアはこめかみを引きつらせていた。
熱く語り合っている二人の目の前まで行き、胸の前で拳を握りしめる。
二人が不思議そうに視線を降ろしてきたところでキッと睨み付けた。
「訂正してください」
「何をだ?」
不思議そうな表情で訊ね返すオーウェルとシラム。その二人に対して、アリアは飽くまで憮然とした表情のまま言った。
「私たちは騎士です。そのことに誇りを持っています。それをたとえ話でも泥棒呼ばわりするなど言語道断。ヘクセン魔導協会所属魔導騎士アリア・ムーシカはここにあなた方の訂正と謝罪を要求します」
凛とした様子でまくし立てるアリアの様子に思わず呆気にとられているオーウェルとシラム。
先に我に返ったのは、幸か不幸かシラムであった。
露骨に顔をしかめてオーウェルの前へと出ると、アリアの正面に立ちその顔を睨み付ける。頭一つ分ほどシラムの方が身長が高い為、アリアを見下ろす形になった。
「騎士だから、なんだって?」
「おい、シラム……」
遅れて我に返ったオーウェルが止めに行くのも手で遮り、シラムはアリアへ怒気を孕んだ視線を送る。
それを正面から受け止めて、アリアはシラムを見上げた。
「まずは訂正を、それから謝罪を要求します。我々騎士の誇りを踏みにじるようなまねは見過ごせません」
「こちとら思ったことを口にしたまでですが……。まさか騎士様ってのは他人の考えまで縛ることが出来る権利をお持ちなですのか? それは知らなかった」
大袈裟におどけるシラムを余所に、アリアはその場から三歩ほど下がる。丁度、対面する相手に対して何かをしようとしても一呼吸必要になる程度の間合いを開ける。
どう見ても、相手からの不意打ちを防ぐ為に距離を取ったようにしか見えない。
二人の間に不自然に開いた空間を見て、シラムが失笑する。
「騎士様でもビビるもんなんですね」
「いえ。単に見上げるのが疲れただけですから、お気になさらずに」
しれっとした様子で首の後ろを揉んでいるところを見ると、恐らく冗談でもなんでもなくアリアにとっては大まじめな話なのだろう。
そこが却ってシラムの神経を逆なでした。
「えっと、そうそう、言動の話でしたよね。勿論、他人の思考を縛る権利なんて誰にもありはしません。考えるだけなら自由。但し、それを他人の耳のあるところで口にして良いか、というのは別の問題です。果たして面と向かって相手を侮辱する様なことが許されるのかどうか……。エルフの文化は知りませんが、私たち人間の間ではそのようなことは許されませんから」
つまり、先ほどの言葉を訂正しなければエルフ全体の品位を疑わなければならなくなる、ということを遠回りに言っているのである。
長々と詰まることもなく紡がれる言葉を聞いているうちに、シラムの顔が露骨に紅潮してくるのが分かった。
「……シラム、お前の負けな」
シラムの後ろで、ぽつりとオーウェルが呆れた様に呟く。
空気の抜けた風船の様に怒気が萎んで、みるみるうちにシラムの持つ雰囲気がだれるのが感じられた。
「ああ、はいはい、分かりました。どうも僕が悪かったです。事情も知らずに泥棒呼ばわりして悪うございました」
「良かった。言葉が通じて」
アリアがほっと笑顔で胸をなで下ろして。
かちん、と。
空気が凍る音が聞こえた気がした。
アリアは決して悪気があって言ったわけではない。暴力沙汰にならずに事態が収拾しそうで良かったと、そう言う思いからでた呟きだった。だが、口から出た言葉が良くなかった。
今の状況でそう言われると、エルフには普通は言葉が通じないと言われているようなものだ。
そんな侮辱を受けてまで、シラムが我慢をし続けている理由はもはや無かった。
「……誇り云々の話はさておき、お前らが本当にさっき名乗った様な騎士だっていう証明はまだだよな。それに、肝心の目的も聞いていない」
ぽつり、とシラムが呟いた。俯いて地面を見ているのか、表情はよく見えない。
「ああ、先ほど兄様が妙な喧嘩をふっかけてしまったことは謝りますし、私たちがここへ来た理由もお話しします」
「そんなことはどうでもいいですよ」
シラムの声は底冷えする様な暗さに満ちているのだが、アリアはそれに気付かないのか笑顔のまま。
「へ? あ、もう通っても良いって言うことですか?」
「違うっての。騎士だとかなんだとか、証明して貰うのには強さで見せて貰うのが一番手っ取り早いだろ!」
そう言って、腰に下げていた剣に手をかける。
「お、おい、シラム!?」と慌てた声で制止をかけようとするオーウェル。
「え、な、なんでそんなことになるんですか?」慌てた様子で二歩三歩と後退するアリア。
制止など耳に入った様子もなく、シラムが身に纏う気迫が渦を巻き、辺りの魔力が一斉に波立ち始める。
剣を抜きはなった後には、先ほどまでとは比べものにならないほどの威圧感を身に纏った一人の戦士がいた。
辺りの大気が無秩序の魔力の奔流に飲まれて揺れ、風が巻き起こる。
エルフは魔力を操ることに長けている民である。それは一般的には多量の魔力を一度に操れるという意味で解釈して概ね間違いはないだろう。だが、これほど沢山の魔力を操れるエルフというのもそうそういるものではない。アリアは目の前の少年が放つ威圧感を検分しながら、そう感じていた。
間違いない。今まで出会ってきた様々なエルフと比べても、目の前の少年の実力は一級品だ。純粋に魔術の力比べをすれば、恐らく自分など叶うべくもない。
だが。
「そんなものですか」
と、虚勢でもなんでもなく、アリアは言い切った。
シラムの纏う威圧感もどこ吹く風、巻き起こる風に揺れる髪の毛だけを少し手で押さえて、後は平然と安心した様な表情でシラムを眺める。
「いやいや、一瞬驚きましたけれども、要は貴方を倒すなりなんなりして納得させれば通して貰えるんですね?」
「人を馬鹿にした態度は相変わらずですか。流石は騎士様。でも、その余裕もいつまで保つか」
「とりあえず、貴方を倒すまでは保つんじゃないでしょうか?」
くすり、と軽い笑いを漏らすアリア。
シラムの近くで二人の様子を見守っていたオーウェルは、思わず声をかけないわけにはいかなかった。
「……あの、お嬢さん、こいつのことは甘く見ない方が良い。上司の僕が言うのもなんだが、僕より強いし半端な強さじゃない」
蚊帳の外に置かれているうちに毒気を抜かれてすっかり丸くなってしまった言葉をアリアは笑顔で受け止めて、丁寧にお辞儀をした。
「お気遣いありがとうございます。でも、大丈夫です。この程度ならどうにでもなりますから」
薄桃色の髪の毛を風に舞わせて、アリアはシラムの方へと軽く向き直った。その姿勢は適度に力の抜けた自然体。攻める気も守る気もとりあえずは見受けられない、ゆったりとした彼女の性格をそのまま見せている様な構えだ。
「騎士様、得物は出さないのか?」
「……必要ですか?」
言外に「貴方如きに」と言われている様な気がして、シラムの頬がひくつく。
が、ここまで来たらあとは冷静さも保っていなければ足下を掬われかねない。
小さくばれない様に息を吐いて、シラムは肩をすくめた。
「後で武器を出していなかったから、って言い訳されても困るんでな。見たところ剣は持ってないみたいだけど、なにかあるんでしょ? さっさと出してくれよ」
「うーん、騎士としてそんな行為はしないと誓っても良いのですが、真剣に望まれた勝負に手ぶらでお相手するのも失礼ですね。分かりました」
そう言うと、ローブの中におもむろに両手を突っ込んだ。
ごそっと一瞬動かしただけですっと出された両手、そこには左右の中指にキラリと輝く指輪と、そこから垂れたがった糸につられる形の宝石。
「振り子?」
「ご名答。さて、私の武器はこれです。というわけで、いつでも掛かってきてください。怪我をさせるつもりはありませんから、安心してください」
「……いちいち人を怒らせるのが上手いね、アンタは!」
そう言うと同時にシラムは駆け出していた。
およそ人の持ち得る加速力とも思えない。そのトップスピードは眼で捉えられるかどうか。恐らく何らかの魔力作用によって加速させているであろうスピードによって、二人の距離は一瞬にしてゼロとなり。
「はい、これで一回」
一瞬にして再び開いていた。
ずざざざざ、と激しい砂埃を立てて、シラムがアリアの後方、随分と進んだところで足を止める。
その剣は振り抜かれた姿勢のままで中に持ち上げられており、表情は驚愕に染まっている。
対するアリアはと言うと、涼しい顔をしてのんびりとシラムの方を振り返る。その様子は先ほどのシラムが駆け出す前と何ら変わらない。傷どころか埃一つついていないのではないだろうか。
その手を顔の前へと持ってきて、指で摘んだ小さな何かをシラムに見せつける様にして片目を閉じる。
果たしてそれは、シラムの服のボタンであった。木の実の殻からくりぬかれた茶色の小さな板を、アリアはすっと懐に仕舞う。
鼻歌さえ歌い始めそうな様子のアリアを見て、シラムは驚愕の表情をより一層濃くする。
オーウェルも二人の様子を見て目を見開いてはいるが、そうは言っても実際に剣を交えたシラムほど何が起きたか正確に分かっているわけではないから、その驚きなどシラムのそれと比べれば微々たるものだ。
現実を振り切る様に剣を一度大きく振り、シラムはアリアの方へと向き直った。
「い、今のは何かの間違いだ!」
「……まあ、先ほど言った様に他人の考えを縛る権利なんかないから、貴方がどう思おうと勝手なんですけれども、自分もだませないような嘘はつくべきじゃないと思いますよ」
「嘘なものか。今度は今みたいなマグレは無い」
「ははあ、そう来ますか。じゃあ、それはきっと嘘じゃなくて誤りですね。微妙な誤りは嘘に近いんです。……あれ、逆だったかな? 微妙な嘘は誤りに近い……?」
「真剣勝負の最中に、何を言っているんだ!」
裂帛の叫びとともに、シラムが再び駆け出す。
今度は先ほどの様に無計画な直進で斬りつけるのではない。アリアの手前で跳び上がり、彼女の直上にて剣を構える。瞬間、魔術により下向きの強風を吹き下ろさせ、一気に加速をつけてアリアに斬りかかる。
予想外の加速だったのか、一瞬アリアの目が見開かれる。
その眉間を剣が捉えたと思った瞬間――すなわち、寸止めをしようとシラムが剣の勢いを一瞬緩めた瞬間。
目の前にあったはずのアリアの顔が消えた。
え? と思う間もなく剣が地面に向かって急速に引っ張られる。シラムの意思に反して固い地面に思い切り切り込んだ剣が柄を通じて手に衝撃を与え、それと同時に首の後ろにトンとかるい刺激。
「二回目ですね」
「ちぃっ!」
地面に刺さった剣を強引に抜き取ると、声のした方へ振り回す。剣閃は虚しく空を走り、視界には遙か遠くに離脱したアリアの姿だけが映った。
「まだやりますか?」
ほほえみを浮かべてそんなことをしれっと問うてくるアリアは、人の良さそうな顔をしていて実に人が悪いと思う。
二人の戦いを離れたところから見ていて「ほどほどにな〜」などと軽く声をかけているジグにしてもそれは同じだ。
分かっている。
先ほどからのたった二回の交錯で、既にアリアの実力は自分のそれを遥かに凌ぐということは分かってしまっている。
だが。否、だからこそ、ここであっさりと負けを認めてしまうわけにはいかないのだ。
「……僕たちエルフは人間の五倍の歳月を生きているんだ。そう簡単に人間に負けるわけにはいかないだろう」
自分に言い聞かせるように独りごちたその言葉に。
「でも、私たち人間だってエルフの五倍の密度で日々を過ごしてますからね。そう簡単にエルフに負ける理由はないんですよ」
そんな言葉が軽く返された。
しかし、その言葉はもうシラムの耳には届いていない。
体術で勝てないのなら、鍛錬による技術で勝てないというのなら、せめて生来の才によるものでは勝たなければ。
もともとプライドを守る為に挑んだ無茶な戦いだ。それで更に負けている様では、本当に良いところ無しになってしまう。
既に思考に論理など無く、とにかくアリアに一撃を見舞いたい。その一心で選択した手段は。
「白き流れは縛られず、全き此岸を染め上げる」
口からなめらかに滑り出してくる呪文。そのひと言が鍵になったかの様に、全身が乳白色の液体の中に浸かっている様な錯覚に陥る。
粘っこさは無く、周りにあるそれらは自由気ままに一つの流れを作り、ただ延々とたゆたい続ける。
それは、この世を満たす白い魔力の流れだ。
「って、シラム、お前が呪文発動なんかしたら一体どうなっちまうのかわかってんのか!?」
オーウェルの驚いた様な声が聞こえてくるが、そんなこと知ったものか。
呪文を介して魔法を起動するという技術は、呪文という自己暗示によって世界と自分の境界線をより曖昧にし、また魔力を呪文という増幅回路に通すことによって魔法の威力を高めるものである。元から魔力に対する適性が充実しているエルフは本来そのような余分なステップを踏まずとも十分な出力を得ることが出来る為、魔法に対して未熟な者か、余程の大魔法を扱う者しかやらないことである。
この場合は後者。シラムの魔法熟練度を考えれば通常レベルのものを扱う分には呪文発動など全くもって必要ない。だが、そんなことは関係ない。
今は目の前の魔導騎士に一撃見舞う。自身をただその為だけの機械とし、自己を変革させる呪文を唱える。
「風は天に、天は宙に、宙はここに」
呪文発動は無理矢理魔力を増幅して魔法発動を行う手段である為、普段の魔法よりも遥かに時間と精神力が必要とされる。故に、多くの場合呪文を使うことによるデメリットはメリットよりも大きい。
しかし、今は相手がこちらに対して余裕を見せてやりたい放題させてくれている。ならば最大の威力でもって倒しに掛かるのも、一つの礼儀の様なものだろう。
そう自分勝手な理屈をつけて、シラムは自分の精神を魔力の流れの中に浸した。
周囲の魔力が強い粘性を帯びて自分にからみついてくるのを感じる。急に息苦しくなって、体が全力で魔法の発動を中止させようとする。が、それを精神力で無理矢理押さえ込んで体にまとわりついている魔力を呪文という回路の中に流し込む。
「へえ。流石はエルフですね。魔法は魔力の規模が違いますね」
アリアの感心した様な声を夢うつつに聞きながら、魔力にイメージを与えていく。
回路から今にも吹き出そうとしている魔力をなんとか押さえつけながら、荒れ狂う風の明確なイメージを脳裏に描く。
その標的はただ一人。目の前でふわふわとした笑顔を浮かべている少女、アリア。
目を見開く。ただその標的一点を見据えて、全ての魔力に命ずる。
「吹き飛ばせ、
その言葉とともに、それまでシラムの制御下にあった魔力が一挙に解放された。
一切物理的干渉力を持たなかった魔力の塊が突如として質量を持つかのごとく振る舞い、辺りの空気を猛烈な勢いで巻き込みながらアリアへと突進する。
地を這う砂埃、森を揺らす爆風、大気を唸らせて、一陣の烈風がアリアへと迫り。
距離がゼロとなり少女の体を襲った暴風は
ふわりと。
そのまま何事もなかったかの様にふわりと彼女の髪を揺らして空へと溶けた。
「……え?」
「はい、六十五点、ってとこですかね」
そう言って、アリアは右手の人差し指を伸ばして顔の前へと持ってくる。先ほどの豪風で巻き上げられた木の葉が一枚、彼女の顔の前へとはらりと落ちてきて、人差し指の真上辺りでぷつりと二つに割れた。
「分かります? ここにさっきの風の一部を捕まえてあるんですけれども、行きますから出来るのなら受け止めてみてくださいね」
そう言って、アリアは人差し指をくるっと一回転、そこに留めていたものをシラムの方へ放り投げるかの様にして、振った。
大気の唸りが聞こえたのは一瞬。
次の瞬間には、惚けたシラムの視界の中を髪の毛がはらはらと落ちていった。
「今ので、三回目ですかね」
前髪だけを狙って斬ることが出来たと言うことは、当然頭を真っ二つにすることだって可能だったと言うことだ。これで、シラムは先ほどからの短いやりとりの間で三回はアリアに殺されたことになる。それも三回ともカウンターに近い形でだ。これで彼女の方から攻められるようなことがあれば、一体何度死んでいたのか分かったものではない。
「魔術の下地がしっかりしていてこそ、大技の魔法が輝くんですよ。逆に言うと魔術でしっかり魔力を制御してやらなければどんな魔法だって意味がないんです。でなきゃ、さっきみたいにちょっとした魔術操作で魔法を解呪できちゃいますからね」
つまり、アリアは先ほど、シラムが放った魔法――つまり形を持った魔力の塊を、自分の魔術によってあっさりと支配下に置いて、暴風をただのそよ風に換えたというのだ。
勿論、理論上は不可能ではない。ただ、エルフの強大な出力から放たれる魔法を一瞬にして変質させることの難しさはいわんやである。
「……まったく、アンタ、何者だよ?」
「名乗りましたよね。ヘクセン魔導協会所属魔導騎士アリア・ムーシカです」
けろりと、まるで今までの戦闘が無かったかの様子であっさりとした笑顔を浮かべるアリア。その顔には勿論勝利に対する満足感のようなものは見られず、或いは彼女のことだから勝利したなどということも思っていないのかも知れない。
「とにかく、私と兄様はこれでこの先へ行かせて貰えるでしょうか?」
アリアの表情は、この期に及んで尚心配そうである。先ほどの実力差を見ればどう考えても最後の手段として力ずくで行った場合にシラムとオーウェルでは彼女たちを止められそうにない、ということに、まだ気付いていないのかもしれない。
「……勝手にすれば、どうぞ。それで良いですよね、オーウェルさん?」
「ん、ああ、まあ止めても無駄そうだしな。……一応理由だけ尋ねてもかまわんか?」
オーウェルがそう言って、不思議そうにアリアの方へと歩み寄る。
「この先には村の宝物庫があるんだ。そちらに異邦人が向かうことについて、何事か誰何するのも理解願いたい」
そう言うオーウェルに、アリアは笑顔をで応えた。
「ええ、それは勿論。私たちは実はこの村に《あちら側》の魔力反応を感じ取って来まして、その魔力反応があっちに……、あれ?」
懐から例の地図を取り出してオーウェルに見せようとした段階で、アリアの言葉が不自然に裏返った。
不思議そうに見つめるオーウェルを余所に、アリアは白い紙を日にすかしたり、裏から見たりしているのだが、地図には辺りの地形が描かれているだけでそれ以外のものは一切無い。
「兄様ー、例の反応が消えました」
「は?」
遠巻きにアリアたちの様子を眺めていたジグもやってくるが、彼が来たところで何が起きる、と言う話である。勿論なんの解決にもならない。
「……話が見えないのだが、つまりは《あちら側》の存在が宝物庫の方角に居たのだが、その反応が無くなっていると言うことか?」
「はい。そうなんです。騎士の誇りに掛けて嘘ではないので信じていただけないでしょうか?」
「嘘をつくのなら、もっとマシなつき方がありますし、信じますよ」
オーウェルはそう言って苦笑の様な笑顔を浮かべた。
「それで、どうしますか? まだ向こうに行くつもりはおありですか? あるなら案内しますが」
「あ、それならお願いしても良いですか?」
アリアの控えめな笑顔に、オーウェルが頷いた。
四人が宝物庫の方へと歩を進める。
その一角は村長の館がある以外はほぼ人家が無く、人影もまばらである。なんとなく気まずい沈黙が漂う中、靴音と風音だけが妙に耳朶を打つ。
そんな中で一行の向かいから一人の青年が、こそこそとまるで身を潜めるかの様に歩いてきた。
彼を目に留めて、シラムが肩をすくめる。
「アイツ、またやってるよ。もっと胸を張ってればいいのに」
シラムが揶揄する様に、確かに向かいからやってくる青年は背を丸めて明らかに不自然な姿勢で、まるで周囲のものから逃げている様に歩いている。
青年と、シラムの目が一瞬合う。すっと避ける様に視線を地に落とす青年。シラムたち一行の横を逃げるかの様に駆け抜けると、そのまま早足で彼らが来た道を戻っていった。
「今の方、どうかされたんですか?」
疑問を堪えきれないといった様子でアリアが恐る恐る訊ねた。
それに対してシラムはそっぽを向き、オーウェルが困った様に頬を掻いてぼそぼそと答えた。
「……いえ、ね。ちょっと変わり者なんですよ。まあ、気にしないでやって下さい」
よく、わからない。が、知らなくても良いことではある。恐らく今回の自分たちの目的とも全く関係ないだろう。そう思って、アリアは青年のことを忘れることにした。
青年の仄かに黄色を帯びた白金の髪の毛。
それが妙に印象に残ってはいたのだけれども。

四つの人影が昼前の日差しの中遠ざかっていく。
先ほどシラムたち一行の横を通り過ぎてそのまま離れていったはずの青年は、木の陰からこっそりと彼らの後ろ姿を見つめていた。
伸びてゆく道の上で少しずつ小さくなっていく四つの人影。
彼の視線は、先ほどからそのうちの二つ、灰色と薄桃色のローブに包まれた二人の人物にばかり注がれている。
「……人間?」
そう呟きながら羨望の視線を送るその人影は、シャルシュ・ワイゼンであった。
WEB版あとがき
どうも、はじめましての人ははじめまして、そうじゃない人はこんにちは。yoshikemです。よしけむ、だとかよしけん、だとか呼んでください。
さて、名称未定ではファンタジーもの書きを自称している僕なのですが、このサイトに今までアップしてきたものはどれもそれなりに現代に根を下ろした作品で、別にファンタジーでも何でもありませんでした。それではいかん、と気合いを入れ直し、漸くファンタジーものの原稿を挙げることが出来ました。それが本作、Monochronikaです。
これは、現在(2008/6/1)幻想組曲の方でちまちまと書かせて貰っているお話でして昨年までちょろちょろと書きためていたMonochromatic〜シリーズの続編という作りになっております。ですがこれ単品でも充分成立するように描いていくつもりなので、そこのところはご安心ください(え? 誰も心配なんてしていない?)。
幻想組曲のあとがきはキャラクターの雑談会になっているのですが、こちらはそれと差別化するという意味で作品裏話のようなものを書いていけたらな、と思っています。
というわけで、早速裏話を少々。いえ、エリアさんたちの誕生秘話、みたいなものでしょうか。
この世界で一番最初に生まれたのは、シャルシュです。モノクロはもともとシャルシュの物語だったんです。それが前作Monochromatic〜では傍若無人なエリアさんが主人公、シャルシュなんて生まれてもいません。それはなぜか。もともとはこのMonochronikaに相当する物語を独立した長編として書くという構想があり、そこから幻想組曲用にキャラをいくらか取り出して別の物語に仕上げよう、ということで作られたのが前作のMonochromatic〜なのです。本当は前作もあんなに続くつもりはなかったんですが、エリアさんたちが予想外に良い仕事をしていたのでだらだらと長いものになってしまった、というところでしょうか。
大学一回生と二回生、二年間を掛けて世界観を当初考えていたものより密に詰めることが出来ました。お陰でシャルシュたちの世界は本来僕が想定していたものよりも遙かに生き生きと動いてくれそうです。
エリアやシラム、オーウェルなどの前作からのキャラもそこそこ登場しつつ、シャルシュとアリアの物語が今幕を開けます。完走できるよう頑張りますので、お暇でしたらどうぞお付き合い下さい。
前作に関しても、またぼちぼちとアップしていきたいと思っています。と言うことを昨年春にも言っていたので、信憑性は低いのですが……。でも出来ればエリアさんの物語もアップしたいと思っているんですよ。
作品展示室トップへ
総合トップへ